煌きを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いでくれます。
男の器量・女の器量―
パーソナリティ 榎本 勝起氏著
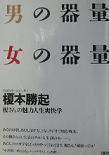
挨拶。―この字をよく見て誰もが感じること。それは、「挨」の字も「拶」の字も“手へん”
挨拶するときは、お互いの心に近づき、手をかけ、誓い、お互いの心を見せ合いましょう、という意味が、この言葉にこめられている。
 春。―今年もまた多くの学生たちが学舎を巣立っていった。卒業パーティでは、振袖をまとった女子学生の姿も多く見受けられた。
春。―今年もまた多くの学生たちが学舎を巣立っていった。卒業パーティでは、振袖をまとった女子学生の姿も多く見受けられた。
しかし、その手を見たとき、あまり感心できない光景が少なくなかった。右手にワイングラス、左手に料理皿。これでは山賊である。
パーティで両手をふさぐことは、恥ずかしいこと。どちらか一方の手は必ずあけておくのが作法。挨拶をするために・・・・。
左手の手ぶりがあって初めて本当の挨拶ができてくるからである。
その、両手にワイングラスと料理皿を持った女子学生のところへ、彼女の教授と思(おぼ)しき人が近づいてきた。
「やあ、おめでとう。本当に良かったね」
教え子たちの晴れ姿に、心を躍らせながら教授が話しかけた心のノックに対し、彼女はポッンとひと言、「どうも!?」と、「ど」の音に力を入れて。
一瞬、教授の顔に複雑な表情が浮かんだ。柔和ななかに、こんな思いを訴えているようだ。(自分は、この娘さんを、この程度にしか教えられなかったのか)と・・・・・。
いままでは、若さが彼女のアラを隠してくれた。だが、このまま歳月の流れるままに、「どうも」のひと言しか言えない女性、「どうぞ」の言えない女性になったとしたら・・・・。
三流の女に、三流の男が近寄り、
三流の男に、三流の女が近寄り。
もし、一流の女に一歩でも近づこうとするならば、恩師である教授に対しても、こうした返事ができるはずだ。「先生ほんとうにありがとうございました。おかげさまで、この四月から社会人になることができます。これからも、よろしくお願いいたします」
感謝の気持ちをこめて話すときの三つの「お」。
一、お願いします。
二、おかげさまで。
三、おそれいります。
これが自然に唇からでるようになって、初めて周囲から尊敬されるレディ誕生といえる。
高尾山の方丈さんがいった言葉を思い出す。
「俺が(我)俺が(我)の(我)を捨てて、おかげ(下)おかげ(下)の(下)で生きよ」
この心がなくて、藤井丙午氏のいった「他人の、部下の後姿に、こちらから声で挨拶する度量」はなかなかつかない。
人間は、最後のひと言、そして語尾のニュアンスで心を動かす
「ね、さ、よ、廃止運動」というのがあった。
四十数年、横須賀の小学校の校長先生が、児童たちの言葉があまりにも乱れているので、それを改めようとしたキャンペーンのこと。
「ワタシねェ、ゆんべ遅くまでェテレビを見てたらさァ、お母さんが怒っちゃってさァ、それでフテ寝したのゥ。朝起きたら起きられなくってよう・・・・・」
言葉の区切りが「ね・さ・よ」で終わっている。これを、普通の話し方にしようとしたのだ。
それから二十数年(平成5年頃)。「ね・さ・よ」を禁止されたはずの子供たちは、もう立派な社会人。しかも、その彼女たちが、いま使っている言葉は、残念ながらあい変わらず「ね・さ・よ」。しかも、その間に「ウッソォ」「ホントォ」「イヤダァ」という言葉が入っている始末。
この「ウッソォ」「ホントォ」「イヤダァ」は『痴呆的感嘆詞の三役揃い踏み』である。
乱れに乱れている話し言葉。特に、語尾の乱れは、聞く人の心に無味乾燥の風を吹かせる。
私は、これを「語尾の砂漠」と呼んでいる。人間関係の潤いを干しあげるからだ。このほかに、「です」「ます」がいえない「デスマス(苦)の人も、語尾の砂漠の熱シンドロームの人。
日曜日。喫茶店に、若い女性が入ってきた。しばらく店内を見渡してから、一つの席を見つけ近づくやいなや、「待ったァ―」
“たァ―”の二文字の中に含まれる心の匂いは、まさに馴れきった男女のもの。待たせてゴメンナサイといった気持ちのカケラもない。魅力の片鱗もない。
少々キツイ表現だったかもしれない。しかし「待ったァ」といわれた相手の気持ちとしては、そう思わざるをえない。
“たァ―”のァの字を全音符にして、品がないものにしている。ァの字を十六分の一音符に短かくした方が…。小走りにかけより、両肩で息を整えながら彼を見あげて、
「待ったァ」
この言葉の最後の語尾にまで自分の心を込められるようになれば一人前。
「秋山君!!係長の辞令だ。期待しているよ!!」上司の語尾に部下は背筋を伸ばす。
その想いは、相手に必ず通じる。自分の言葉の語尾まで気をつける上役、妻、女性なら、一人に限らない。多くの部下や男性から熱いまなざしが送られてくる。
人間というものは、最後のひと言、最後の言葉、そして語尾のニュアンスで心を動かし行動する。
「胸にしみます、ジンともきます
心の余韻と除夜の鐘」
「鹿鳴館」の幕切れの台詞「それでこそ、あなたですわ」の「わ」に、また映画「ジェーン・エアー」の好きな人に名前を呼ばれて応える「イエース」の「ス」に、愛ある人の語尾のゆかしさを感じる。
「食べちゃった」「行っちゃった」の“ちゃった言葉”は、
可憐さと醜悪さを秘めた幼児語
大阪の人は、郷土愛がたいへん強い。
自分の故郷の言葉を誇りにし、またその言いまわしが骨の髄までしみこんでいる人が、わりあい多いもの。
五人のうち二人が大阪弁を使うと、いつのまにやら五人の会話は“大阪言葉”ですすんでいることが、よくある。
箱根の山を越え、東京に行っことのないのに東京弁を使いたがる人。こういう人が使う「ちゃった言葉」などを、大阪では、
「行かず東京弁」
という。エーカッコシイの見本の一つだ。
具体的にどんな話し方を指すのだろうか。「ちゃった言葉」が、その代表格。
「きのう、新宿で徹夜しちゃった」「六本木へ飲みに行っちゃった」
「主任試験に落ちちゃった」。
これは、使い始めると、麻薬のように習慣となる。なかなかぬけきれない。いかにも都会風の響きが、この言いまわしのなかにあるのだろうか・・・・・。「ちゃった」というのは、音声心理で分類幼語。子供の話し言葉である。
それを大人が使うのは?
ブリッ子という表現が一時流行したが、幼語は自分を“可愛らしく見せようとする意図”が相手に伝わったとき、醜悪な言葉に変化する。
ブリッ子というのは、そのあたりを鋭く指摘した表現だったのかもしれない。
「ちゃ」は、音がハネている。どこか硬い響き。語尾の舌端破裂は心の破裂である。
それに比べて語尾の「ね」。これを優しくつかうとき、音が鼻にぬけ、柔らかい無響きを感じさせてくれる。
そういえば、ハネているような音の「ちゃちゃ」と、しっかり落ちついた「ねね」。秀吉の側室と正室である。
茶々は、後の淀君。ねねは北政所(きたのまんどころ)。
茶々は大阪城のグレンの焔(ほのお)のなか、我が子の秀頼とともに生涯を閉じ、寧々(ねね)は、その後天下を取った家康に手厚く礼を尽くされ、一生を全うしている。
男の品定めで話題にしていけない五つの“か” 男の品定めの五戒。
女性にとって、これほど楽しいものはないといえる。
いくら男の品定めをしようとしても、言葉に出して話題にしてはいけない事柄もある。それを私は五つの“か”と呼んでいる。
「顔」(かお)(からだ)
「金」(かね)
「学歴」(がくれき)
「会社」(かいしゃ)
「家庭」(かてい)(かぞく)
この五つの“か”。
しかし、五つの“か”を除いたら男の品定めなどできるものではない。同じ「か」でも自分の「過去」ばかり友達に告げたがる“過去告白魔”はいるが―。なぜ、この五つの“か”を言ってはならないのか。それは、「顔」「金(収入)」、「学歴」、「会社」、「家庭」のことを他人が噂をしても、どうにもならないことだからだ。
知らず知らずのうちに、他人の心のなかに土足で入りこんでいるからである。
会社は、楽しければ何を話していい、というものではない。会話のテーマは、自分が意識して選ぶようにすべきだ。言葉を口にする前に、ちょっとだけ自分の心を通過させ、話すべきどうかを考えてみよう。
無口は困りもの。
しかし、饒舌はそれ以上にやっかいなもの。
たったひと言、よけいな言葉をしゃべったばかりに、自分の人生を大きく狂わせた人が、この世の中には意外と多いもの。
「火を消すのも口の息、火を起すのも口の息」
「部下をやる気にさせるのも上役のひと言、部下からやる気をなくすのも上役のひと言」
何も考えず、惰性で喋っている怖さを知るべきだ。
二十代後半、三十代前半、後半…・と、年齢を重ねるとともに、自分の話し方も話題も変化していなければならない。それには、「いうべきこと」「いってはならぬこと」を自分なりに心の奥にしまっておくこと。
家康がいっている。
「その男が、どんな魅力の持主か、どんな過去の失敗があるか、いっさい忘れて使い切ってみれば実力以上の力を出してくれるものだ」と―。
人間として、いってはならぬ言葉。この辺をわきまえておかないと、思いがけない火傷をするもの。
例えば、こんな会話があったとする。
もうあとわずかで定年を迎える人。健康を害し、しばらく会社を休んでいたのが、今日から出勤してきた。これを迎える同室の若手社員。バリバリの現役で、やることなすこと仕事がおもしろくて仕方がない年ごろ。
若手社員がいう。
「元気じゃありませんか。お若いですねェ。同期の皆さんが“お化け”と呼んでいますよ。こんど機会があったら若さの秘訣を教えてください。それじゃァ、失礼します」
これを耳にした定年まぢかの社員の心を忖度(そんたく)すると、つらく悲しい気分が充満しているのではないだろうか。
「元気ですね」というのは“年齢に比べて”という枕詞を省略している。「お若いですね」とは、あなたの本当の年齢は十分承知ですよ、という意味だ。
「お化けといっていますよ」は、若く見えることだけが取柄です。というウラの意味。
「若さの秘訣を教えてください」とは、それ以外の仕事のことや、あなたの持っている知識を教えてくれなくても結構です。という気持ちが含まれている。
こう書くと、なにもそこまでヒネクレた見方をしなくてもいいじゃないか、という声が聞こえてきそうだ。
しかし、ヒネクレているわけではない。これは、自信満々の若手社員が、自分の気持ちを別の表現に置き換えて喋った結果から起きたもの。
もし、この若手社員が相手の気持ちになったら、はたしてこれだけ喋るだろうか。
これほどまでの饒舌にならなかっただろう。たぶん、定年まぢかの社員を勇気づけている自分に酔っていたのだと思う。
たとえホメルにしても、決していってはならない事柄もある。
「年齢」「健康状態」
この二つである。
これにつけ加えるなら、相手の「直せない性格」。
会話のタブーをわきまえることによって、人とのコミュニケーションが円滑にいくもの。特に組織のなかで働く人間にとって、このことは肝に銘じておきたいもの。
平社員は、いえるときにいう。
上役は、いいたいときにいう。
「いえるときにいう」ことは、「いえないときには決していわない」こと。サラリーマンの哀しい知恵の一つである。
人に自分の言葉を理解してもらうために、ゆっくりすぎるほどの「間」を置く。
「話し方」テーマにした本、セミナー、講演があいかわらず盛んなようだ。
なぜ人は、そんなに「話し方」についてこだわるのだろう。人はだれでも毎日話している。それで生きていける。なのに、どうして…・。
私たちが日常で何気なく喋っている言葉は、それほど正確さを必要としないから、簡単な言葉の羅列だけでこちらの意思が通じる。未開発の原住民でも同じだ。
しかし、いったん正式な意思伝達をしょうとするとき、日常の“原住民的話し方”では通用しない。人間の思索、感情。心、周囲の状況にのっとった話し方を要求される。それは、形式ばった表現を求められているのではなく、相手が十分理解できる話し方を要求されている。という意味。
そうである。相手に理解してもらうこと。ここに話し方の根本原理がある。話し方に限らず、文章にも同じことがいえる。だが、一般に販売されている書物のなかにも、理解されることを拒んでいるとしか思えないような文章に出会うことがある。
「崖越しに吹きつける北風の威力は、家屋の端のところに白けた数本のもみの木がひどく斜めに伸びていることからも、また立ち並ぶやせこけたばらの枝々がどれもこれも日光の恵みを求めて、一方へばかり腕差しのべているさまからも、容易に察せられる」
どこが「容易に察せられ」るか!!。全然察せられていない文章である。「嵐が丘」の翻訳文。
もし、このような“名文”で企画書や報告書を書いたていたのでは、内容以前に失格になってしまう。まして、それを棒読みするなどもってのほか。
きっと、そういう話し方はスピードが早く、理解しずらいのかもしれない。「間」がないのだ。
先年、日本の歴代総理の施政方針演説、または国会内での質疑応答のスピード・ベスト10が発表された。
トップは、驚くなかれ、鈍牛といわれたアーウー宰相といわれた大平正芳さん、一分間に290字の文章を話された。
第2位は中園康弘氏。269字だ。
同じような調査が、その後。ラジオ、テレビのタレント、アナウンサー、俳優たちを対象に、「会話のスピード」をテーマにおこなわれた。それを計測したのがコンピュータ。
その結果、思いがけないことが出てきた。「昭和時代のこの日本において、最もゆっくりと喋る芸能人は古今亭志ん生さん、第2位は榎本勝起TBSアナウンサー」という調査結果。
それを聞いて、私は鳥肌が立つほど感動した。つねに聞き手の理解を第一義に考えセンテンス、フレーズのあいだに「間」を取ってきた私の姿勢を、客観的な数値ではじき出すコンピュータが証明してくれたのだ。
「風の又三郎」を放送したとき、同録テープの希望が、御親戚から送られてきた。宮澤賢治記念館に永久保存するから、と―。
世の中に、ブスという意味の二つあり、言葉のブスと狂言のブスここで、話し方をテーマにした道歌を二,三首披露しよう。
「心せよ、いってはならぬひと言は、心の底の奥深く秘め」
「話し方、電気ドリルに、似た人の、次つぎ穴を人の心に」
「フラッシュを、たいて写真を撮るごとく、ストロボ言葉、むやみに叩き」
「一言が、十言につらなり、出る口の、抑えもきかず、不幸をばらまき」
最近は、日本の女性も化粧が上手になり、ちょっとドレッシィな服を着ていると、どなたでも美人に見えてくる。
「Beauty but skin deep」といわれても、われわれ男性にとって、これほど歓迎することはない。
「美人が多いこと」ほど気分のいいものはないのだ。
しかし、外観は美人だが、いざ彼女たちが口を開き、言葉を喋り始めると、もう無残。手垢のついた、あるいは指紋のついた言葉を何度となく繰り返し、必要以上の甘え声で話をしている。
先日、ある美人カメラマンと言われている人がテレビ対談で、こんなことをいった。「そうですねェ、シャッターはここ一番というときにはヤタラメッタラに切ります。チンタラチンタラしていたら、チャンスを失くしてしまいますからねェ」―。
この女性カメラマンが、いかに芸術的アングルで女性ヌードや自然の一部を切り取ったとしても、こんな言葉づかいの人で、観る人を感動させる写真が撮れるだろうか。
私は、こういう女性たちのことを、「言葉ブス」と呼んでいる。
女が美しく見える、その話し方。しぐそ、物腰、表情、そして教養、知識、まわりの人への配慮といったことまで含めて、美しさは問われるもの。
しかし、そんなことはお構いなし、とにかく外観をよくすれば美人になれる、と思っている女性たちが最近とみに多くなっているようだ。
その象徴的光景を、私は、東京の赤坂で見かけた。横断歩道での出来事。
向こう側から歩いてきた女性が、なんと口紅をぬりながら交差点を渡ってくるではないか。これには驚いた。
昔、男の前で化粧するのは、吉原の花魁(おいらん)か、宿場女郎ぐらいのもの。市井の女性たちは。男の人の前では決して化粧などしなかった。恥ずかしいことだからだ。女の楽屋裏をのぞかせているからである。テーブルで鏡をのぞくのは三流だ。
ストリッパーは、舞台の上で、すべての衣装を脱ぐ。でも、楽屋に入れば衣装を着る。その衣装をめくろうとする男がいたら、彼女たちはその手をピシャリと叩くであろう。恥の心のなんたるかを知っているからだ。
横断歩道で口紅をぬっていた女性。彼女は“楽屋で衣装を着ないストリッパー”である。
心の姿勢がなっていない。その唇から出る言葉も想像できる。狂言の附子(ブス)は、甘い砂糖にまつわる。和尚と小僧のはなし。言葉のブスの女性の唇に甘さは期待できない、暖かさも―。
「バスでブスとボスにはさまれ、
ビスをふくんでベソをかいた」の早口言葉
青春はオードブル、無熟年はデザート、私の日誌に、こう書いてあるページがある。
とすれば、次の話はまさにオードブルのハッラッさが感じられる。お菓子。小指の先ほどの小麦粉を団子状にし、きな粉をまぶしたもの。
「まァ、可愛い」「おいしそうじゃない、何ていうのかしら」
と、OLたちが話していると、新入社員がひと言、「天使のオチンチン!!」
これには、居並ぶ先輩のOLたちも大笑い、思わず吹いてしまい、あたりは“オチンチン”のきな粉だらけになってしまった。
吹く、といえば、ついつい自分の心を無意識のうちに吹きだし
ていることもある。周囲に笑いを振りまく、話題を吹くのは結構。だが、こんな吹きは困る。
早口言葉を喋らせてみると、その人の潜在的性格が端的にあらわれる。私の作った早口言葉。
「バスでブスとボスにはさまれ、ビスをふんでベソをかいた」
この短い言葉のなかに、バ行音(バビブベボ)が含まれている。
これを、お嬢さんに発音してもらう。
すると、その人の話術がどのていどか、そのひとの置かれている立場がどうなのか、その人の性格はどのようなものか―といったことがわかってくる。
まずバスの「バ」そして「ビブベボ」。この音を意識的に強くいう人、つまり上唇と下唇を必要以上に破裂させて言う人。こういうお嬢さんは、たいていわがまま。他人の言うことをあまり聞かない。いつも心の片すみで不満を抱きながら生きている。そんな感じの人が多いようだ。
「風と共に去りぬ」のスカーレット・オハラのように「パトラーを必ず取り戻して見せる」と自ら誓う激しい気性の女性に多い。
次にバスの「ス」「サシスセソの音を軽く発音する人」は演歌がうまい、といわれている。聴く人に、語りかけるような唄いまわしが、擦歯音を抑え、その音が人々の琴線に触れるからだ。
これは、歌に限らない。ふだん私たちが話しているときでも、サシスセソの音を軽く発音できる人は、人間の情を理解している人といえる。逆に、バスの「ス」の音が、聴く人の耳に残るような話し方をするお嬢さんがいたら、その女性はササクれだった勝ち気な性格である。
その昔、学校に通っていたころ、先生が教室にくる気配を察した女生徒が、まわりの生徒を制して「シー」と人差し指を唇に当てるというようなことがあった。
それにつられて、他の生徒は静かになる。けれど「シー」といっている御本人の音声だけが、異様に教室中に響きわたっていた。
他の生徒を制するほどの性格、勝ち気な女の子だった。
そんな、小さなころの性格までもが「バスでブスとボスにはさまれ、ビスをふくんでベソをかいた」という早口言葉で見分けることができる。
「弁慶と、小町は、馬鹿だ、なあ嬶(かかあ)」という川柳(せんりゅう)。弁慶の「ベ」(バ行)と、馬鹿の「バ」が、なぜか、おかしく哀しい。意味? それは、そちらでお考えを…・。
人間の魅力とは、三割の秘密をもつことだ―
「人間は、何にでも飽きてしまうものだ」
と、いったのはドストエフスキー。
人間関係とはむずかしいもの。飽きられないためには、三割の秘密をもつことだ。とよく耳にする。
秘密。それは、過去、現在に自分の見聞、体験したことを、ひた隠しに隠す、ということでない。相手にとって「未知」なものを、つねに三割ほど心の底にもて、という意味である。
珍しい話、おもしろい話、ためになる話、笑える話…・こういう情報をつねに自分の頭の中にプールして、いつも新鮮な自分を相手に見せる、聞かせる。
チャーリー・チャップリンが、ダグラス・フェアバンクスと夫婦で日本やってきたときのこと。
彼の日本でのスケジュールのなか、東京、大阪の各地で公演があった。そのいずれも同じ内容で、すますわけもいかない。
そこで、チャップリンはカードをつくり、それぞれに各テーマを書きこみ、シャッフルして、一枚一枚を取り出した。
「こうもり傘」「洗濯機」「赤ちゃん」といったテーマが書かれたカードは、各公演会場名が記入された一覧表のうえに、順番におかれていった、という話がある。
あのチャップリンでさえ、人に飽きられないために、かげで努力している。
人間は、核(コア)の部分は、歳をとってもそれほど変わらない。しかし、それを包む部分は、つねに新鮮にしておかなければ、成長は止まってしまうもの。
初めて会ったとき、全身に「電気が走る」ほどの衝撃を受け、その人のすべてが新鮮で、好きになれたのに、いまでは会うたびに「虫酸(むしず)が走る」というようになったとしたら、それは脱皮を図ることを怠った人間から滲み出る、古いニオイのせいではないだろうか。(いつ、どこでそんな話題を?)
そのためには、自分が現在もっている物の考え方の整理箱を全部開け、頭の中を空っぽにするほどの勇気をもつことが必要。これは恐怖だ。しかし、その恐怖を乗り越えられないのでは、“また逃げられた”ことをまた繰り返すのがオチになる。
大臣に“叱正術”を伝授、
他人の前で叱らなかった清水の親玉
明治時代というのは、どこか憎めない。“いたずらッ子”のようなところがある。
戸籍がしっかりし、役所のシステムができあがりすぎてしまった現代から見ると、明治時代は実に奔放であり柔軟であったようだ。
明治・中央政府の榎本武揚逓信大臣が、東海道の清水次郎長大親分を訪れた。事情聴衆をするためではない。依頼に来たのだった。「親分、ぜひとも親分にお教えいただきたいことがあって、はるばる東京から参りました」
「それは、御苦労で…・。で、その御用件とは?…」
「ほかでもございません。人使い、のことでございます。私は中央政府で四〜5百人からの人間を使って業務を進めていますが、なかなか人身掌握の術というのはむずかしい。
そこで、清水の二十八人衆の面倒をみて、ひところは東海道5千人からの子分衆をアゴの先で使ってらした方、その大親分に、どうやって人を使いこなすのかをお聞きしたいと思いまして、こうやってうかがった次第です」
そのへんが明治という時代のおおらかさ、中央政府の役人が、やくざの親分に人身掌握の術を聞きに来るとは…・。
「そのように、あらためて聞かれてましても、なァ……。
とんと自分ではわかりませんが」
「いやあ、そんなことをおっしゃらずに、ひとつお教えを願いたいのですが」
ここで、次郎長、ハタと、思いつき、
「そういえば、他人を叱るとき、私は絶対に人前で叱ったことはございません」
「人前で叱ったことがおありにならないと?」
「へえ。大政、小政だろうと、十五歳の使いっぱしりのどんなつまらない野郎でも…・」
これを聞いた榎本武揚「ありがとうございました」と深々と頭を下げ、帰って行ったという。
もし、織田信長が、明智光秀をその家来の前で面罵(めんば)していなかったら、日本の歴史は大きく変わっていたと言われている。
叱り方のむずかしさは、ほめることの百層倍、とはいつの世も同じこと。
巨人軍の元監督の長嶋茂雄氏に、ご自宅近くの中華料理店でインタビューしたときのことだ。
「レギュラーは九人ですが、二軍を含むと六十人近い選手が巨人軍の中にいます。この六十人を、皆同じように叱っていたのでは、すぐれた才能もつぶれてしまいます。選手の個性にあわせて、それぞれ叱り方を変えています。チーム全体のブラティクスのミスはその場で、個人的なアドバイスは一人のときにやります。
つまり、体罰に近い激しい叱り方をして納得するものもおれば、優しく噛んでふくめるようにいって理解する選手もいる。要は、納得させることですからねェ―」
ちょっとした気づかいで、叱り方の効果がグーンとアップ。それこそ、人間関係の妙が生まれてくる。
多すぎると枯れる。少なすぎると育たない
―“言葉”は人間関係の肥料だ「無駄なこと 無理に 無口な 無言劇 能力者と 無視され 無念」道歌「無」。
昭和二十年8月15日以来の日本人にとって、「沈黙は愚者の甲冑(かっちゅう)である」と私はいいつづけてきた。
沈黙は金(きん)ではない。喋らなければ結局自分がバカを見る。
敗戦はそれを私たちに教えてくれた。「お上のやることだから、われわれは黙ってついていけばいい」という愚かな考えを、完膚なきまでに叩き潰したのが、敗戦という現実だった。
「もう騙されないぞ。言うべきことは断固としていうぞ」と心に誓ったものだ。だが、喋ればいいというものではない。
このへんが難しい。
「お喋りは分母、多いほどに価値が下がる」
悪い分母の形は、大きく分けて次の三つになる。
多弁―多く喋りすぎること 詭弁―自分の論理を強引に正しくし、相手の意見をねじ伏せてしまう強弁―強がりをいうことこの「三弁」を、心の中に楔(くさび)として打ち込んでおかないことには、喋りすぎの害をまき散らす結果になる。こう考えてくると、話すことと、その素材である言葉はなんと複雑で、やっかいなんだろうと思うことがある。
アナウンサーという仕事をつづけるほどに、言葉の使い方の奥の深さに、いまさらながら驚いている。
「言葉は人間関係の肥料だ。多すぎると枯れる。少なすぎると育たない」加減、という、ほどのよさ、である。これを承知しながら、話ができる人が、男も女も優秀な人となる。
では、具体的には、どうすればいいのだろうか。
それは、私がこの本で再三指導しているように、まず第一歩は、
「聞き耳をもつ」こと。人の話を聞く。最後まで聞くのだ。喋り終わった相手は、今度は必ずあなたの意見を聞こうとする。人間は、自分の意見を心地よく喋った後は、人の話をきこうとするもの。
第二は、「恥をかいてもいい、意見をのべる」こと。
世間体を気にして何も話さないほうが、よっぽど恥だ。そして
第三は、「人の意見をはじめとする情報をメモる」こと。
これをつづけていれば、あなた自身の人間関係の本を、大樹に育てあげることができる。