ガチャ、という音と共に、全身に戦慄が走った。イク時なんかよりもずっと強烈な戦慄に、私は鳥肌を立ててヒクッと短い痙攣した。胃に力が入り、それと共に何故か膣にも力が入った。エクスタシーと同じように、陰部全体が痺れた。
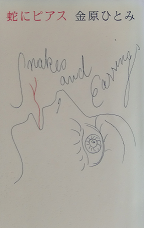 金原ひとみ著
金原ひとみ著
蛇にピアス 金原ひとみ
「スプリットタンって知っている?」
「何? そけ。分かれた舌って事?」
「そうそう。蛇とかトカゲみたいな舌。人間も、ああいう舌になれるんだよ」
男はおもむろにくわえたタバコを手に取り、べろっと舌を出した。彼の舌は本当に蛇の舌のように、先が二つに割れていた。私がその舌に見とれていると、彼は右の舌だけ器用に持ち上げて、二股の舌の間にタバコを挟んだ。
「‥‥すごい」
これが私のスプリットタンの出会い。
「君も、身体改造してみない?」
男の言葉に、私は無意識のうちに首を縦に振っていた。
スプリットタンていうのは主にマッドな奴らがやる、彼等の言葉でいえば身体改造。舌にピアスをして、その穴をどんどん拡張していって、残った先端部分をデンタルフロスや釣り糸なで縛り、最後にそこをメスやカミソリで切り離し、スプリットタンを完成させる。と、彼は手順を教えてくれた。ほとんどの人はこのやり方で改造するらしいけれど、中にはピアスなしでいきなりメスを入れる人もいるという。大丈夫なの? 舌嚙み切って死ぬんでしょ? っていう質問に、蛇男は淡々と答えた。
焼きゴテを当てて止血するんだよ。手っ取り早いけど、さすがに俺はピアス使ってる。ピアスでやると時間はかかるけど、いきなり切るより綺麗な切り目が出来るのだ。私は血まみれの舌に焼きゴテを当てるシーンを想像すると、腕に鳥肌が立った。今、私の右耳には0Gのピアスが二つ、左耳には下から0、2、4Gのピアスが並んでいる。ピアスのサイズはゲージという単位で表され、Gと略される。ゲージは、数が小さくなっていく程太くなっていく。
普通の耳ファーストピアスは、大体16Gから14Gで、太さは一・五ミリ程度。0Gで、これが九・五ミリ程度。それ以上の物は分数で表され、一センチを超える。でも、はっきり言って00を超えてしまうとどこかの民族みたいで、かっこいいとか悪いとかの話ではなくなってしまう。耳の拡張でもかなり痛いと思ったのに、舌の拡張なんてどれだけ痛いのか想像もつかない。
元々16G程のピアスをしていた私はクラブで知り合った二つ年上の女の子、エリの00Gに憧れて拡張を始めた。「かっこいいね」と言うと、えり「ここまでやっちゃうともう細いのは使わないから」と言って12から0、までのピアスを何十個もくれた。16から6くらいまでは、難なく拡張出来た。4から2、2から0、これはもう拡張そのもの。
穴には血が滲み、耳たぶは赤く腫れ、二、三日はじんじんしている。0にするまでに三ヶ月もかかった。エリの信念「拡張機は使わない」これを私も引き継いだ。そろそろ私も00に踏み込んだか思っている頃だった。拡張にハマっていた私はスプリットタンの話をかじりつくように聞いた。男はまんざらでもなさそうに語ってくれた。
そして数日後、私は蛇男ことアマと二人でパンクなDesireに来ていた。その店は繫華街の外れの地下にあって、入るなり目に飛び込んできたのはもろに女性器がアップの写真。ビラビラの部分にピアスが刺さっていた。他にも、タマにピアスが刺さっている写真や、刺青の写真。そんなのが壁に貼ってあった。中に進むと普通のボディピアスやアクセサリーもあったけど、ムチやペニスケースまで並べてある。
私に言わせてもらえれば変態向けの店だった。アマが声を掛けるとカウンターの中から頭がひょこっと現れた。その頭はスキンヘッドで、つるつるの後頭部に丸くなっている龍が彫ってあった。
「おー、アマ、久しぶり」
多分、二十四、五くらいのパンクな兄ちゃん。
「ルイ、この人が店長のシバさん。あ、これ、俺の彼女っす」
はっきり言ってアマの女のつもりはなかったけど、黙ってシバさんに会釈した。
「あー、そう。可愛い子捕まえたねえ」
私は軽い緊張で、どうも落ち着かなかった。
「今日は、こいつの舌、穴開けてもらおうと思って」
「ふうん。ギャルも舌ピとかするんだ」
シバさんはもの珍しそうに私を見た。
「ギャルじゃないです」
「こいつもスプリットタンをやりたいって言うんですよ」
アマは私の言う事なんか聞いてないようにイタズラっぽく笑った。いつだかピアスショップで、性器以外のピアスで一番痛いのは舌ピだと聞いた事がある。こんなパンクな男に任せて平気なんだろうか。
「お姉ちゃん、おいで。舌見せて」
カウンターに近づいて舌をベロツと出すと、シバさんは軽く身を乗り出した。
「あー、まあまあ薄いからそんなに痛くないと思うよ」
私はその言葉に少しほっとしていた。
「でも、焼き肉だとミノの次くらいにタンって歯ごたえありますよね」
ずっと思っていた。あんなにプリプリしている肉に穴を開けるなんて、大丈夫なんだろうか。
「お姉ちゃん、いいとこつくね。うん、まあ耳とかに比べたら痛いよ。まあ、ね。だって穴開けるんだもん、痛いよそりゃ」
「シバさん怖がらせないでくださいよ。大丈夫だよルイ、俺だって出来たんだから」
「何だよ、アマだって開けた時は悶絶してたじゃねーかよ。いいや。おいで」
シバさんがカウンターの奥を指差して私に微笑んだ。笑顔が歪んでいる人だと思った。シバさんの顔は瞼、眉、唇、鼻、頬にピアスが刺さっている。こんなに武装されたら、表情なんて分からない。それに、シバさんの両手の甲は一面ケロイドに覆われていた。一瞬火傷かと思ったけど、チラッと観察するとそれが全て直径一センチ程の丸である事に気づいた。
根性焼きでケロイドを施したんだろう。全く、狂ってる。こういう人種と関わるのは、アマが初めてだった。そして、このシバさんという人は舌こそスプリットではないものの、顔中のピアスが近寄りがたくさせていた。アマと一緒に奥の部屋に入ると、シバさんはパイプ椅子を指差した。座って部屋を見渡す。寝台や、私にはよく分からない器具、壁にはやっぱりきわどい写真。
「ここって、スミもやってるんですか?」
うん、俺も彫り師なんだよ。これは人にやってもらってるんだけど」
シバさんはそう言って頭を指差した。
「俺もここで入れたんだ」アマが言う。
アマと知り合ったあの日、私たちはスプリットタンの話で盛り上がり、私はアマの部屋に持ち帰りされた。アマは舌ピを拡張していく過程やメスで切り裂いた時の様子を写真に収めていて、私はそれを一枚一枚じっくり眺めた。アマは00Gまで拡張し、メスで切り離した部分はほんの五ミリ程度だったけど、驚くくらい血が流れていた。
それからアマは舌を切り離す映像をネットで公開しているアンダーグランド系のサイトに行き、その映像を私はアマが呆れるほど繰り返し何度も見た。どうして自分がこんなに興奮しているのか分からなかった。その後、私はアマと寝た。寝た後、左の二の腕から背中にかけての竜の刺青をかっこいいでしょー? と自慢するアマを受け流しつつ、スプリットタンを完成させたら刺青もやってみようと思った。
「刺青、やってみたいな」
「ほんとに?」
シバさんとアマは声を揃えた。
「いいね、絶対綺麗に入るよ。あのね、刺青っていうのは男なんかより女がやった方が断然綺麗なんだよ。特に若い女の子はね。肌のキメが細いから繊細な絵が彫れるんだよ」
シバさんは私の二の腕を撫でながらそう言った。
「シパさん、ピアスが先っすよ」
しばさんは、「ああ、そうか」なんて言いながらスチールラックに手を伸ばし、ビニールに入ったピアッサーを持ってきた。ピストル型の、耳に穴を開けるのと同じようなやつ。
「舌出して。どの辺に開ける?」
鏡の前で舌を出して、先端から二センチほどの中心に指をさすと、シバさんは慣れた手つきで私の舌をコットンで拭き、指差した部分に黒い印を付けた。
「テーブルに顎を載せて」
私は舌を出したまま言われるままに体を低くした。舌の下にタオルが敷かれ、シバさんがピアッサーにピアスをセットした。私は思わずシバさんの腕をバシバシこづき、首を振った。
「ん? 何?」
「14にして。お願い」
私は必死になって、反対するアマとシバさんを説得した。耳のファーストピアスだって、いつも14か16だった。シバさんは14のピアスをセットし、もう一度「ここね?」と確認した。私は軽く頷き、拳に力を込めた。すでに手は汗ばんでいて、ぬるぬるした感触が気持ち悪かった。シバさんはピアッサーを縦にして先端をタオルに押しつけた。そろりと舌を挟み、舌の裏に冷たい金属が当たった。
「オッケー?」
シバさんは優しい声で聞き、上目遣いで軽く頷くと、いくよ、小さい声で言って指を引き金に賭けた。その声でシバさんがセックスしてる所が頭に浮かんだ。セックスしてる時もあんな小さい声でGOサインを出すのだろか。ガチャ、という音と共に、全身に戦慄が走った。イク時なんかよりもずっと強烈な戦慄に、私は鳥肌を立ててヒクッと短い痙攣した。
胃に力が入り、それと共に何故か膣にも力が入った。エクスタシーと同じように、陰部全体が痺れた。バシッという音と共にピアスはピアッサーから離れ、自由になった私は顔を歪めて舌を口の中に戻した。
「みして」
シバさんは私の顔を自分の方に向かせて自分の舌を出して見せた。私は少し涙目になりながら感覚のない舌を突き出した。
「うーん、オッケーだね。真っ直ぐに入ってるし、位置もばっちり」
「ほんとだ。ルイ、良かったじゃん」
アマが割り込んできて、私の舌をジロジロ見た。私は舌がじんじんしていて喋るのも億劫だった。
「ルイちゃん、だっけ? 痛いの強いんだね。女の方が耐えられるんだってね、こういうの。舌とか性器とか、粘膜に開けると失神する人とかいるんだよ」
私は頷いて、表情だけでそうなんだ、と答えた。鈍い痛みと鋭い痛みが短い間隔で交互に襲ってくる。でも、ここに来て良かったと思った。最初は自分で開けようと思っていたけど、アキの言うことを聞いて良かった。自分だったらきっと途中で断念していただろう。
その後氷を貰い、舌を冷やした。興奮が少しずつ治まっていくのが分かった。落ち着くと店内に戻ってアマと二人でピアスを物色した。アマはピアスに飽きるとSMグッズのコーナーをうろつき、私は奥の部屋から出てきたシバさんを見つけ、カウンターに寄りかかった。
「シバさんはスプリットタン、どう思います?」
シバさんは、ん? と言って首をひねった。
「ピアスは刺青と違って、形を変えるもんだからね。おもしろい発想だと思うけど、俺はやりたいとは思わないね。俺は、人の形を変えるのは、神だけに与えられた特権だと思ってるから」
シバさんの言葉は、何故かすごく説得力があって、私は大きく頷いた、私は自分が知っている限りの身体改造を頭に浮かべた。纏足(てんそく)、ウェストンのコルセットでの矯正、あと首長族なんてのもあった。歯の矯正なんてのも、改造だろうか。
「じゃあ、シバさんが神だったらどんな人間を作ります?」
「形は変えないよ。ただ、バカな人間を作る。ニワトリみたいなに、バカなのを。神の存在なんて考えつく事のないように」
私は少しだけ目を上げてシバさんを見た。シバさんはサラッと言ったけど、目はいやらしく笑っていた。おもしろい男だと、私は思った。
「今度、刺青のデザイン見せてもらっていいですか?」
シバさんはニッコリしていいよ、と優しい目で言った。シパさんの目は不自然なほど茶色く、白い肌といい、白人並に色素の薄い人なんだなと思った。
「良かったら電話して。ピアスの事も、訊きたいことがあったらいつでもいいよ」
シバさんはそう言ってお店の名刺の裏に携帯電話の番号を書いて私に手渡した。私はそれを受け取るとありがとう、と微笑み、まだムチを手にとって物色しているアマにチラリと目をやって、財布に押し込んだ。
「あ、お金」
「財布で思い出して「いくら?」と聞くとシバさんは「いいよ」と興味なさそうに言った。私はカウンターに肘をつき、手に顎を載せてシバさんを観察した。カウンターの中の椅子に座っているシバさんは私の視線をうざったそうにかわし、ずっと目を合わせなかった。
「なあ、俺はお前の顔を見てるとSの血が騒ぐんだ」
おもむろに、シバさんが目を合わせないまま言った。
「私Mだから。オーラ出てんのかな」
シバさんは腰を上げ、やっと私の目を見た。カウンターの向こうから私を覗き込むシバさんは、子犬でも見るような愛おしい目をしていた。私の目の高さに合わせて腰をかがめると細い指で私の顎をぐいと持ち上げ、微笑んだ。
「この首、ニードルで刺してぇ」
彼は今にも声を上げて笑いだしそうな顔でそう言った。
「それってSavageのSじゃないの?」
「ああ、確かに」
何それ、と返されるだろうとおもっていたら、少し驚いてシバさんを見つめ返した。
「知らないと思った」
「俺、残酷な言葉は詳しいの」
そう言うとシバさんは唇の片端だけ上げて恥ずかしそうに笑った。狂ってる‥‥という思いの中、この男になぶられたいという欲求だけは否めなかった。腕をカウンターに置き顎を上に向けた私の首を、シバさんは撫でまわした。
「ちょっとお、シバさん。人の女に手ぇ出さないでくださいよ」
私たちの視姦を遮ったのはアマの間抜けな声。
「ん? 肌見てたんだよ。彫る時の参考に」
シバさんの言葉にアマはそっか、と顔の筋肉を緩めた。私とアマはいくつかピアスを買い、シバさんに見送られて店を出た。
アマと一緒に外を歩くのも、段々慣れてきた。アマは左眉に三本4Gの針型のピアスを刺し、下唇にも同じように三本同じピアスを刺している。それだけでも目立つというのにタンクトップからは龍が飛び出し、真っ赤な髪はサイドが短く刈り込まれていて、太いモヒカンみたいな形。あの暗いテクノしかかけないクラブでアマを見て、はっきり言って私は引いていた。
私はそれまでヒップホップとトランスをかけているクラブにしか行ったことが無かった。ほとんどが友達付き合いのイベントだったけど、クラブなんてどこも同じようなもんだと思っていた。あの日、私は友だちと遊んだ帰りになまった英語を話す黒人に声を掛けられ、あのクラブに連れていかれた。
クラブはクラブ違い。知らない曲ばかり流れるブースに嫌気がさしてカウンターで飲んでいると、そこから妙な踊り方をするアマが目に入った。異質な客の中でも際立っていた彼は、私と目が合うとつかつかと歩み寄って来た。こういう人種もナンパするんだ、と少し驚いた。
他愛もない話の後、私は彼の舌に見せられた。そう、私は彼の二手に分かれる細い舌に魅せられた。どうして強く惹きつけられたのか、未だに分からない。私はこの意味のない身体改造とやらに、一体何を見出そうとしてるんだろう。
舌のピアスを指でつついてみた。たまに、口の中でピアスが歯に当たりカチ、と音をたてる。痛みはあるけど、痺れは大分治まってきた。
「ルイ、スプリットタンに一歩近づいてきた感想は?」
不意にアマが振り返ってそう言った。
「よく分からない。でも嬉しい気がする」
「そうか、良かった。俺は、お前と気持ちを共有したいんだよ」
アマはそう言って、だらしなく笑った。どこがだらしないのか分からないけど、アマは笑うとだらしない顔になる。口を開けると下唇のピアスの刺さった部分がダラッと下がるかもしれない。私の中でアマみたいな、パンクな人のイメージはいつもマリファナ吸って乱交してるって感じだったけど、意外とそうでもない人もいるらしい。
アマはいつも優しくて、ガラにもなくくさいセリフを吐いたりする。全く、似合わないにも程がある。アマは部屋に帰ると呆れるくらい長いディーブキッスをして、あの蛇舌で私の舌のピアスを舐め回した。じんじんと体の芯を震えさせる痛みが、もうすでに心地よかった。
アマとセックスしながら、目を閉じてシバさんの事を思い出した。
神の特権‥‥上等だ。私が神になってやる。喘ぎ声が冷たい空間に響く。夏で、エアコンも効いていなくて、私の体は汗ばんでいるというのに、何故かアマの部屋は冷たい。
「イッていい?」
アマの苦しそうな声がだらしなく宙を舞う。私はうっすら目を開けて、小さく頷いた。アマは引き抜くと、私の陰部に放出した。まただ‥‥。
「ちょっと、お腹に出してって言ってるじゃない」
「ごめん、ちょっとタイミングが‥‥」
アマは申し訳なさそうに言ってティッシュを引き寄せた。アマはいつも私の性器に射精する。何が嫌って、毛がバリバリになる事。そのまま余韻に浸って寝てしまいたいのに、アマのせいでいつもシャワーを浴びる事になる。
『広告 挿入避妊具なら小さいチンコ、ユルユル膣であっても相手に満足させ心地よくイカせられる』
「お腹に出せないんだったゴム使ってよ」
アマは俯いてもう一度ごめん、と言った。私はティッシュで軽く拭き取ると立ち上がった。
「シャワー、浴びるの?」
アマの声があまりにも寂しそうで思わず足が止まった。
「浴びる」
「俺も一緒に入っていい?」
思わずいい、と言いかけたけど、全裸のまま情けない顔をしているアマを見てバカらしくなった。
「狭い風呂に二人で入るなんて嫌よ」
私はバスタオルを取ると風呂場に入り、鍵を閉めた。洗面台の鏡に向かって舌を出してみた。舌の先には銀の玉が付いている。これが、スプリットタンへの第一歩だ。一カ月位は拡張しないように。とシバさんは言っていた。道は、まだまだ遠い。
風呂を出るとアマは黙ったままコーヒーを差し出した。
「ありがう」
そう言うとアマは顔をほころばせ、コーヒーを飲む私をじっと見ていた。
「ルイ、布団に入ろう」
言われるままに並んで布団に入ると、アマは私の胸に顔を埋めて乳首を口に含んだ。アマはこれが大好きで、セックスの前も後もこれを欠かさない。スプリットタンだからだろうか、アマの愛撫は気持ちいい。安心しきったアマの顔は本当に赤ちゃんみたいで、こんな私でもほんの少し母性本能が働く。身体を撫でてやるとアマは上目遣いで私を見て、幸せそうな笑みを浮かべた。それを見たら、私も少しだけ幸せな気分になった。パンクなくせに、癒し系。アマはよく分からない男だ。
「えっ? うそっ? ちょーいたそー」
友達のマキの反応はこんなもん。まじまじと私の舌を見て、いーたっそー、と連呼して顔を歪めている。
「どういう心境の変化なの? 舌ピなんてさ。ルイ、パンクとか原宿系とか嫌いじゃん」
マキは二年前にクラブで知り合った。コテコテのギャル。ずっと仲良しで、いつも一緒に遊んでるから、私の趣味をよく分かっている。
「うん、ちょっとパンクな人と知り合ってさ。影響受けたというか。なんつーか」
「でもギャルが舌ピっつーのも珍しいよね。耳のピアスの穴でかくしたと思ったら次は舌かあ、ルイ、このままパンクに走っちゃうんじゃないのぉ?」
ギャルじゃないって、という私の言葉にも耳を貸さずマキはあーだこーだとパンク批判を口走り続けた。確かに、キャミソールワンピースに、金の巻き毛で、舌ピは変だろう。でも私がやりたいのは舌ピじゃない、スプリットタンだ。
「マキ、スミってどう思う?」
「スミって刺青? 刺青はいーんじゃない? 薔薇とか、蝶とか可愛いんじゃん」
ニコニコしてそう答えるマキ。
「そうじゃなくて、龍とかトラ、バクとか浮世絵とか、可愛くないやつ」
マキは顔を曇らせて、はぁ? と大きな声を出して、どーしちゃったのよ? と私に詰め寄った。
「その知り合ったパンクな人にやれって言われたの? その人と付き合ってんの? ルイ、もしかしてその人に洗脳されちゃったんじゃないの?」
洗脳、そうかもしれない。初めてアマのスプリットタンを見た時、明らかに自分の中の価値観が音を立てて崩れるのが分かった。何がどう変わったのかは分からないけど、私は一瞬にしてあの舌に魅了された。でも魅了はされたけど、それで私もやりたいと思ったわけじゃない。どうしてこんなに血が騒ぐのか、その理由を知りたくて今スプリットタンに向かってひた走っているような気がする。
「そうだ、マキ会ってみる?」
二時間後、私たちは待ち合わせ場所で落ち合った。
「あ、アマ」
「手を振る私の視線の先を見て目を丸くしているマキ。
「うそ、まじで?」
「うん、あの赤毛ザル」
「うそ、まじで? あたし怖いよ」
明らかに引いているマキに気づいて。アマは申し訳なさそうにおずおずと私たちに近づいた。
「何か、怖くしてごめんね」
アマはマキに訳の分からない謝罪をし、マキはその言葉に大ウケし、私はマキの反応に安堵した。私たちは夜の繁華街を徘徊して、結局安いだけが取り柄の居酒屋に入った。
「何か、アマさんと歩いているとみんな道をあけるよね」
「ほんとだよ。アマと歩くとね、キャッチされないしティッシュももらえないんだから」
「じゃー俺って便利じゃん」
アマとマキはすぐに打ち解け。アマがスプリットタンを自慢すると。かっこいーじゃん、とマキは手のひら返してはしゃいだ。
「じゃあ。ルイもこれやるんだ」
「当たり、おそろにするの。ルイさあ、眉ピと口ピもしなよ。全部おそろにしようよ」
「やだよ、私がやりたいのは舌と刺青だけ」
「でも悪いけどルイをパンクな道に連れ込まないでくださいね。私とルイは二人で一生ギャル同盟組んでるんです」
「組んでいないし、ギャルじゃないし」
二人は「ギャルだし」と言って、何故か私に一気コールをかけた。
三人でペロベロに酔っぱらって店を出ると、ギャーギャー騒ぎながら駅に向かって歩いた。もう店は閉まって、静まり返っているスカウト通りでたむろしている、見るからにチンピラかギャングみたいな男が二人、目に入った。例のごとく、アマをジロジロ見ている。アマはしょっちゅうガラの悪い奴らに絡まれてている。ガンくれただけの、ぶつかったただの、いちゃもんつけられて。でもアマはいつもヘラヘラ笑って「ごめんね」と言うだけだ。パンクはパンクでも、中身はただのヘタレだ。
「おねーえちゃん、そいつ彼氏?」
片方のベルサーチの服を着た男が私に歩み寄って来て、ちゃかすように言った。マキは私たちの後ろに隠れて目を合わせないようにしているし、アマは男を睨みつけるだけだし、どいつもこいつも役に立たない。シカトして通り過ぎようとすると、男は「違うよね?」と言って私の前に立ちはだかった。
「私とこいつがヤッてるとこ、想像できないの?」
無表情のまま小首をかしげると、男は私の肩を抱き、できないよー、と言って無造作に私のワンピースの胸元に手を掛けた。今日、何色のブラジャーしてたっけ? と考えた瞬間。ゴッという音と共に私の視界からワンピースの中を覗き込んでいた男が消えた。一瞬訳が分からず、ぐるりと一周見渡した。男が道端に倒れていて、アマの目が血走っていた。なるほど、アマが男を殴ったわけね。
「てめー何するんだこら」
そう怒鳴ったもう一人のツレがアマに殴りかかる。アマはそいつにも鉄拳をくらわし、まだ倒れたままの男に馬乗りになって仰向けにさせるとこめかみの辺りを何度も殴りつけた。どろっとした血が流れるのが見えた。男は気を失っていて動きもしない。
「ひぃっ」
マキが血を見て悲鳴をあげる。
「あ‥‥」
そうだ。私はふと思い出す。アマのお気に入りのシルバーリング、今日も右手の人差し指と中指に嵌めていた。鈍い音の正体が分かって、全身に冷や汗がにじんだ。ゴッ‥‥ゴッ‥‥TEL・骨と銀がぶつかる音。
「アマ、もういいでしょ」
アマは無言のまま、私の声が聞こえているのかいないのか。また拳を男のこめかみに叩きつける。アマが一発加えたもう一人の男が起き上がってじりじりと逃げていく。まずい、警察呼ばれる。私は思わず声を荒げる。
「いい加減にしろよ」
私がそう言ってアマの肩をつかむと同時に、アマの拳が男の顔面に振り下ろされた。思わず、目を伏せた。マキが嗚咽している。
「アマ!」
怒鳴ると、アマはようやく体の力を抜いた。正気に戻ったかとホッと息をついた私の目に映ったのは、男の口の中をまさぐるアマの指。
「何してんだよこの野郎!」
私はアマの頭を引っぱたいてタンクトップを引っ張った。その時、微かにサイレンの音が聞こえた。
「マキ、あんた逃げな。早く」
マキは真っ青な顔で頷くと「今度また三人で遊ぼうーね」と言って手を振った。マキは、意外とタフだ。酔っている割にはなかなかの走りでその場を去った。フラフラしているアマは虚ろな目で私を見つめたまま。
「ほら、ねえ分かってよ。アマ、警察呼ばれたんだよ。逃げるんだよ」
肩を叩くとアマはいつものようにだらしなく笑って、やっと走り出した。アマは思いのほか逃げ足が速く。私はぜいぜい言いながら手を引かれて走った。細い路地裏で、私たちはやっと足を止めた。アマの後ろで、私はへたり込んだ。
「何やってんだよ馬鹿野郎―」
絞り出すように言った私の言葉は、自分でも驚くくらい情けなかった。アマは私の隣にしゃがみ込むと血まみれの右手を出し、拳を開いた、そこには一センチ程の赤い物体が二つ。すぐに、あの男の歯だと分かった。背中に一滴冷水を垂らされたような感覚が、私の全身の毛という毛を逆立てた。
「ルイの仇、取ってやった」
そう言って勝ち誇ったような笑みを浮かべるアマ。何により恐ろしかったのは、その笑みが少年のように無邪気だった事。大体仇って言われても…‥、私は殺された訳じゃない。
「んなもんいらねーよー」
そうシカトする私の腕を取り。アマは二本の歯を私の手の平にコロッと落とした。
「これも一応、俺の愛の証」
私は呆れて、口を開けたまま肩をすくめた。
「日本じゃそんな愛の証は通用しないわよ」
私は寄り添って来るアマの頭をぐしゃぐしゃと撫でてやった。
それから私たちはトロトロと公園まで歩き、アマは水道でタンクトップと手を洗って、何事もなかったように終電でアマの家まで帰った。部屋に入ってすぐアマを風呂場に押し込むと、捨てる事も出来ず化粧ポーチに放り込んだ二本の歯を手に載せて観察した。キッチンの水で歯に付いた血を洗い流すと、また化粧ポーチに押し込んだ。もしかしたら私は相当厄介な男に関わってしまったのかもしれない。アマは完全に私と付き合っていると思っているようだし、もし別れを切り出して逆上されたら殺されるかもしれない。アマは風呂から出てくると私の隣に座り、窺うような目でこちらを見て、私が黙ったままでいるとボソッとごめんね、と呟いた。
「コントロール出来ないんだよ。俺って結構温厚な方だと思うんだけど、一回殺してやる、って思っちゃうと本当に殺すまでやらなきゃ、って気になっちゃうんだ」
こいつは人を殺した事あるんじゃないかと思った。
「アマ、あんたもう成人してるんだから、人殺ししたら実刑なんだよ。分かってるの?」
「いや、俺まだ未成年だけど?」
アマは真面目な顔でそう言って、まじまじと私を見た。私はそんなアマに呆れて、心配しているのがバカらしくなった。
「バカじゃないの?」
「本当だよ」
「だって会った時二十四って言ったじゃない」
「いや、ルイがその位かと思って合わせてみた。ガキだと思われたくなかったし。ああ、何か軽いトーンでカミングアウトしちゃったね。もっと真剣に言うべきだった? そういや、ルイって幾つなの?」
「あんたね、失礼にも程があるわよ。私だって未成年よ」
「うそっ?」
短くそう叫んで目を丸くするアマ。
「まじで? 俺何かすごく嬉しいや」
そう言って満面の笑みで私を抱きしめるアマ。
「まあ、お互い老けているって事だな」
私はそう言ってアマを突き放した。そう言えば、私たちはお互いの事をほとんど知らない。お互い、生い立ちや歳の事も、避けていた訳ではなくてただ話題に上がらなかった。結局私たちは未成年だということだけ知ったけども、やっぱりそこから、じゃあ幾つなの? という話にならなかった。
「ねえアマ、あんた名前何ていうの? 天野? スアマ?」
「何だよスアマって。俺のアマはね、アマデウスのアマなの。アマが名字でデウスが名前ね。ゼウスみたいでかっこいいでしょ?」
「ふうん、まあ言いたくないならいいけど」
「本当だってば。ルイは?」
「あんたはどうせルイ十四世のルイだと思ってんでしょ。私はルイ・ヴィトンのルイよ」
「あっそう。随分お高い女だな」
私たちはその後もくだらない事ばかり話して、ビールを片手に明け方まで語っていた。
次の日の昼過ぎ、私はDesireでシバさんと刺青のデザイン画を見ていた。その筋の人が入れるような浮世絵から、ドクロや初期のミッキーマウス等の洋画まで、様々なデザイン画が気が遠くなるほどファイルされていて、私はシバさんのマルチな画力に啞然とした。
「お前、龍がいいの?」
何十枚もある龍のページにじっくり目を通しているとシバさんが身を乗り出してファイルを覗き込んだ。
「うん、やっぱり龍かなあ。これアマのやつじゃない?」
「ああ、そう。少し形は違うけどそのデザインだよ」
シバさんはカウンターに寄りかかって、椅子に座ったままファイルに目を通している私を見下ろした。
「なあ、アマ知らないんだろう? お前がここに来るって事」
目を上げるとシバさんはうっすら笑みを浮かべていやらしい目で私を見た。知らないよ」
そう言うとシバさん少し真面目な顔で、俺が携帯の番号教えたの、あいつに言うなよ、と言った。その言葉でシバさんがアマのあの気質を知っているんだと分かった。
「ねえ、アマってさ‥‥」
私はそこまで言って口を噤んだ。
「知りたい? あいつのこと」
シバさんは一瞬おどけたように宙を見上げてから私を見つめ、首を傾げて言った。
「ん、やっぱいいや。知りたくないかも」
そ、シバさんは興味なさそうに言うとカウンターを出て、店を出た。十秒もしない内にドアが開いてシバさんは戻った。
「何? どうしたの?」
「大事なお客様が来たから閉店しといた」
そ、私は興味なさそうに言ってまたファイルに目を落とした。それから、私たちは奥の部屋でデザインの打ち合わせを始めた。シバさんは驚くくらい素早く綺麗な絵を描いていく。そういうアーティステイックな血がまるで通っていない私は羨ましい限りだ。
「でもね、はっきり言って迷ってるんだよね。スミって一生モンでしょ。入れるからには最高の絵を入れたいし」
私は頬杖をついてシバさんが描いた龍を指でなぞった。
「そりゃ、そうだよな。今はレーザーで取ることは出来るけど、基本的に取り返しつかないからね。ま、俺の場合、これは髪伸ばせば見えなくなるけど」
シバさんそう言ってツルツルの頭に舞う龍を撫でた。
「そこだけじゃないんでしょ?」
そう聞くとシバさんは見たい? と言ってニヤッと笑った。私が軽く頷くと、シバさんは長袖のTシャツに手を掛けた。シバさんの体はキャンパスのようにカラフルな画が所狭しと描かれていた。背中には龍、猪、鹿、蝶、牡丹や桜や松。
「猪鹿蝶だ」
「そう。俺、花札とか好きなの」
「でも萩と紅葉入ってないんじゃん」
「ああ、場所がなかったから諦めたんだよ」
ふうん、なかなか適当なもんだな。そして、シバさんが私の方に向き直った瞬間、一匹の動物が目に入った。
「これ、麒麟?」
シバさんの右の二の腕に彫ってある一角獣に、私の目は釘付けになった。
「ああ、知っている? こいつはね、俺の一番のお気に入りなんだ。聖なる生き物なんだよ。生草は踏まず、生物を食わず。言ってみりゃ動物界の神だな」
「麒麟って一角獣だっけ?」
「ああ、これはねえ、中国人の想像の産物だから、中国では、麒麟には肉に包まれた一本の角があるって言われているんだ」
「私これがいい」
腕を眺めながら呟いていた。シバさんは一瞬言葉を失って俯いた。
「これ彫ったの、日本でトップクラスの彫り師なんだ。俺、麒麟彫ったことないし」
「その彫り師に彫ってもらえない?」
「その人、死んだんだ」
シバさんはそう言うと顔を上げた私の目を真っ直ぐみつめた。軽く息を吐くとアメリカ人のように肩をすくめて口を開いた。
「麒麟のデザイン画抱いて焼身自殺したんだ。芥川龍之介の世界でしょ。多分、麒麟が怒ったんだよ、神聖な麒麟を勝手に彫ったから。麒麟彫ったら呪われるかも知んねーぞ」
シバさんはちゃかすように言って、自分の腕の麒麟を撫でた。私はどうしても諦めきれず、シバさんの麒麟をじっと見ている事しか出来なかった。
「しかもお前、麒麟って鹿と牛とかオオカミとか、色んな動物の集合体なんだぞ。描くのだってめんどうくせーんだからな」
「これがいいの。シバさん、お願い」
「…‥」
「お願い。デザインだけでも描いてみて」
シバさんはチッと舌打ちして苛立ったような顔で私を見た。そして小さい声で仕方ないねーな、と呟いた。
「やった。ありがとうシバさん」
「とりあえず、デザインだけ描いてみる、何か、背景とかリクエストある?」
私はしばらく考えて、またさっき見ていたファイルをめくった。
「これ、アマの龍と組み合わせて欲しいの」
シバさんはしばらく龍のデザインを見つめ「なるほどね」、と独り言のように呟いた。
「麒麟彫るの初めてだし、何かとコラボレーションした方が気が楽ではあるね。いいね、今流行のコラボレーション」
私は一笑して「そうだね」と言った。
「アマのと同じくらいの大きさで、背中に収めて欲しいの。幾らくらいかかる?」
シバさんはうーん、宙を見上げ、エッチ一回、と言って私を横目で見た。
「そんなんでいいんだ」
横目で見返すシバさんはS丸出しのやらしい目つきで私を睨んだ。
「服脱げよ」
というシバさんの言葉に、私は立ち上がる。ノースリーブのワンピースは汗ばんでいる体に張り付いて、ジッパーを下げると少し冷たい空気が入った。ワンピースを床に落とすと、シバさんは興味なさそうな目で私の体を一瞥した。
「お前、細いなあ。彫った後に太ると皮が張ってかっこ悪いぞ」
ブラジャーとパンツも、脱ぐと汗で湿っていた。ミュールを脱ぎ、寝台に腰を下ろした。
「大丈夫。もう何年も体重は変わっていないし」
シバさんはタバコを灰皿に押し付けるとベルトを外しながら寝台に歩み寄った。寝台の脇で立ち止まると、シバさんは片手で乱暴に押し倒し、私の首に手の平を押しつけた。指は頸動脈をなぞり、次第に力がこもっていった。シバさんの細い指が私の肉に食い込んでいく。立ったまま、私を見下ろしているシバさんの右腕に血管が浮き出ているのが見えた。私の体は酸素を欲しがり、所々短く痙攣した。喉が音をたて、私の顔は歪みだす。
「いいね。お前の苦しそうな顔。すげえ勃つよ」
シバさんは無造作に手を放し、パンツとトランクスを脱いだ。寝台に上がり、まだ意識が朦朧(もうろう)としている私の肩の上に膝をつき、チンコを差し出す。シバさんの両脚には龍が一匹ずつ泳いでいた。私は無意識のうちにチンコを手に咥えていた。酸っぱい匂いが口の中に広がった。
春夏秋冬の中で夏のセックスが一番好きなのは、この汗とアンモニアの混ざった匂いが好きだから、というのもある。シバさんは私を無表情のまま見下ろし、私の髪を鷲掴みにして引っ張った。顎をガクガクと前後運動させていると、濡れてくるのが分かった。どこを触られた訳でないのに濡れるなんて、便利なもんだ。
「なあ、アマってどんなセックスすんの?」
シバさんはそう言って腰を上げた。
「ん? ノーマルだけど?」
ふうん、と頷きながらシバさんは自分のベルトをパンツから引き抜いて、私の手首を後ろで縛った。
「欲求不満になんない?」
「別に。私はノーマルでもイケるくちだから」
「何? 俺はノーマルでイケないくちだと思う?」
「イケるの?」
「イケない」
「マッドなサディストだもんね」
「でも俺、男でもイケるよ。結構広範囲でイケる方だと思うけど」
シバさんが笑って言った。その言葉で、アマとシバさんがヤッているところを想像してみた。案外、美しいかもしれない。シバさんは細い腕で私をひょいと持ち上げ、寝台から下ろし、寝台に腰を下ろすと右足を私の前に出した。私は親指から小指まで丹念に吸い、口の中がカラカラになるまで足を嘗め続けた。手が付けず這いつくばっていたから、首が痛くなった。シバさんはまた私の髪をつかんで、上を向かせた。多分私は虚ろな目をしてたんだと思う。シバさんのチンコには血管が浮き立っていた。
「濡れてんの?」
小さく首を縦に振ると、シバさんはまた私を抱き上げ寝台に座らせた。私は無意識に脚を開いていた。軽い緊張が私を包む。Sの人を相手にする時、いつもこの瞬間私は身を硬くする。何をするのか分からないからだ。浣腸だったらいい、おもちゃもいいし、スパンキングも、アナルもいい。でも、出来るだけ血は見たくない。昔、膣にファイブミニの瓶を入れられ、危うくトンカチで割られそうになった事があった。あと、針で刺す人も苦手。
手首から手の平がじっとりしていて、肩から二の腕にかけては鳥肌が立っていた。シバさんは、物を使う気はないらしく、私はホッとした。シバさんは指を二本入れ、何度かピストンさせると引き抜き、汚いものを触ったように私の太股に濡れた指をなすりつけた。シバさんの表情を見て、また濡れていくのが分かった。
「入れて」
そう言うとシバさんは太股で拭った指を私の口に押込み、口の中をまさぐった。
「不味いか?」
シバさんの言葉に頷くと口から指を引き抜き、そのままマンコに入れ。また口の中に戻し、口の中をまさぐった。チンピラの口の中を探るアマの姿がフラッシュバックした。
「苦しいか?」
同じようにまた頷くとシバさんは指を抜き、私の頭に手を当てて荒々しくシーツに押し付けた。顔と肩と膝で体を支えると、下半身がガクガクした。
「お願い、早くいれて」
うっせーな、シバさんはそう吐き捨てて私の髪を掴み、枕に押し付けた。シバさんは私の腰を高く上げるとマンコに唾を吐き、また指で中をグチャッとかき混ぜるとやっとチンコを入れた。初めからガンガン奥まで突かれ、私の喘ぎ声は泣き声のように響いた。気づくと本当に涙が流れていた。
私は気持ちいいとすぐに涙が出る。満たされていくのが分かった。シバさんは突きながら私の手首を縛っていたベルトを外し、私の手が自由になると勢い良くチンコを抜いた。抜かれた瞬間、また一筋涙がこぼれた。シバさんは私を上に乗せ、私の腰を掴んで揺さぶった。マンコ一帯がシバさんの肌と擦れて痺れていた。
「もっと泣けよ」
シバさんの言葉に、また涙が伝わった。私は短く「イク」と呟き腰がガクガクと震わせた。イッた後、満足に動けないでいるとシバさんはめんどくさそうに私を押し倒し、上になった。シバさんは深く、強くピストンして私の髪を掴んだり、首を絞めたりしてひとしきり私の苦しむ顔を楽しむと「いくよ」と言った。あのピアッサーを持って言った時と同じだった。
短く、抑揚のない声。ぐっと深く入れて、引き抜き、私の口の中に射精した。その終わりは地獄からの解放のようでも、天国からの追放のようでもあった。シバさんはすぐに寝台から降りて。ティッシュでチンコを拭くとトランスを穿いた。私は投げられたティッシュの箱をキャッチし、鏡を見ながら精子を拭きとった。涙でメイクもはげかけていた。
私たちは寝台の上に座って壁に背をもたせかけ、宙を見つめてぼんやりタバコを吸った。「灰皿取って」とか「暑いね」とか何でもない言葉を交わし、しばらくそのまま何もせずに座っていた。やっと立ち上がるとシバさんは振り返り、蔑(さげす)むような目で私を見た。
「お前、アマと別れたら俺の女になれよ」
私は思わずその言葉に吹き出した。
「シバさんの女になったら殺されそう」
シバさんは表情を変えずに口を開いた。
「それはアマだって同じだろう」
私は一瞬言葉を失った」
「付き合うんだったら、結婚を前提にな」
シバさんそう言ってブラジャーとパンツを私に投げた。パンツを穿きながらシバさんとの結婚生活を想像してみた。きっとサバイバルな生活なるだろう。ワンピースを着て寝台を降りると、シバさんは小さな冷蔵庫から出したばかりの缶コーヒーを開けて差し出した。
「優しいだね」
「お前の爪が異様になげぇから開けてやったんだよ」
ふてぶてしくそう言うシバさんに私は素早くキスをした。
「ありがとう」
このダークな部屋に不釣り合い極まりない感謝の言葉が、行く当てのなく宙に舞った。私たちは店内に戻って、シバさんは店を開けた。
「でもこの店はほんと客来ないよね」
「ほとんどがピアスか刺青なんだよ。だから大体予約してくんの。こんな店にフラッと立ち寄る奴いないだろ」
「なるほどねー」
カウンターの中の椅子に腰を下ろし、舌をベロッと出した。ピアスを指で確認してみる。もう痛くない。
「ねえ、もう12入れてもいいかな?」
「まだだよ。一カ月くらいつけときな。だからファーストピアス12にしときゃ良かったのに‥‥」
シバさんは素っ気なく言ってアロアーの方からカウンター内を覗き込んだ。
「デザイン、出来たら連絡してくれる?」
「電話は、日中にお願いね。アマがバイトの時間に」
はいはい、と言ってラックの整理に戻るシバさん。帰ろうかとバッグに手を掛けた瞬間、シバさんが振り向く。私は思わずピタッと止まって何? と目で問いかけた。
無表情で、シュールギャグをかますシバさん。
「カミノコ? 何かノコギリみたい」
「人間に命を与えるなんて、神は絶対サディストだ」
「マリア様はMだった?」
もちろん、シバさんは呟いてまたラックに向き直った。私はバッグを持ってカウンターを出た。
「飯とか、食ってかねー?」
「もうアマが帰って来ちゃうもん」
「そ。じゃあまたな」
シバさんはそう言って乱暴に私の頭を撫でた。私はシバさんの右腕を取り、麒麟の場所を撫でた。
「かっこいいの、描いてやるよ」
シバさんの言葉に笑顔で応えると、私は小さく手を振って踵(きびす)を返した。店をでるともう外は陽が傾きかけていた。空気が爽やかで。むせかえりそうだった。電車に乗って、アマの家に向かう。駅から家までの道、家族連れが多い商店街で、うるさい人々の声に吐き気を覚えた。
ゆっくりと歩く私の足に、子供がぶつかった。私の顔を見て、素知らぬ顔をするその子の母親。私を見上げて泣き出しそうな顔をする子供。舌打ちをして先を急いだ。こんな世界にいたくないと、強く思った。とことん、暗い世界で身を燃やしたい、とも思った。
アマの部屋に帰るとすぐに服を洗濯機に入れて回した。Desireはいつも甘ったるいお香の匂いがする。きっと服にも匂いが付いているだろう。それからバスルームに入ると丹念に全身を洗った。部屋に戻るとデニムのパンツにアマのTシャツを着た。さっと薄く化粧をして、髪の毛を乾かした。洗い終わったワンピースを外に干し、やっと一息ついた所でガチャン、という音と共にアマが帰って来た。
「おかえり」
アマは満面の笑みで、私はホッとした。
「今日は一日中眠かったよ」
欠伸をしながらアマが言う。当然だ、朝方まで飲んでいのだから。私だってヘロヘロだ。今朝、アマを送り出した後、私は何故か寝付けずにシバさんに電話をした。いってみれば私の意志通りの、意外性の欠片もない一日だった。ただ一つ、今日という日のおまけに麒麟が私の体に住み着く日が待ち遠しい。
アマがアマデウスで、シバさんが神の子なら、私はただの一般人で構わない。ただ、とにかく日の光が届かない、アンダーグラウンドの住人でいたい。子供の笑い声や愛のセレナーデが届かない場所はないのだろうか。
私たちは居酒屋で夕飯を食べ、部屋に戻るとノーマルのセックスをして、アマは気を失うようにして眠りにおちた。私はアマの寝顔を眺めながらビールを飲んだ。私がシバさんとセックスした事を知ったらアマはあの薄汚い男にしたように、私をたこ殴りにするだろうか。どちらかと言えば、私はアマデウスより神の子に殺されたい。でもきっと、神の子は人を殺さない。
ベッドからだらんと伸びているアマの手には、あのごついシルバーリングが光っていた。気を紛らわそうとテレビを点けたけど、くだらないバラエティやつまらないドキュメントばかりで、一通りチャンネルを回し、電源を切った。アマの部屋にある雑誌は男物のファッション誌ばかりだし、パソコンの使い方は分からない。私は舌打ちをして新聞を手に取った。下世話なスポーツ新聞だけど、一応これが私の社会の情報源。テレビ欄で深夜番組をチェックし、裏から目を通した。
この日本で毎日殺人が行われ、風俗業界も不景気だという事ぐらいしか、理解できないが、ふと小さな記事が目に留まった。『新宿の路上で二十九歳の暴力団員撲殺される』という見出しで昨日の男が思い出された。いや‥‥あの男はもっと歳がいっていたはずだ。あの顔で二十代なんて、私やアマ並みの老け顔だ。まあ、同じような事件が、同じ新宿で起こってんだろう。
フッと息をついて記事を読んだ。『被害者は搬送先の病院で死亡。犯人は逃亡中。目撃者の証言によると、男は二十代半ばで赤い髪。身長は175~180センチ、細身の男』そんな感じ。記事とアマを見比べて、新聞を閉じた。もしこれがアマの起こしたあの事件で、目撃者というのがあの男のツレだったとしたら、犯人の特徴はまず第一に顔面のピアスと刺青を挙げるはずではないのか?
分からないけど、きっとアマは大丈夫。そんな根拠のない自信があった。きっと、アマと同じような男が、二十九歳暴力団員を殺したんだ。アマが殴った男は、きっと生きている。そう強く思った。私はバッグをつかむと部屋を出て、早足でコンビニに向かった。ブリーチ剤とアッシュのヘアカラーを買って戻るとスヤスヤと寝息を立てているアマを叩き起こした。
「ん? ルイ、どーしたのぉ?」
間抜けな声を上げているアマの頭を引っぱたき、鏡前に座らせた。
「何っ? 何事?」
「何事? じゃないわよ。髪の色変えんの、前から気になっていたのよ、その気色悪い赤毛」
アマは訳が分からない顔のまま私に言われるがままに服を脱ぎ、トランクス一枚になった。
「大体さあ、黒い肌に赤って汚いのよ。アマはね、センスなさすぎ」
ブリーチ剤を混ぜながら強烈な匂いに顔をしかめていると、アマは何故か満面の笑みを浮かべていた。
「ルイって優しいんだね。俺、もっとセンス磨くから、ルイも手助けしてね」
アマはポジティブな解釈をしてくれたようだ。きっとアマは幸せ者だ。私は「はいはい」、と流してブリーチ剤をブロッキングした髪に塗り始めた、髪の色を変えたからってどうにもなるもんじゃないけど、変えられるところは変えたほうがいいと思った。私はブリーチ剤を半分に分けて使った。
一度髪を流し、ドライヤーで乾かすともう既に赤色は抜けて金になっていたけど赤からアッシュとか、反対の色を入れる時には念を入れて丹念に色を落とした方がいいと、昔美容師さんから聞いた。残りのブリーチ剤を混ぜ、もう一度さっきと同じ工程を繰り返すとアマの髪はほぼ白に近い金になっていた。
ドライヤーでパリパリに乾かし、アッシュのカラー剤を塗り込んだ。アマの眠気はマックスらしく、ずっとうとうとしていた。さすがに可哀想に思ったけど、これも一応アマの事を思ってやっているんだと思い直した。カラーを塗り終えて頭にラップを巻くとアマは虚ろな目で私に笑いかけた。
「ルイ、ありがとね」
新聞を見せた方がいいとのかどうか考えたけど、私は黙ったまま手を洗いにバスルームに向かった。
「アッシュだったら少しはかっこよく見えるかな?」
「別に、かっこわるいとか言った訳じゃないでしょ」
そう言って洗面所から顔を出すとアマは笑った。
「俺、ルイのためだったら坊主なしてもいいよ。服も、ルイに合わせてギャル男っぽくしてもいいよ。美白しろって言うならするよ」
「勘弁してよ」
アマは別にかっこ悪い訳ではない。目つきは悪いけど、むしろかっこいい部類に入る方だと思う。ただ刺青と顔面のピアスが、かっこいいとか悪いとかの問題じゃなくしている。きっと他人として街で見かけたらもったいない‥‥と思うだろう。でも今はアマの気持ちが分かる。私は今、外見で判断される事を望んでいる。陽が差さない場所がこの世にないのなら自分自身を影にしてしまう方法はないかと、模索している。
カラーを入れて十分もするとアマはそわそわし始め「まだ? まだ?」と何度も聞いた。気持ちは分からないでもないけど、私は少しでも赤みを落とそうと躍起になっていた。結局私は三十分以上も放置させ、ラップを取ると無造作に髪の毛に手ぐしを入れてバサバサとかした。
「何してんの?」
「酸化させてんの。空気に触れさせると色が深く入るの」
ムラがないかチェックすると、もういいよ、と言ってバスタオルを手渡した。アマは「はーい」、と言って意気揚々とバスルームに向かった。アマが出て来るまで私はまたあの新聞の記事に目を通した。アマじゃない、アマのはずがない、自分にそう言い聞かせた。幾ら考えても答えは出なかった。
出てきたアマの髪を乾かしてセットしてやると、アマは鏡に向かって目をパチパチさせて微笑んだ。
「やめろよ、気色悪い‥‥」
私が呟くとアマはふくれ顔で振り返った。アマの髪は見事な灰色になっていた。灰そのものの色だった。あの赤毛の面影は、もう何処にもない。
「アマ、あんたに明日から長袖の着用を義務づける」
「何で? まだ暑いじゃん」
「うっさいな。タンクトップばっか着てっからギャングにしか見えねーんだよ」
そう言うとアマはしょんぼりして「はーい」と答えた。刺青は目立つ。もしかしたら、警察が捜査のために刺青の事を公表していなかったのかもしれない。私は気がおかしくなりそうな程、深読みと逆読みをして、ギャング系の服は着るなだの髪を伸ばせだの外で目立つなだのアマにきつく注意した。アマは私の剣幕にキョトーンとしつつも分かった。約束するもと言って私をきつく抱きしめた。
「ルイのためならお安いよ」
そう言って私をベッドに引きずり込むアマは、とても殺人犯になんか見えなかった。大丈夫、アマはいつも間抜けなバカ男で、私の隣で笑ってる。アマはベッドの中で私のキャミソールをたくし上げ、乳首を吸った。次第にその口が脱力し、そのままアマは寝息をたて始めると私はキャミソールを下ろし、電気を消して目を閉じた。闇の中で、私は懇願した、アマが捕まりませんように。誰に懇願したのか分からない。
でもたとえそれが神にでもあっても構わないとすら思った。深い眠りが、私を飲み込んでいくのが分かった。
次の日、ずっと休んでいたコンパニオンのバイトに出る事になった。昼過ぎ、電話の声で起こされ、欠員の穴埋めに入ってくれないか言われ、渋っていると三万円出すとマネージャーは太っ腹にもそう言った。アマと会ってから、アマの金で生活していたから、もうバイトも辞めてしまおうかと思っていた。
バイト代でおいしい酒でも飲みに行くか、と思い私は重い腰を上げた。コンパニオンのバイトは登録制プラス日払いという手軽さに後押しされて半年前に始めた。ホテルのイベントでお酒をついで回るだけにも関わらず、一パーティー大体二時間で一万円。ウケのいい顔に生まれて、良かった。
少し時間に遅れたけど、ホテルのロビーでマネージャーと女の子たちと落ち合った。マネージャーは私を見付けると顔をほころばせ、良かった、微笑んだ。控え室でそれぞれ着物を渡される。私は先ず自分で着つけが出来ない子の着つけを始めた。このバイトを始めて、見よう見まねで始めた着付けも、今ではそつなくこなせるようになっていた。
私は赤い派手な着物を渡され、自分で着付けをすると、持って来ていた茶色のストレートのウィッグをつけた。金髪で一流企業のパーティーのコンパニオンは出来ない。といって染めるのも嫌だった私はいつもウィッグを持参していた。ウィッグをアップにまとめているとマネージャーが声を掛けた。
「中沢さん」
久々に名字を呼ばれて、私にもそんな名前があったことを思い出す。
「あの、ピアス‥‥」
マネージャーは申し訳なさそうに言った。ああ、と呟いてピアスを触った。忘れる所だった。普通のピアスなら何も言われないけど、さすがに0Gにもなると着物には不釣り合いだし、一流企業には引かれる。五のピアスをすべて外すと、化粧ポーチに入れた。ちらっと二本の歯が見えた。もしもあの記事がアマの起こした事件だったとしたら、警察は男の歯が二本消えてることに気づいているのだろうか。
「中沢さん?」
またマネージャーの声がして、うんざりしながら、はい? と振り返った。マネージャーの顔に驚きの色が広がる。
「中沢さん、それピアス?」
すぐに、舌のピアスの事だと分かった。
「そうですよ」
マネージャーは困惑の表情を浮かべて「外せる?」と聞いた。
「あ、入れたばかりなんでまだ外したくないんですけど」
そう答えるとマネージャーは更に首をひねり「でも…」とか「うーん」とか言葉を濁した。
「大丈夫ですよ。大口開ける事はないですから」
にっこりして近づくと、マネージャーは顔の筋肉を緩めて仕方ないな、小声で言った。マネージャーは私のことを気に入っているらしく、大抵の事はにっこりすれば許してくれる。だから私はほとんどの女の子に嫌われている。
会場に入ると、私たちは笑顔を振りまき、トレーを片手にビールやワインを注いで回った。いつもと全く変わらない。退屈な立食パーティー。しばらくすると私は数少ない中のいいコンパニオン仲間のユリと会場の控え室で空き瓶の整理をしているふりをしながらビールを飲み、舌ピの話で盛り上がっていた。
「いやあ、びっくり。まさか舌に開けるとね」
ユリの反応はマキとほぼ同じ。
「男の影響でしょ?」
ユリはニヤッとして親指を立てた。
「まあね、男よりも舌に惚れた感じだけど」
話は舌から下ネタにもつれ込み、キャッキャとはしゃいでいるとマネージャーが呼びに来て、私たちは最後に一杯ずつビールを飲むと口臭スプレーをして会場に戻った。
私は二時間のパーティーでエリートさんたちから十三枚名刺を貰い、パーティーが終わった後ユリと名刺を物色した。
「これでいいじゃん。取締役」
「でも顔覚えてないし。どうせオヤジじゃないのぉ?」
はっきり言って、スーツを着込んだエリートに興味はないし、彼らだって舌ピをしているような女に興味はないだろう。気だての良い日本女性を装うった私は、どこのパーティーでもたくさん名刺を渡されるけど、結局私のイメージは全てが作り物。スプリットタンを完成させたら、このバイトも出来なくなる。早く穴を開けたいと、舌を鏡に映して思った。
私たちはその後別のホテルでも同じことを繰り返し、夜の八時に解散した。バイト料を貰いユリと一緒に事務所まで行った後、途中まで一緒に帰る事にした。携帯が鳴り、ユリが親指を立てて眉を上げて笑った。着信はアマからだった。そう言えば、置手紙かメールをしようと思っていたけど、完全に忘れていた。
「もしもし? ルイ? どこいんの? 何してんの?」
アマは今にも泣き出しそうな声でたたみかけた。
「あー、ごめん。急にコンパニオンのバイトに呼ばれて、今帰ってるから」
「何それ? ルイ、バイトなんかしてたの? コンパニオンって?」
「うるさいなー。登録制のバイトだよ。変なバイトじゃないから」
アマの怒涛の質問に辟易(へきえき)している私を、ユリが笑いをこらえながら見ていた。駅前で落ち合う約束して電話を切ると、ユリは吹き出した。
「何? 彼氏、束縛厳しいの?」
「あー、何か子供みたいな奴でさ。調子が狂うよ」
可愛いじゃーん、と言ってユリは私を小突いた。可愛いだけならいいんだけど‥‥、そう思ってため息をついた。駅でユリと別れて、帰路についた。二十分電車に揺られて、駅に着くと軽いステップで階段を上った。改札の向こうにアマの姿が見えた。手を振ると、アマは情けない顔をして手を振り返した。
「帰ったらルイいないし、書き置きもないし、出て行っちゃったんじゃないかって死ぬほど心配したんだから」
焼き肉屋に入り、ビールを注文するとアマは一気にそう言った。
「ま、いいじゃん。おかげで贅沢出来る訳だし」
アマはバイトの内容をしつこく聞き出し、やましいことがないと分かるといつものスマイルを見せた。アマはルイの着物姿見たいなあ、なんて言って私の小皿にレモンを搾った。焼き肉は美味しくて、ビールも美味しくて、最高の夕飯だった。働くのは大嫌いだけど、働いたのちのビールはいつもより美味しい。
それだけが労働の救いだ。上機嫌の私はアマの髪の色を褒めてやったし、珍しくつまらないギャグにも笑ってやった。大丈夫、アマの髪の色はアッシュだし、アマは幸せそうに笑ってる。まずいところは何一つない。
暑い。このクソ暑さも、残暑と呼ばれるようになった。Desireで麒麟の刺青を見せてもらった日から三週間余り、やっとシバさんから電話が来た。なかなか上手く描けなくて、苦戦したんだぞ、シバさんそう言ってデザインにかけた苦労をひとしきり語ると、早く見せてやりたいよ、とボソッと言った。私の舌ピも12Gになっていた。
次の日私はピアスを見たい、とアマを誘い、二人でDesireに向かった。Desireに着くと、シバさんは待っていましたとばかりに私たちを奥の部屋に連れて行き、デスクから一枚の紙を取り出した。すげえ、と声を上げたアマ。私もその絵に釘付けになった。そんな私たちをシバさんは満足そうに見て「いいだろ」と子供がおもちゃを自慢するように呟いた。
「これ、彫って」
私は一目で決めていた。こんな麒麟が私の背中に住むなんて、考えただけでゾクゾクする。今にも紙から舞い上がりそうな龍と、その龍を飛び越えようとするかのごとく前脚を高く持ち上げている麒麟、彼等は、私の一生の伴侶に相応しい。
「いいよ」
シバさんはニヤッとして答え、アマはやったじゃん、と叫んで私の手を取った。
こんなに素晴らしい刺青もデザインも、見たことがない。早速私たちは彫る場所と大きさを確認した。左肩の裏から背中にかけて、アマのよりも少し小さめで、15×30センチくらい。三日後に施術と決めた。
「前日はアルコールをとらない事。それと、出来るだけ早く寝て。体力使うからね」
シバさんの言葉に、アマもうんうんと頷いた。
「大丈夫ですよ。俺がルイの面倒見ますから」
アマはそう言ってシバさんの肩を抱いた。あきれ顔のシバさんがチラッと私を見て、一瞬あのヤッてる時の冷たい目をした。私が上目遣いで微笑むと、シバさんは含み笑いをした。
その後、飯でも食おう、というアマの提案でシバさんは少し早く店を閉めた。三人で外を歩くと、通り過ぎる人たちが道を空けた。
「いやー、やっぱシバさんと歩くとみんな振り返りますね」
「お前の方が目立つだろ。そんなギャングみてーなカッコして」
「ていうか二人とも怖いから」
私の言葉に二人は口を噤んだ。
「でもさ、ギャングとパンクとギャルって変な組み合わせだよな」
アマがそう言って私とシバさんを見比べた。
「ギャルじゃないってば。ねえ、私ビールを飲みたい。居酒屋いこっ」
私はシバさんの間に入り、三人並んで人通りの多い繁華街を歩いた。安い大衆向けの居酒屋で、座敷席に案内されると、他の客が私たちを一瞥して気まずそうに目を逸らした。私たちはビールで乾杯して、刺青の話でヒートアップした。アマの体験談から始まり、シバさんの彫り師になったばかりの苦労話、麒麟の画にかけた情熱。終いには二人とも上半身裸になってこの彫り方がどうだの、ここのぼかしがどうだのと熱く語り、そんな二人を見たらひどく微笑ましい気持ちになった。
その時、私はシバさんが楽しそうにしているのを初めて見たことに気づいた。二人でいた時には決して見せなかった顔だった。S男も時には満面の笑みを浮かべるんだ。「服着ろよ」とか「うるせーよ」とか言いながら、私はゴキゲンそでビールを飲んだ。素晴らしいデザイン画、楽しい宴、美味しいビール。これだけあれば、ほとんどの事が上手くいくような気がした。アマがトイレに立った隙に、シバさんは身を乗り出して私の頭を撫でた。
「あれで文句ないだろう?」
もちろん、と答えると、私たちはニッコリして見つめ合った。
「綺麗に彫ってやるからな」
というシバさんの言葉は力強く、私はこの人に出会えてよかった、と思った。
「シバさんの手にかかればお安いもんでしょ」
「ゴッドハンド?」
シバさんは苦笑交じりにそう言ってテーブルの上に置いた手をパーにした。
「彫っている時、お前の事殺したくなったらどうしよう」
シバさんはまた冷たい目に戻って自分の手を見つめた。
「いーんじゃない? それはそれで」
私はそう言ってビールをあおった。アマが戻って来るのが見えた。
「他人にこんなに強い殺意を持ったのは初めてだ」
シバさんがそう言い終わった瞬間、アマがだらしない笑みを浮かべてテーブルに戻った。
「トイレゲロまみれ。俺も吐きそうになったよ」
アマの言葉で、場の空気はあっさり元に戻った。私のために男を殴り続けた男と、私に強い殺意を持った男。どちらが、いつか私を殺すことはあるのだろうか。
二日後、アマは冷蔵庫の中のアルコール類を全て台所の棚の中に入れ、鎖を巻き付け鍵をかけた。「アル中じゃないんだから」と言うと、アマは「アル中みたいなもんだろ」と言って鍵をポケットに入れた。
「俺がいない間にコンビニにビールを買いに行ったりすんなよ」
そう言い残してアマはバイトに向かった。人の事をバカにして…‥。一日アルコールを抜くくらい何て事ない。そう思って棚を軽く小突いた。でも、その日の夜アマが帰って来る頃には、私の頭の中はビールの事で一杯になっていた。このところ、毎日昼夜欠かさず飲んでいた事を思い出した。
日常になっていて、気づかなかったけど、アルコールっていうのは本当に依存性が高いんだ、と再確認した。アマが帰ってくると、たまっていた物を吐き出すようにアマに当たり散らし、そんな私をアマはやっぱりね、という顔で宥めた。
「だから言ったじゃない。ルイは自覚が甘すぎるんだよ。いつも酒浸りなんだから」
「うっさいわね、別に酒飲みたい訳じゃないわよ。あんたの顔を見てると腹立ってくんのよ」
「はいはい。ま、酒の事は忘れてご飯食べて早く寝ようよ。明日は大勝負なんだから」
アマに宥められるなんて、何て失態だ。そう思いながら私は外に出る支度をした。夕飯はノンアルコールの牛丼だった。私は甘ったるい牛丼に腹を立て、七味をまんべんなくふりかけて食べた。アマはそんな私を子を慈しむ母のような目で見た。そんなアマの視線がウザったくて、何度もアマの頭を引っぱたいた。
家に帰るとアマは次々に指示を出し、まだ八時だというのに私は風呂上がりでアマのジャージを着せられ、アマの作った砂糖たっぷりのホットミルクを無理矢理飲まされ、ベッドに引きずり込まれた。
「眠れる訳ないでしょーが。昨日何時に寝たと思ってんのよ」
「がんばれ、寝るんだルイ。羊数えてやろうか?」
アマは頼んでもいないのに羊を数え始め、私は仕方なく目を閉じた。羊が百匹を超えようという時、突然アマは黙り込み、私を抱きしめた。
「明日、俺も一緒に行っていい?」
「何言ってんの? アマ、バイトでしょ明日」
私の言葉にアマは俯いた。
「シバさんの事信用していないわけじゃないけど、心配なんだよ。二人きりな訳だろ?」
私はため息をついた。
「大丈夫だって。シバさんはプロでしょ。そんな事する人じゃないよ」
強い口調で説得すると、アマは分かったよ。としょぼくれた顔で呟いた。
「でも、気を付けてね、本当に。たまに、あの人の考えている事が全く分からない時があるんだ」
「あんた程分かりやすい人の方が珍しいわよ」
そう言うとアマは弱々しく笑った。アマは私の服を脱がせるとうつぶせにさせて、背中を何度も撫でまわし、キスをした。
「明日には、ここに龍が舞うんだね」
「麒麟もね」
「ルイの肌、白いからもったいない気がするけど、彫ったらきっともっとセクシーだね」
アマは繰り返し背中を愛撫して、バックから入れた。アマはいつものように陰部に射精し、私はいつものようにブツブツ言いながらバスルームに向かうハメになった。
出ると、アマはまた謝り、私の体を隅から隅までマッサージした。体がほぐれると次第に意識がボヤけ始め、眠りが目前まで迫っているのが分かった。明日、行く前に舌のピアスを10Gにしようと思った。
Desireに着くと、すでにドアにはCLOSEDの札が出ていた。外は暑くて、ピラピラのワンピースもじっとり湿っていた。ドアは開いていて、押し開けるとカウンターの中でコーヒーを飲んでいるシバさんと目が合った。
「いらっしゃい」
シバさんは威勢良くそう言って、手招きした。奥の部屋に入ると、テーブルの上にはあのデザイン画が置いてあった。シバさんは黒い革の鞄をテーブルに置いて、そろりと開いた。私にはよく分からないけど、色んな道具が入っていた。先に何本も針がついている棒とか、インクとか。
「昨日はちゃんと寝た?」
「アマに急かされ八時に布団に入ったわよ」
シバさんはクスッと笑って寝台にシーツをしいた。
「服脱いで。戸棚の方頭にして寝て」
シバさんはインクや針を取り出しながら私の方を見もせずに言った。私はワンピースを脱いでブラジャーを外し、寝台に横になった。
「今日はライン彫りな。今日で形が全部決まるから。今なら形の変更とかあれば聞けるよ、何かある?」
私は上半身を起こしてシバさんの方を振り返った。
「一つだけ。お願いがあるの。龍と麒麟に目を入れないでほしいの」
シバさん一瞬あっけにとられた顔をして、おずおずと口を開いた。
「それは、瞳を入れないって事?」
「そう。目の玉を入れないでほしいの」
「どうして?」
「画竜点睛(がりょうてんせい)の話、知ってる? 瞳を描いたら、飛んで行っちゃったってやつ」
シバさんゆっくり頷き、上目遣いで宙を見つめた。そして私の方を見た。
「なるほどね。分かった。龍と麒麟には瞳を入れない。その代わり、顔のバランスが悪くなるから、インパクトをつけるために目の縁のラインにぼかしを入れるよ。それでいい?」
「それでオッケー。ありがとう、シバさん」
このワガママ女、シバさんそう言って寝台の脇の椅子に座って私の顔を撫でた。
シバさんは左肩から腰にかけてカミソリで産毛を剃り、ガーゼで消毒して、ラインをトレーシングペーパーで背中に写した。左肩から背中一帯にかけて画が写され、シバさんはそれを鏡に写すとこれでいい? と聞いた。オッケー、そう言うとシバさんは鞄の中の道具をあさり、ハンドルがついている太いボールペンみたいな物を取り出した。恐らくこれが彫る機械なんだろう。
「ねえ、見て。10Gにしたの」
シバさんの方に顔を向けて舌を出すと、シバさんはその日一番の笑顔を見せた。
「そっちも着々と進行してるな。あんまり急いで無理すんなよ。耳と違って粘膜は炎症起こすと厄介だからな」
口をすぼめてはーい、と言うとシバさんは痛かったろ? と私の唇を指でなぞって聞いた。うん、そう答えるとシバさんはまた私の顔を撫でた。
「じゃ、いくよ」
シバさんは私の背中に手を置いた。シバさんはゴム手袋をはめていて、冷たい感触がした。こくっと頷くと、背中にピリッとした痛みが走った。思ったほどの痛みではなかったけど、針が入る度に体中に軽く力が入った。
「針を入れる時に息を吐いて、抜く時に吸ってみな」
シバさんの言ったとおりにすると少しだけ楽になった。
シバさんはまるで絵を描くようにザクザクと彫っていき、二時間もすると龍と麒麟のラインが入った。シバさんは彫っている最中ずっと無言で、たまにチラチラ目を向けて観察してたけど、額に汗を浮かべて一心に彫り続けていた。最後の一針を抜いて、私の背中をタオルで拭くと、シバさんは伸びをしてコキコキと首をならした。
「お前ってほんと痛いの平気なんだな。初めての奴って大体いてぇいてぇってうるせえもんだけどな」
「ふうん。私って不感症なのかな」
「んな訳ないだろう。あんなによがっといて」
シバさんはタバコに火をつけて一口大きく吸うと私に咥えさせた。そしてまたもう一本取り出し火を点けて吸い始めた。
「優しいじゃん」
からかうように言うとシバさんは笑って、一口目がうまいんだよ、と言った。
「噓だあ。美味しいのは二口目でしょ」
シバさんは何も答えずにクスッと笑った。
「ねえ、殺したくなった?」
「ああ、だから彫る事だけに集中してた」
私は寝そべったまま灰皿に手を伸ばして灰を落とした。灰は手応えなく灰皿の中にポロッと落ち、細かい灰がヒラヒラと灰皿の外に落ちた。
「なあ。もしもお前がいつか死にたくなったら、俺に殺させてくれ」
シバさんは私のうなじに手を当てた。軽く微笑んで頷くと、シバさんはニッコリして「死姦してもいい?」と聞いた。
「死んだ後の事なんてどうでもいいわ」
私は肩をすくめてみせた。死人に口なしって言葉があるように、何事にも感想を述べられないなんて、そんな無意味な事ってない。だから私は墓石なんかに高い金を払う人間の気持ちは分からない。自分の意識が宿っていない身体になんて、興味はない。私は自分の死体が犬に食われよと知ったこっちゃない。
「でもお前が苦しそうな顔見れなかったら、勃たないかな」
シバさんは私の髪をつかみ、上に持ち上げた。首筋の筋肉がきつい角度に驚き、ビクビクした。顔を歪めるとシバさんは私の顎をつかみ、上を向かせた。
「舐めるか?」
私は無意識の内に首を縦に振っていた、シバさんには有無を言わせない、絶対的な威圧感がある。上半身を起こし、シバさんのベルトに手を掛けた。シバさんは私の首に手を掛けた。首を絞める力が強くて、殺されるんじゃないかと思った。でも、シバさんは私の背中をかばってくれたのか、ずっとバックだった。そして終わった後もずっと私の背中を見ていた。
ブラジャーをすると痛そうだったから、ノーブラでワンピースを着た。シバさんは上半身裸のまま、ずっと私を見ていた。精子を拭いたティッシュを捨てようとゴミ箱を探していると、僅かな物音が聞こえた。シバさんにも聞こえたのか、怪訝そうな顔をして店の方を見た。
「お客さん? 鍵かけてなかったの?」
「忘れてた。でも、クローズにしておいたけど」
シバさんがそう言った瞬間、ドアが開いた。
「ルイ? 来ちゃった」
「おー、今終わったとこ。お前、バイトは?」
白々しく涼しい顔で答えるシバさん。あと十分早くアマが来ていたら、どうなっていた事か。
「便秘っつて早退しちゃった」
「あんたのバイトは便秘で早退出来る訳?」
私は肩をすくめて言った。
「店長に怒られたけど、何とか」
嫌味で言ったつもりだったのに、アマはニッコリしてそう答えた。私はさりげなくティッシュをシーツの下に隠した。アマは私の刺青を見ると「おー」とか「すげー」とか騒いで、シバさんにお礼を言った。
「でもシバさん、ルイに変な事しなかったでしょうね?」
「大丈夫だよ。俺痩せている女に欲情しないの」
シバさんの言葉にホッとした表情を見せたアマ。あれ‥‥? とアマは間抜けな声を上げ、後ろめたさが残っていた私は驚いてアマを見た。シバさんも同じだったのか、ん? とでも言いたげに眉をひそめている。
「龍も麒麟も、目入ってないんじゃん」
私は胸をなで下ろして、ホッと息をついた。
「私が頼んだの」
シバさんにしたのと同じ説明をすると、アマは大きく頷いてなるほどね、と言った。
「でも俺の龍は目入ってるけど飛んでいかないよ?」
そう言う間抜け面のアマの頭をはたくと私はワンピースの紐を肩にかけた。
「しばらく、風呂入らないでね。シャワーも直接当てないで、後に、タオルとかで拭く時も擦っちゃダメだからね。それと、消毒した後は何かクリームとか塗っておいて。消毒は一日二回くらい。あと、あんまり日光に当てないでね。一週間くらいするとかさぶたが出来ると思うけど、引っ掻いちゃったりしちゃダメだよ。完璧にかさぶたと腫れがなくなったら次の施術な。とりあえず、かさぶたが完全に剥がれたら連絡して」
シバさんはそう言って私の肩を軽く叩いた。はーい、と何故かアマも私も声を合わせて返事をした。飯いきません? というアマの誘いをシバさんはこんな中途半端な時間にくわねえよ、とあっさり返し、私たちは二人でDesireを出た。帰り道で、思いっきり首をひねって背中を見ると、ワンピースから龍と麒麟が少し飛び出していた。そんな私にアマは複雑そうな顔で見ていた。
なに? と目で聞くとアマは私から目を逸らして口をへの字にした。無言のアマに嫌気がさし、半歩先を歩いていると、アマは不貞腐れた顔のまま私の手をつかんで横に並んだ。
「ルイ、何でワンピースなんて着てくんだよ。パンツ一枚で彫ってもらったんだろ?」
バカバカしい言葉に思わずしかめっ面をすると、アマはムッとした顔をして俯いた。
「Tシャツなんかよりヒラヒラな方が彫ってもらったあと楽だと思ったのよ」
そう言うとアマは俯いたまま黙り込み、つないだ手にグッと力を込めた。信号待ちで立ち止まると、やっと顔を上げて私を見た。
「情けない? 俺」
情けない顔でそう聞くアマを見てると、同情に近い気持ちが生まれた。誰かに一生懸命になっている人を見ると、いつもいたたまれない気持ちになる。
「ちょっとね」
アマは情けない顔のまま困ったような笑みを浮かべて、私が弱弱しく微笑み返すと勢い良く私を抱きしめた。仮にも、繫華街。通行人が私たちに目を止めていく。
「情けない男、嫌い?」
「ちょっとね」
アマは更に腕に力を込め、私は少し苦しくなった。
「ごめん。分かっていると思うけど、ルイのこと愛しているんだ」
やっと私から離れたアマの目は少し充血していて、ジャンキーみたいだった。頭を撫でてやると間抜け笑い、私たちはまた歩き出した。その日、私は倒れるまで酒を飲み続けた。アマは意外と嬉しそうに私を介抱した。もう、あの事件から一ヶ月近く経った。アマは、変わらず私の傍にいる。大丈夫、大丈夫だってば‥‥。私は自分に言い聞かせた。
舌ピをした。刺青が完成して、スプリットタンを完成したら、私はその時何を思うだろう。普通に生活していれば、恐らく一生変わらない筈の物を、自ら進んで変えるという事。それは神に背いているとも、自我を信じているともとれる。私はずっと何も持たず、何も気にせず何も咎めずに生きてきた。きっと、私の未来にも、刺青にも、スプリットタンにも、意味なんてない。
刺青は、四回の施術を経て、完成した。デザイン構想から四ヶ月経っていた。シバさんは彫るたびに私を抱いた。最後の施術を終えた後、シバさんは珍しく私のお腹の上の精子を拭いた。シバさんはおもむろに口を開いて「俺、彫り師やめようかな」とボンヤリ宙を見上げ、そう言った。私はシバさんを止める理由もなく、ただ黙ってタバコに火を点けた。
「アマみたいに、一人の女と付き合ってみようかと思って」
「彫り師やめるのと関係あるの?」
「人生の再出発ってやつ? 最高の麒麟彫ったし、思い残す事もーないって思って」
シバさんは自分の頭を撫でて、ため息をついた。
「無理だよな。俺って基本的にいつも転職考えているから、気にしないで」
上半身裸のシバさんの腕の麒麟は、まるでそこに君臨するかのように鋭い目をして、私を睨んでいた。
龍と麒麟は最後のかさぶたを作り、それも完全にはがれ、完璧に私の物となった。
所有、というのはいい言葉だ。欲の多い私はすぐに物を所有したがる。でも所有というのは悲しい。手に入れるという事は、自分の物であるということが当たり前になるという事。手に入れる前の興奮や欲求はもうそこにはない。
欲しくて欲しくて仕方なかった服やバッグも、買ってしまえば自分の物で、すぐにコレックションの一つに成り下がり、二、三度使って終わり、なんて事も珍しくない。結婚なんてんのも、一人の人間を所有するという事になるのだろうか。事実、結婚をしなくても長い事付き合っていると男は横暴になる。釣った魚に餌はやらない、って事だろうか。でも餌がなくなったら魚は死ぬか逃げるかの二択しかない。
所有ってのは、案外厄介なものだ。でもやっぱり人は人間も物も所有したがる。全ての人間は皆MとSの要素を兼ね備えているんだろう。私の背中に舞う龍と麒麟は、もう私から離れる事はない。お互い決して裏切られる事はないし、裏切る事も出来ないという関係。鏡に映して彼等の目のない顔を見ていると、安心する。こいつらは、目がないから飛んでいく事すら出来ない。
施術前10Gだった私の舌ピは6Gになっていた。拡張するたび、これ以上は拡張出来ないんじゃないかと思うくらい痛い。拡張した日は飯が不味い。拡張した日はイライラしてアマにあたる。拡張した日は自分が自己中心的でひどくワガママだという事を再確認する。拡張した日は皆死んじゃえばいいとすら思う。思考とか価値観は、ほぼ猿並だ。
窓からの景色が寒々しい。外に出ると乾いた空気の匂いがする。十二月に入って一週間が過ぎた。滅多に働かないフリーターには曜日感覚がない。刺青を入れ終えてから、一ヶ月以上が経った。あれからというもの、私には活力という物が全くない。寒いからだろうか。毎日毎日、時間が過ぎることを願っている。早く明日になったところで、何が解決するという訳でもないのに。
大体、問題がある訳でもない。なのに私には活力がない、朝起きて、アマを見送り、二度寝する。時にバイトをしてみたり、シバさんとセックスをしたり、友達と遊びに行ったりするけど、自分の行動一つ一つにため息が付きまとう。夜、アマが帰ってくると二人で飯を食いに行き、酒を飲んだりつまみを食べたりして、帰って来てまた酒を飲む。ただのアル中だろうか。
アマは元気のない私を飽きることなく心配し続け、無理にテンションを上げたり、機関銃のように喋り続けたりして、それでも私が暗い表情のままいると急に泣き出したり、憤りと切なさを切々と語ったり「何でだよ」と悔しそうに言ったりもした。そんなアマを見ていると、気持ちに応えてやりたいという小さな希望が生まれるけど、それはいつも自己嫌悪に押しつぶされた。
まあとにかく光がないって事。私の頭ん中も生活も未来も真っ暗って事。そんな事とっくに分かっていたけど。今はよりクリアーに自分が野垂れ死ぬところが想像できるって事。問題はそれを笑い飛ばす力が今の私にないって事。少なくとも、アマに出会うまでは生きる為だったらソープで体売るくらいの事はしてやるよ、と思っていた。
それが今の私には寝て食べるくらいの事しか出来ない。今は、臭いオヤジとやるくらいだったら死んでもいいかなと思う。一体どっちの方が健康的なんだろう。ソープで働いてでも生きてやるってのと、ソープで働くくらいだったら死んだほうがまし、ってのと。考え方としては後者の方が健康的だけど、本当に死んだら健康もクソもない。やっぱり前者が健康的なんだろう。そう言えば、セックスで満たされている女の肌の艶がいいとか言う。別に不健康でもいいけどね。
そして舌ピを4Gに拡張した。血がにじんでその日は飯を食えなくて、ビールだけで腹を満たした。アマは拡張するテンポが早いんだよ、と言ったけど、私は急がなきゃと思った。末期癌と告知された訳でもないのに、時間がないと感じた。きっと時には行き急ぐことも必要だ。
「ルイは、死にたいとか思う事ある?」
いつも通り夕飯を食べて、家に帰ってビールで乾杯した後、アマは不意にそんな事を聞いた。しょっちゅうよ、そう呟くとアマはビールの入ったグラスをぼんやり見つめてため息をついた。
「たとえお前だろうが、お前のその体を殺すことは許さない。自殺するんだったら、その時は俺に殺さしてくれ。俺以外の人間がお前の生を左右するなんて、耐えられないんだ」
シバさんの事を思い出した。私は死にとり憑かれたとき、どちらに殺しを依頼するのだろう。どっちの方が鮮やかに殺してくれるだろうか。明日、Desireに行こう、そう思った。そしたら、ほんの少し生きる気力が湧いた気がした。
昼過ぎからのバイトに向かうアマを見送った後、私はシバさんに会いに行くために化粧をしていた。化粧が終わったらシバさんに電話をしよう、そう思った瞬間だった。けたたましく携帯が鳴った。私の気持ちを読んだのだろうか。シバさんからだった。
「はい?」
「あ、俺、今大丈夫?」
「うん。今日ね、シバさんとこに行こうかと思ってたの。どうかした?」
「ああ、あのさ、アマの事なんだけど」
「‥‥何?」
「あいつ、七月頃に何か問題起こした事とかなかった?」
シバさんの質問に、胸が苦しくなるのが分かった。男を殴り続けるアマの姿が頭に浮かんだ。
「知らないけど。…‥どうして?」
「さっき、警察が来て、刺青を入れた客のリストを見せろって言われた。龍の刺青を彫った客を教えろって。アマの事かは分からないけど、俺リストなんて一見の客しかつけていないし、アマも書いていなかったからもしあいつの事もパレてないと思うけど」
「‥‥アマの事じゃないよ。アマはいつも私と一緒に居たもん」
「そうだよな。ごめん、赤い髪って言っていたから。ほら、あいつ髪赤かっただろう? だから、ちょっと気になってさ」
そう…私は呟いて大きく息を吸った。心臓の鼓動が全身を震わせた。携帯を持っている手が細かく震えていた。どうしよう、シバさんに言ってしまおうか。言ってしまえば、きっと楽になる。シバさんの意見を聞く事も出来る。でも、言っていいのだろうか。シバさんは私の話を聞いたらアマに言うのだろうか。アマは、私が新聞で読んだ事を知ったらどうするのだろうか。自首でもするだろうか。それとも、どこかに逃げたりするだろうか。
こんなにアマの傍にいるのに、あんなに分かりやすいアマの事なのに、私はアマの行動を一つも予想する事が出来ない。だって、人殺しの容疑がかかっているなんて状況。未だかつて経験したことが無い。人を殺したかもしれないとき、人は何を思うんだろう。自分の将来、大切な人の事、今までの生活、きっと様々な思いが頭に浮かぶのだろう。でも、そんなの分からない。だって私には未来なんて見えてないし、そんなのあるかどうかだって分からないし、大切な人なんていないし、生活なんて酒浸りで良く分からない。ただ一つ分かるのは、私はこの生活の中でずっとアマと一緒にいて、次第にアマを大事に思うようになってきたって事。
「ルイ、気にしないでくれ。ただちょっと気になって電話してみただけなんだから。今日、来るか?」
しばらく黙り込んでいると、シバさんが心配そうな声で言った。
「あ、うん。ありがと。今日は、やめとく。また今度行くことにする」
「‥‥来てくれないのか? 話がしたいんだ。お前と」
「じゃあ‥‥気が向いたら、行く」
私は電話を切った後、部屋中を歩き回って、とにかく考えた。イライラして、酒を飲んだ。アマと一緒に飲もう、と約束していた日本酒を開けて、ラッパ飲みした。思った以上においしくて、日本酒はどんどん私の中に落ちていった。空っぽの胃に水分が溜まっていくのが分かった。四合瓶を一本空けてしまうと、途中だった化粧を再開して、化粧が終わるとバッグを持って部屋を出た。
「こんにちは」
「‥‥何だよ、白々しいな」
そう言ってドアの方に振り返ったシバさんは、私を見ると眉間に皺を寄せて訝しげな顔をした。
「心労?」
苦笑してそう言うシバさんに、私も苦笑で返した。カウンターの前まで歩くとレジの脇で焚いているお香がツンと匂った。吐き気がした。
「冗談じゃなくて、お前おかしいぞ」
「何が?」
「前に会ったの、いつだった?」
「二週間前、くらいじゃない?」
「お前あれから何キロ瘦せた?」
「分かんない。アマんとこ体重計ないから」
「お前、気は持ち悪いくらい痩せているぞ。顔色悪いし。酒臭いし」
ショーケースに自分の姿を映して見た。ほんとだ。ガラスに映った私はまるで蚊トンボのようだった。きもちわる…自分でもそう思った。生きる気力が湧かないと、こんな症状まで出て来るのか。そう言えば、最近酒しか飲んでいない。食べるのは酒のつまみだけ。最後にちゃんとした食事をとったのはいつだろうか。私は何だかおかしくなって、肩を震わせて笑った。
「アマに食べさせてもらっていないのか?」
「アマは食べろ食べろってうるさいよ。私は酒が飲めればいいから」
「お前、そんなじゃ、自殺とかの前に餓死すんぞ」
「自殺、しないよ」
私はそう言うとシバさんの横を通って奥の部屋に入った。
「何か買ってくるわ。お前、食べたい物ある?」
「じゃあ、ビール買って来て」
「ビールは冷蔵庫に入ってるよ。他に、ないの?」
「シバさん、人殺した事ある?」
シバさんは、一瞬、私の方を見た。シバさんの目は鋭くて、体中が痛くなった気がした。「‥‥そうだな」シバさんはそう呟いて私の頭を撫でた。私は何が悲しいのか分からなかったけど、涙を流していた。
「どんな気持ちだった?」
そう言った私の声は流れ続ける涙のせいで震えていた。
「気持ち良かった」
お風呂どうだった? と聞かれたかのように答えるシバさん。聞く相手を間違えたな‥‥。私は流してしまった涙に後悔しながら「そう」と呟いた。
「服脱げよ」
「買い物行くんじゃなかったの?」
「お前の泣き顔を見たら勃つた」
私は服を脱いで下着姿になるとシバさんに手を伸ばした。シバさんは珍しく白のワイシャツなんて着ていて、下はグレーのパンツだった。ベルトを外すとシバさんは私を抱きかかえて寝台に寝かせた。見下ろすシバさんの冷たい目に反応する私の下半身。パブロフの犬じゃないんだから‥‥。
シバさんは私のあらゆる肉に指やペニスをめり込ませ、私はその都度苦しんだり喘いだりした。セックスするたび、私に触れるシバさんの指の力が強くなる。これが、シバさんの愛の証なんだろうか。このままじゃ、いつか殺される。
「お前、俺と結婚しない?」
シバさんはセックスした後、寝台で寝そべる私の隣に座り、タバコに火を点けて言った。
「話しがしたいって、その事だったの?」
「まあ、ね。アマは、お前の手に負えるような相手じゃないし、お前は、アマの手に負えるような相手じゃない。とにかく、バランスが悪いんだよ、お前らは」
「だから俺と結婚しろって?」
「いや、別に。まあ、それとは関係なしに。何となく結婚、してえと思ってさ」
シバさんは素っ気ない言い方で、変なことを言った。何となくしたい結婚って‥‥。随分曖昧なプロポーズだ。シバさんは私の返事を待たずに寝台から降りて服を着た。デスクの中からジャラッと何かを摂り出した。
「一応、指輪作ってみた」
シバさんはそう言って私にシルバーのいかつい指輪を手渡した。それは指の付け根から爪の途中まである指輪だった。いかにも‥‥というパンク臭さ。作りはしっかりしていて、関節の所は指の動きに合わせてちゃんと曲がるようになっていた。私はそれを右の人差し指にはめた。
「作った、の?」
「ああ、趣味でこういうのもやってんだ。ま、お前の趣味とかけ離れたもんだろうけど」
「ふうん、すごい。それにしてもいかついね」
そう言って笑うとシバさんも苦笑した。ありがと、私はそう言うとシバさんにキスをした。シバさんはうざったそうな顔をして、買い物に行ってくる、と言って部屋を出た。私はシバさんの言葉を思い出していた。バランスが悪い、っていうのはどういう事だろう。大体、バランスがいい人間関係なんてあるんだろうか。
無気力の中、私は結婚という可能性を考えてみた。現実味がない。今自分が考えている事も、見ている情景も、人差し指と中指で挟んでいるタバコも、まったく現実味がない。私は他のどこかにいて、どこかから自分の姿を見ているような気がした。何も信じられない。何も感じられない。私が生きている事を実感できるのは、痛みを感じている時だけだ。
シバさんがコンビニの袋を持って帰ってきた。
「ほら、食えよ。少しくらい、食えんだろ」
シバさんそう言ってカツ丼と牛丼を私の前に並べた。
「どっちがいい?」
「いらない。ビール、飲んでいい?」
シバさんが答える前に腰を上げた。冷蔵庫からビールを出して、デスクの脇のパイプ椅子に座ると一気に飲んだ。シバさんは呆れた、と言いたげに私を見ていた。
「ま、そんな調子のお前でも、俺はいいと思っているから。気が向いたら結婚してくれよ」
はーい。私は元気よくそう言うとビールを飲み干した。
暗くなる前に帰路についた。外は冷たい風が吹いていた。私は一体、いつまで生きていられるのだろう。そう長くないような気がした。部屋に帰ると、舌のピアスを2Gにした。ググ、と押し込むと血が出た。痛さのあまり涙が出た。私は一体何のためにこんな事をしてるんだろう。アマが帰って来たら、即喧嘩だろう。私は痛みに苛つきながらビールを一気飲みした。
その日、アマは帰ってこなかった。何かが起こったのは、確かだ。一緒に住み始めてからアマが帰ってこない事は一度もなかった。私が待つ部屋に、必ずアマは帰ってきた。異常な程に律儀な奴だった。バイトが延びて遅くなる時は必ず電話してきたし、そう、一度もこんな事はなかった。
携帯に電話したけど、呼び出し音すら鳴らず、留守電に切り替わった。私は眠れないまま朝を迎え、クマを作った。どうしよう。一体どうしたらいい? アマは、私を一人にして一体どこで何をしてるんだろう。アマは、今何を考えてるんだろう。何かが静かに終わるような、そんな予感がした。
「アマ」
アマのいない部屋に、情けない私の声が、響いた。ピアス、2Gにしたんだよ。早く笑って喜んで。スプリットタンに近づいたね、って笑ってちょうだい。勝手に日本酒を飲んでしまった事を、あきれ顔で怒ってよ。
私は考えるのをやめて自分を奮い立たせた。私は意気込んで部屋を出た。
「捜索願って、親族以外でも出せるんですか?」
「あー、出せるよ」
警察のやる気のない態度に私は苛立った。
「あ、出すときは写真持って来てね」
私はそれに答えず交番を出た。私はズンズンと歩いていたけど、何処に向かっているのか分からなかった。私はふと、足を止めた。あ‥‥。私の中にまた一つの不安が生まれた。
「私、アマの名前知らないじゃん」
小さく呟くと、事の重大さが分かってきた。名前を知らないって事は、捜索願も出せないって事だ。私は顔を上げて歩き出した。
シバさんは必死の形相の私に驚いたような顔でもの言いたげに見つめた。
「アマの名前なんて言うの?」
「は? 何、急に」
「アマが、帰ってこないのよ。捜索願出すの」
「何だ? 名前って、名前知らねーの?」
「知らないのよ」
「一緒に暮らしてるんだろ?」
「暮らしているわよ」
言いながら、私は涙を浮かべていた。
「泣くなよ。だって表札とか手紙とか見るだろ普通」
シバさんは、よほど私の涙に引いたのか、目の前で大事故が起きたような顔で私を見つめながら言った。
「アマ表札なんか出していないし、郵便受けはいつもチラシが満タンになってから開いたこともなかったよ」
「ていうか、昨日は普通に仕事行ってたんだろう? 昨日の夜帰ってこなかって事か?」
「そうよ。昨日バイトに行ったきり帰ってこないのよ」
「一日くらいで何でそんなにいきり立ってるんだよ。大丈夫だよ。大体一日家を空けたくらいでそんな慌てるんだよ。アマは子供じゃねーんだぞ」
要領を得ないシバさんの言葉に、私は苛立った。
「アマは私と暮らし始めてから一度も無断で外泊なんてしたことないのよ。バイト三十分延びるってだけで電話してくるような男なのよ」
シバさんは黙り込んで、カウンターに視線を落とした。だからって‥‥、シバさんは呟いて私を見上げた。何故こんなに不安なのか、自分でもわからなかった。そう、シバさんの言っている事は正しい。一日くらい家を空けたって、心配する事はないんだ。
「アマ、人を殺したかもしれないの」
「あの。警察が言っていた暴力団員の‥‥・?」
「私がいけなかったの。私があそこであの男をシカトしてれば、アマはあの男を殴らなかった。まさか、死ぬなんて思ってもいなかったし、新聞見た時もまさかあのアマが殴った男なんて思ってもなかった。きっと別人だって思った。アマの事だなんて‥‥」
シバさんは私の手を取って強く握った。
「捜索願出したら、アマは捕まるかもしんねーぞ。もしもアマが事件のことを知って逃げているとしたら、このまま俺たちが知らないふりをしていれば、アマは逃げきれるかもしれない」
「‥‥アマが心配なの。どこで何して何を考えているか、分からないのが辛いの。アマは、アマは一人で逃げようと考えない。逃げるんだったら、絶対私に何か言っていくはずよ。きっと、私を連れていくはず」
「‥‥分かった。行こう」
シバさんは店を閉めて、私たちは警察署に向かった。シバさんは手際よく捜索願を出すとアマが上半身裸で写っている写真を手渡した。
「写真なんか、持っていたんだ」
「ん? ああ、彫ってやった時に龍撮って、悪ノリして二人で撮ったんだよ」
「雨田和則(あまだかずのり)さん、ですね」
警察が用紙に目を通しながら言った。私は初めてアマの名前を知った。アマダウスじゃ、ないじゃん。再びアマに会うことが出来たら、まず最初にそれを突っ込もう。そんな事を考えていたら、涙が出てきた。私は涙を止めることが出来なくなって、あたふたした。冷静なのに、涙腺が故障したように涙がダクダク流れた。
「‥‥大丈夫か?」
シバさんが私の頭を撫でたけど、涙を止める事が出来なくて、下を向いたまま署の入り口まで歩いて、待合い用の椅子に座って泣いた。どうして。どうして突然いなくなったりするのよ。私は身体を折り曲げて俯いたまま泣きじゃくった。しばらくすると手続きを終えたシバさんが戻って来た。私の視界は曇ったまま。拭いても拭いても涙が溢れる。コートの袖でゴシゴシ涙を拭いていると、子供の戻ったような気がした。私たちはタクシーでアマの家に戻った。
「アマ?」
玄関で呼んだけど、返事はない。シバさんは後ろから私の頭を撫でるとまた溢れだした私の涙を拭った。部屋に上がるとフローリングにべったりと座り込んで、泣いた。グズグズ泣き続ける私を、シバさんはベッドに座って観察するように見ていた。
「どーしてよつ」
そう叫んでフローリングを殴ると、人差し指にはめていたシバさんからもらったリングがぶつかって鈍い音がした。その音に反応して、私はまた激しく泣きじゃくった。一体、どうして、どうして私の事を置いてったのよ。涙が止まると怒りが込み上げてきた。
歯を食いしばっていると、頭が痛くなった。ガリ、と口の中で嫌な音がした。舌で口の中をまさぐると、虫歯だった奥歯が欠けていた。私は欠けた歯をかみ砕いて飲み込んだ。私の血肉になれ。何もかも私になればいい。何もかも私に溶ければいい。アマだって、私に溶ければ良かったのに。私の中に入って私の事を愛せば良かったのに。私の前からいなくなるくらいなら、私になればよかったのに。そうしたら、私はこんな孤独を味わう事はなかったのに。私の事を大事だって言ったのに。何でアマは私を一人にするの。どうして。どーして。
部屋中に、耳障りな泣き声が舞う。私はアマと二人で使っていたジュエリーボックスを開け、ピアスを摂り出した。昨日は2Gにしたばかりで、到底普通に入る訳ないから、短い角型のピアスを選んだ、大台の0G。私を見ていたシバさんの顔色が変わった。
「お前、それ0だろ。昨日4だったじゃねーかよ」
シバさんの言葉に振り返らず、鏡向かって2Gのピアスを外した。ピアスを差し込むと、真中まで入れたところでビリビリした痛みが走った。一気に、奥まで押し込んだ。シバさんが手を伸ばしたけど、ピアスは私の舌にギュウッとはまっていた。
「お前、何してんだよ」
シバさんは私の口を開け、眉をひそめて覗き込んだ。
「舌出せ」
言われた通りにすると、血が舌を伝わって床に落ちた。涙も、落ちた。
「ピアス、外せ」
私が左右に首を振ると、シバさんはひどく落ち込んだような顔をした。
「無理な拡張はすなって、言っただろう」
シバさんは私を抱きしめた。シバさんに抱きしめられたのは、初めてだった。私は、どうしていいかも分からずに、溢れる血をゴクッと飲み込んだ。
「私、00にしたら切る」
ろれつの回らない私の言葉は、アマの笑顔のようにだらしなかった。
「分かったよ。分かったから」
気づくと、涙は止まっていた。アマは、私の0Gを見たら何て言うだろうか。すごいじゃん、そう言って笑ってくれるはずだ。もうちょっとだね。そう言うはずだ。きっと喜んでくれる。
私はビールを飲み、ひたすら泣いた、アマを待った、シバさんはずっと私を見ていたけど、何も言わなかった。また、夜が来た。部屋の中はひんやりしていて、私は身震いした、シバさんは黙ったまま暖房を入れ、座り込んだまま私に毛布をかけた。
舌の血は止まった。涙は、断続的に流れた。悲しくなったり、怒りが込み上げてきたり、感情は揺れ動いた、七時になった。いつものシフトだったらアマが帰って来る時間だ。私は十秒ごとに時計を見上げ、何度も携帯を開いた。何度かアマの携帯に電話をしたけど、やっぱり留守電話に切り替わった。
「ねえ、アマがバイトしてる店って知っている?」
「‥‥え? お前、知らないの?」
シバさんが不思議そうな顔で私を見た。そう、私たちは何も知らない。
「知らないの」
「古着屋だよ。お前らって、ほんとに何も知らないんだな。って事は、まだ連絡してないの?」
「うん」
シバさんは携帯を開いてカチカチ検索すると耳に当てた。ああ、俺だけど。アマの事でさ。‥‥ああ、無断欠勤ね。昨日は? ‥‥ああ。家にも帰って来ていないんだよ。‥‥まだ分からない。‥‥ああ、何か分かったら連絡するからさ。
シバさんの言葉だけで、何も手がかりがないと分かった。シバさんは電話を切るとため息をついた。
「昨日は普通にバイト上がって帰って行ったてさ。今日は無断欠勤だって。電話してもつながらないって怒ってた。アマのバイト先、俺の知り合いの店なんだよ。無理言ってあいつを雇ってもらったんだ」
私はアマの事を何も知らない。昨日までは、自分が見ているアマの事だけ知っていればいいと思っていた。でも今はアマの事も何も知らないという事がひどく私のハンデになっている。どうして、名前や家族構成くらい聞いて置かなかったのだろう。
「知らない。でも、多分親は片方はいるんじゃないかな。父親の話、してた気がするけど」
そう、私は呟くとまた泣いた。
「なあ、何か食いに行かねぇ? 俺腹減ってんだけど」
シバさんの言葉に反応して、また私は泣き出す、いつもそうだった。私がビールだけで腹を満たしてしまうから、アマはいつも腹減った腹減った、と言って無理矢理私を外に引っ張り出していた。
「私、ここにいる。シバさん行って来なよ」
シバさん答えず、台所に行くと冷蔵庫をあさった。酒ばかりじゃねーかよ。シバさんがそう吐き捨ててイカの塩辛を取り出した瞬間、シバさんの携帯が鳴った。
「ねえ、鳴ってる」
私の声は、自分でもビックリするくらい大きく響いた。具合が悪くなるような動悸に、胸を押さえながら携帯を取って、シバさんに投げた。ナイスキャッチ。
はい? はい。ええ、はい。はい‥‥はい。分かりました。すぐ行きます。
シバさんは電話を切ると私の肩をしっかりつかみ、私を睨みつけた。
「横須賀で死体で発見されたらしい。アマかどうかはわからないけど、龍の刺青が入ってるって。確認に遺体安置所来てくれ、ってさ」
「‥‥そう」
そう、アマは死んだ。遺体安置で見たアマはねもう人間でなく、一体二体…と呼ばれる死体になっていた。人間であるアマは、もういない。現場で撮られた写真を見て、私は失神しそうになった。アマは、胸にナイフかなんかで網のような模様を刻み込まれていて、タバコを押し付けられた痕も無数にあった。爪は手も足も全て剝げていたという。アマは裸で、ペニスには何かお線香のようなものが刺してあった。
短い髪は所々むしり取られていて、血が滲んでいた。もう何ていうか、いじるだけいじり倒された後に、殺されたって事。自分の所有物のように思っていた人間がこれだけ他人に弄ばれた後に、殺された。こんな絶望、私はこれまでの人生の中で初めてだった。そして、アマの死体は解剖に回され、更に切り刻まれる事になった。
怒りすらも、痺れた頭は受け付けない。多分、私のアマへの最後の言葉は、今日はシバさんところに遊びに行こう、と考えながら背を向けたまま言った「行ってらっしゃい」だったと思う。シバさんはフラフラする私に何度も何度も手を貸し、遺体安置所で膝から崩れ落ちた私を支えた。そう、やっぱり私の未来に光なんて見えない。
「お前、しっかりしろよ」
「無理」
「お前、飯くらい食えよ」
「無理」「お前、少しくらい寝ろよ」
「無理」
アマが発見されてから、シバさんのところにお世話になる事にした私は、何度となくシバさんとこんなやり取りをした。会話にならねぇ…シバさんはいつもそう言って舌打ちをした。司法解剖の結果、死因は首を絞められた事によると窒息死。何とか反応がどうで、身体につけられた傷は全て生きているうちに付けられた事が分かった。
へえ、ていうか、早く犯人を見つけろよ。アマがどうやって殺されたなんて事よりも犯人が誰かが知りたいんだよ。手がかりなんて、たくさんあるだろ。私がどうしても納得出来なかった。アマの死体が発見された時、あの暴力団の仲間がやったのかと思ったけど、どうも違うんじゃないかと死体を見て思った。
暴力団が、タバコでヤキを入れたり、ペニスに線香を刺したり、そんな足のつくような証拠を残していくだろうか。どうせなら死体を東京湾に沈めてしまって欲しかった。あんな死体、私は見たくなかった。見つからなかったら、いつまでもアマは生きている、という自信をもっていられたのに。そう、アマはあの暴力団を殺していた。今更犯人が死体で見つかっても、しょうがない。アマが起こしたあの事件は、今まで何の意味もない。被害者も、加害者も、死んでしまったのだから。
アマの葬式に行った。アマのお父さんは、人の良さそうな顔をしていて、喪服に似合わない金髪の私を、嫌な顔一つせずに迎えてくれた。火葬場で棺の顔の部分を開けた時、私はその中を覗き込めなかった。お別れなんか言いたくなかった。遺体安置所で見たアマはまだ生きていて、棺の中にいるのは別人だと思いたかった。現実逃避をする以外なかった。こんなに思い悩むって事は、もしかしたら、私はアマの事を愛していたのかもしれない。
「いつになったら犯人は捕まるの?」「あの、こちらも、全力で捜査してますので」
「‥‥何? 私の言い方押しつけがましい?」
葬式が終わった後、私は警察に詰め寄った。
「ルイ、やめろよ」
シバさんが私を押し止めた。犯人も捕まえられないで、何葬式なんて来るんだよ。
私は憤りを抑えることが出来なかった。
「何? 人の事押しつけがましいって言うの? そんな権限ねーだろうお前らによ。じゃあ何? 犯人捕まえろっていう私はおこがましいの? アマが人殺しだから手ぇ抜いてんだろ。おめーらみんな死んでしまえ。みんな死にゃーいーんだよ。それで何もかも解決だろ」
「いい加減にしろよ、ルイ。言っている事が、支離滅裂だぞ」
私はその場で崩れて泣きわめいた。ふざけんなよ、死ねよ、ばかやろー。私のボキャブラリーの少なさがこんな所で暴露された。情けない。自分でも分かっていた。何て情けないんだ。私は。
アマが死んで、五日が経った。犯人はまだ捕まっていない。私はDesireにいた。シバさんに連れられて一度病院に行ったきり、外に出なくなった私を見かねて、シバさんが一緒に店番をしようと言ってくれたのだった。シバさんは、気まぐれに何度か私を抱こうとしたけど、首を絞めても苦しい顔をしなくなった私のことは抱けなかった。首を絞められると、苦しいという思いより先に早く殺して、と思ってしまう。
多分、それを口に出していたら、シバさんは私を殺してくれるだろう。でも、私は殺してと言わなかった。言葉を口にするのが億劫だったのか、この世に未練があるのか、まだアマは生きていると思いたいのか、私には分からない。ただ、私は生きている。アマがいない退屈な日々を生きている。シバさんに抱かれる事も出来ない退屈な日々を生きている。そして、私はつまみさえも食べるのを止めた。半年前に計った時は四十二キロあった体重が、三十四キロになっていた。物を食べて排泄する何て面倒臭い事、出来ればしたくない。
でも、酒しか飲まない私でも、排便する。これを宿便というらしい。腸の中には常にウンコが溜まってるんですよ、と連れられていった病院の先生が言っていた。先生は、このまま痩せてったら死にますよ、と穏やかな口調で私に言った。入院を勧められたけど、それはシバさんが断った。抱けない女なんて囲ったって、シバさんは一体どうするつもりなんだろう。
「ルイ、そこのラック整理して」
シバさんの言葉に私は素直に従い、今値段を貼ったばかりのピアスの袋をまとめてラックに向かった。シバさんはさっきから店のあらゆるところを掃除している。心機一転、って事なんだろうか。そう言えば、もう今年も残り少ない。寒さも厳しくなる一方だし、クリスマスなんていうイベントもすぐそこまで近づいている。年末の大掃除のつもりだろうか。
「ねえ、シバさん」
「お前さあ、そろそろさん付けで呼ぶのはやめない?」
「俺の名前は、柴田キヅキって言うんだ」
シバさんのマンションの表札に名前が書いてあったから、知っていた。
「女の名前みてえだろ、キヅキって。何でか知らないけど、みんなシバって呼ぶんだよな」
「なんて呼べばいいの?」
「キヅキでいいよ」
こういう普通のカップルならあるはずの会話が、アマと私にはなかった。だから、思い残す事がたくさんあるのかもしれない。もっと、普通の会話をすればよかった。家族の話とか、過去の話とか、名前とか、歳とか。そう、葬式の時初めて知った。アマは十八歳だって事。私は、生まれて初めて年下の男と付き合っていた事を、彼が死んでから知った。私は十九歳で、アマの一個年上だった。そんな事、出会ったその日に話すべきだったのだ。
「ギヅキ」 言いにくい。そう思ったけど、そう呼ぶことにした。
「何?」
「ここのラック、もう一杯で入らないんだけど」
「あー、適当でいいよ。隣のラックに掛けてもいいし。無理やり押し込んでもいいし」
私はラックにぎゅうぎゅうピアスを押し込んだ。かなり無理矢理だったけど、袋はラックに整列した。ピアスを見ていたら、アマの事が頭に浮かんだ。あれからというもの、舌の痛みも治まってきたというのに、私は舌ピを拡張する気にはなれない。褒めてくれる人もいない今、私の舌ピは意味を持たないのだろうか。もしかしたら、私がアマに言ったように、アマと同じ気持ちを共有したくてスプリットタンを目指していたのかもしれない。
後一つ拡張すれば、アマがメスを入れた00Gになる。00Gにしたら切ろうと思っていた。アマも熱意もなくなってしまった今、この舌ピに一体何の意味があるんだろう。私はまたカウンターに戻ってパイプ椅子に座るとボンヤリ宙を見つめた。何もする気がない。何かする事にも、それで何かが動くという事にも、今の私には関心がない。
「ルイ、お前の名前、聞いてもいいか?」
「聞きたいの?」
「聞きたいから訊いているだろう」
「私のルイはルイ・ヴィトンの…」
「本名を聞いているの」
「…‥中沢ルイ」
「本名だったんだ、ルイって。ルイ、家族は? 親はいるの?」
「私はいつも孤児に見られるけど、両親いるのよ。今埼玉に住んでるんじゃないかな」
「へえ、意外。今度挨拶しに行かなきゃな」
どうして、私は孤児に見られるのだろう。両親健在で、家族関係には今のところ何も支障はないというのに。シバさんはご機嫌な様子でラックにハタキをかけていた。
私はそんなシバさんみて、一日を過ごした。
次の日、私はDesireに行かなかった。警察に行った。朝方、電話があった。新しくいくつかの情報が入ったという。シバさんは店に出なければならなかったから、私が行くことにした。私はしっかり化粧して、アマの好きなワンピースを着た。寒かったら、カーディガンとコートを羽織った。
「押し付けられたタバコは、全てマルボロのメンソールでした。唾液の鑑定も進めています。それから、陰部に挿入されていたのは、アメリカから輸入されているEcstasyというお香で、種類がムスクでした」
そんな事分かって、どうすればいいんだよ、という憤りがまた怒りを増長させる。アマも、私も、シバさんも、マキも、みんなマルボロのメンソールだ。タバコの銘柄なんて分かっても嬉しくない。
「お香なんて、何処でも売ってるんでしょ」
「ええ、まあ。でも関東区域に限られます。それと、今日は中沢さんに聞きたいことがあるんです」
刑事の顔が一瞬緊張したのが分かった。
「雨田さん、バイセクシャルの気がありましたか?」
私の怒りはマックスになった。悪気があって聞いたわけじゃないのは重々承知だけど、この刑事の顔をシバさんに貰った人差し指の指輪で叩き潰してやりたかった。
「アマがレイプされてたとでも言うの?」
「…‥検死の時に解かったんですが」
私はフゥ、と息をつくと記憶を巡らせた。アマのセックスはいつも単調でアブノーマルなところなんて一つもなかったし、ほぼ毎日のように私とセックスしていた。こっちが嫌になる程単調だったんだ。そんなはずはない。アマが誰か他の男にレイプされていたなんて、考えただけでも反吐が出る。
「そんな気はありませんでした。断言出来ます。絶対にそんな趣味はないはずです」
警察とすれ違うたびに奴らを軽蔑の目で見つめつつ、私も署を出た。そして、収穫が無かった事を伝えるためにDesireに向かった。アマがレイプされたなんて、思いたくもなかった。大体、アマはどっかと言えばネコよりもタチの方だ。アマにそんな趣味があるはずない。
私はDesireのドアを開け、カウンターの中でタバコを吸っていたシバさんに弱々しく微笑んだ。シバさんに、アマが犯されていた事を話すつもりはなかった。アマの印象が汚れるのは、私の頭の中だけで充分だ。
「収穫無し」
シバさんは私の真似をするように弱々しく微笑んで「そうか」と呟いた。シバさんはアマが死んでからというもの、私に優しくなった。変わらず乱暴な言葉遣いをするけれど、どこか表情や行動の端にシバさんの心遣いや優しさを感じることが多くなった。シバさんは私が奥の部屋に連れていき、私が寝台に横になったままいたけど、シラフでは眠れそうにないと思い、起き上がって冷蔵庫を開けて。安い赤ワインを開け、ラッパ飲みした。
久々に食欲を感じた私は、冷蔵庫に入っていたパンを砕いて一口だけ食べた。イースト菌の匂いに、吐き気がした。パンを戻して冷蔵庫のドアを勢いよく閉めると、ワイン片手にデスクの椅子に腰掛け、バッグから化粧ポーチを出してあのアマがくれた、アマいわく愛の証の歯を眺めた。
手のひらに載せ、コロコロと転がしてみた。アマがいなくなった今、この二つの愛の証は何を意味するんだろう。こんな事をして、私は一体何を求めているんだろう。アマは私が手の届かないところに行ってから。私はこの歯をよく眺めるようになった。いつも、この歯をポーチにしまうたび、一つ諦めに近い気持ちが生まれる。
いつも、この歯を眺める習慣がなくなったら、私はアマを忘れた事になるんだろうか。私は歯を化粧ポーチにしまった。その時、私は目にある物が映った。デスクの半開きの引き出しから覗く、細い紙のパックだった。一瞬にして、最悪の結末を予想した。私が手に取った物、それはEcstasyの、ムスク。私は立ち上がった。
「買い物に行ってくるね」
驚いた顔で、どこに? と言うシバさんに振り返らず店を飛び出した、アジアン雑貨の店に向かった。駆け足だった。
息を切らしてDesireに帰ると、シバさんが心配そうな顔で私の頭を撫でた。
「ルイ、どこに行ったんだよ? 心配したぞ」
「お香、買ってきた。私、ムスク嫌いなの」
私はデスクからムスクのお香を持って来ると全部ひとまとめにしてパックごと半分に折ってゴミ箱に捨てた。
「ココナッツ買ってきた」
私はココナッツのお香に火を点け、お香の台に差した。
「どうかした? ルイ」
「ううん。何も。そうだキヅキ、髪の毛伸ばしてよ。私ね、長髪が好きなの」
私の言葉に、シバさんは笑った。前だったら、きっと「うるせぇ」とか言って冷たい目で睨んでいただろう。
「そうだな、たまには伸ばしてみるか」
その日、私はシバさんと一緒に家に帰って、少しだけご飯を食べた。気持ちが悪かったけど、シバさんがすごく喜んでくれたから、吐かなかった。ベッドに入って、シバさんが眠るまで添い寝をした。静かな空気の中、私はずっと頭の中で反吐が出そうな妄想を繰り返していた。シバさんが、アマを犯しながら、首を絞めている場面がリピートしていた。その時、もしかしたらアマは笑っていたんじゃないか、とか、シバさんは泣いてたんじゃないか、とか、色々想像をした。
もしもシバさんが犯人だとしたら、アマはその時シバさんが私にするよりも強く首を絞められていたという事は確かだ。シバさんが寝息をたてると、私はリビングでビールを飲んで、あのアマがくれた愛の証を、また眺めた。私は物置になっている玄関脇の棚をあさってトンカチを手に取った。二本の歯をビニールとタオルにくるみ、トンカチで砕いた。ボス、ボスという鈍い音が胸を震わせた。粉々になると、私はそれを口に含んで、ビールを飲み干した。それはビールの味がした、アマの愛の証は、私の身体の中に溶け込み、私になった。
次の日、私たちはDesireに出勤して、二人で店を開けた。私はほんの少しだけど、シバさんの買ってきたパンを食べた。シバさんはそんな私を満足げに眺めた。
「ねえ、キヅキ、お願いがあるの」
「何?」
私はワンピースを脱いで寝台に横になった。
「本当に、いいんだな」
私は黙ったままコクッと頷いた。シバさんあの機械を手に持った。そう、ボールペンみたいな機械で、私の背中の龍と麒麟に、瞳が入る。私の龍と麒麟は、目を持つ。命を持つ。いくよ‥‥シバさんの言葉と共に、私の背中に懐かしい痛みが走った。刺青を入れたあの時私は一体何のために入れたのだろう。今、私はこの刺青には意味があると自負できる。私自身が、命を持つために、私の龍と麒麟に目を入れるんだ。そう、龍と麒麟と一緒に、私は命を持つ。
「飛んでいかねえかな」
シバさんは私の背中に針を刺しながら言った。
「飛んでっちゃうかもね」
私はクスクスと笑ってシバさんの顔を盗み見た。シバさんは、もう私を犯せないかもしれないけど、きっと私のことを大事にしてくれる。大丈夫。アマを殺したのがシバさんであっても、アマを犯したのがシバさんであっても、大丈夫。龍と麒麟は目を見開いて、鏡越しに私を見つめていた。
閉店前に一人で部屋に帰った私は、舌ピを外し、舌先の残った肉をデンタルフロスデきつく縛ってみた。ぎゅっと結ぶと鈍痛が走った。もう残りは五ミリ程度だった、このま切ってしまおうかと思ったけど、私は眉バサミを手に取り、デンタルフロスをパチンと切った。デンタルフロスは弾けるようにほどけ、痛みはすぐに和らいだ。私はこれを求めていたのだろうか。この、無様にぽっかり空いた穴を、求めていのだろうか。舌の穴を鏡に映してみると、肉の断面が唾液に濡れて、テラテラと光っていた。
翌朝、明るい陽の光の中で目を開けた。ひどく喉が渇いていて、仕方なく起き上がると台所に向かった。冷蔵庫の中の冷え切った水をペットボトルのまま飲むと、舌の穴に水が抜けていく。まるで自分の中に川が出来たように、涼やかな水が私という体の下流へと流れ落ちていった。
シバさんはもそもそと起き出して、鏡向かっている私を不思議そうに見て、目を擦った。
「何しての?」
「私の中に川が出来たの」
「へえ。ねえ、俺さ、変な夢見たんだ」
「どんな?」
「昔仲が良かった友達がさあ、ヒップポップやってて、俺その友達と遊びに行く事になったんだ。でも俺待ち合わせにすげえ遅れちゃってさ、そしたら友達とその仲間が怒りを歌で表現していくんだよ。俺は五、六人に囲まれて歌われたんだ。ラップで怒りの歌」
私は、なかなか布団から出ないシバさんを見ながら、00Gに拡張したら、川の流れはもっと激しくなるんだろうか、なんて考えていた。陽の光が眩しすぎて、私は少しもっと激しくなるんだろうか、か、なんて考えていた。陽の光が眩しすぎて、私は少し目を細めた。
第二回すばる文学賞作 すばる2003年11月号掲載
金原ひとみ
蛇にピアス 2004年1月10日第一冊発行
「何? そけ。分かれた舌って事?」
「そうそう。蛇とかトカゲみたいな舌。人間も、ああいう舌になれるんだよ」
男はおもむろにくわえたタバコを手に取り、べろっと舌を出した。彼の舌は本当に蛇の舌のように、先が二つに割れていた。私がその舌に見とれていると、彼は右の舌だけ器用に持ち上げて、二股の舌の間にタバコを挟んだ。
「‥‥すごい」
これが私のスプリットタンの出会い。
「君も、身体改造してみない?」
男の言葉に、私は無意識のうちに首を縦に振っていた。
スプリットタンていうのは主にマッドな奴らがやる、彼等の言葉でいえば身体改造。舌にピアスをして、その穴をどんどん拡張していって、残った先端部分をデンタルフロスや釣り糸なで縛り、最後にそこをメスやカミソリで切り離し、スプリットタンを完成させる。と、彼は手順を教えてくれた。ほとんどの人はこのやり方で改造するらしいけれど、中にはピアスなしでいきなりメスを入れる人もいるという。大丈夫なの? 舌嚙み切って死ぬんでしょ? っていう質問に、蛇男は淡々と答えた。
焼きゴテを当てて止血するんだよ。手っ取り早いけど、さすがに俺はピアス使ってる。ピアスでやると時間はかかるけど、いきなり切るより綺麗な切り目が出来るのだ。私は血まみれの舌に焼きゴテを当てるシーンを想像すると、腕に鳥肌が立った。今、私の右耳には0Gのピアスが二つ、左耳には下から0、2、4Gのピアスが並んでいる。ピアスのサイズはゲージという単位で表され、Gと略される。ゲージは、数が小さくなっていく程太くなっていく。
普通の耳ファーストピアスは、大体16Gから14Gで、太さは一・五ミリ程度。0Gで、これが九・五ミリ程度。それ以上の物は分数で表され、一センチを超える。でも、はっきり言って00を超えてしまうとどこかの民族みたいで、かっこいいとか悪いとかの話ではなくなってしまう。耳の拡張でもかなり痛いと思ったのに、舌の拡張なんてどれだけ痛いのか想像もつかない。
元々16G程のピアスをしていた私はクラブで知り合った二つ年上の女の子、エリの00Gに憧れて拡張を始めた。「かっこいいね」と言うと、えり「ここまでやっちゃうともう細いのは使わないから」と言って12から0、までのピアスを何十個もくれた。16から6くらいまでは、難なく拡張出来た。4から2、2から0、これはもう拡張そのもの。
穴には血が滲み、耳たぶは赤く腫れ、二、三日はじんじんしている。0にするまでに三ヶ月もかかった。エリの信念「拡張機は使わない」これを私も引き継いだ。そろそろ私も00に踏み込んだか思っている頃だった。拡張にハマっていた私はスプリットタンの話をかじりつくように聞いた。男はまんざらでもなさそうに語ってくれた。
そして数日後、私は蛇男ことアマと二人でパンクなDesireに来ていた。その店は繫華街の外れの地下にあって、入るなり目に飛び込んできたのはもろに女性器がアップの写真。ビラビラの部分にピアスが刺さっていた。他にも、タマにピアスが刺さっている写真や、刺青の写真。そんなのが壁に貼ってあった。中に進むと普通のボディピアスやアクセサリーもあったけど、ムチやペニスケースまで並べてある。
私に言わせてもらえれば変態向けの店だった。アマが声を掛けるとカウンターの中から頭がひょこっと現れた。その頭はスキンヘッドで、つるつるの後頭部に丸くなっている龍が彫ってあった。
「おー、アマ、久しぶり」
多分、二十四、五くらいのパンクな兄ちゃん。
「ルイ、この人が店長のシバさん。あ、これ、俺の彼女っす」
はっきり言ってアマの女のつもりはなかったけど、黙ってシバさんに会釈した。
「あー、そう。可愛い子捕まえたねえ」
私は軽い緊張で、どうも落ち着かなかった。
「今日は、こいつの舌、穴開けてもらおうと思って」
「ふうん。ギャルも舌ピとかするんだ」
シバさんはもの珍しそうに私を見た。
「ギャルじゃないです」
「こいつもスプリットタンをやりたいって言うんですよ」
アマは私の言う事なんか聞いてないようにイタズラっぽく笑った。いつだかピアスショップで、性器以外のピアスで一番痛いのは舌ピだと聞いた事がある。こんなパンクな男に任せて平気なんだろうか。
「お姉ちゃん、おいで。舌見せて」
カウンターに近づいて舌をベロツと出すと、シバさんは軽く身を乗り出した。
「あー、まあまあ薄いからそんなに痛くないと思うよ」
私はその言葉に少しほっとしていた。
「でも、焼き肉だとミノの次くらいにタンって歯ごたえありますよね」
ずっと思っていた。あんなにプリプリしている肉に穴を開けるなんて、大丈夫なんだろうか。
「お姉ちゃん、いいとこつくね。うん、まあ耳とかに比べたら痛いよ。まあ、ね。だって穴開けるんだもん、痛いよそりゃ」
「シバさん怖がらせないでくださいよ。大丈夫だよルイ、俺だって出来たんだから」
「何だよ、アマだって開けた時は悶絶してたじゃねーかよ。いいや。おいで」
シバさんがカウンターの奥を指差して私に微笑んだ。笑顔が歪んでいる人だと思った。シバさんの顔は瞼、眉、唇、鼻、頬にピアスが刺さっている。こんなに武装されたら、表情なんて分からない。それに、シバさんの両手の甲は一面ケロイドに覆われていた。一瞬火傷かと思ったけど、チラッと観察するとそれが全て直径一センチ程の丸である事に気づいた。
根性焼きでケロイドを施したんだろう。全く、狂ってる。こういう人種と関わるのは、アマが初めてだった。そして、このシバさんという人は舌こそスプリットではないものの、顔中のピアスが近寄りがたくさせていた。アマと一緒に奥の部屋に入ると、シバさんはパイプ椅子を指差した。座って部屋を見渡す。寝台や、私にはよく分からない器具、壁にはやっぱりきわどい写真。
「ここって、スミもやってるんですか?」
うん、俺も彫り師なんだよ。これは人にやってもらってるんだけど」
シバさんはそう言って頭を指差した。
「俺もここで入れたんだ」アマが言う。
アマと知り合ったあの日、私たちはスプリットタンの話で盛り上がり、私はアマの部屋に持ち帰りされた。アマは舌ピを拡張していく過程やメスで切り裂いた時の様子を写真に収めていて、私はそれを一枚一枚じっくり眺めた。アマは00Gまで拡張し、メスで切り離した部分はほんの五ミリ程度だったけど、驚くくらい血が流れていた。
それからアマは舌を切り離す映像をネットで公開しているアンダーグランド系のサイトに行き、その映像を私はアマが呆れるほど繰り返し何度も見た。どうして自分がこんなに興奮しているのか分からなかった。その後、私はアマと寝た。寝た後、左の二の腕から背中にかけての竜の刺青をかっこいいでしょー? と自慢するアマを受け流しつつ、スプリットタンを完成させたら刺青もやってみようと思った。
「刺青、やってみたいな」
「ほんとに?」
シバさんとアマは声を揃えた。
「いいね、絶対綺麗に入るよ。あのね、刺青っていうのは男なんかより女がやった方が断然綺麗なんだよ。特に若い女の子はね。肌のキメが細いから繊細な絵が彫れるんだよ」
シバさんは私の二の腕を撫でながらそう言った。
「シパさん、ピアスが先っすよ」
しばさんは、「ああ、そうか」なんて言いながらスチールラックに手を伸ばし、ビニールに入ったピアッサーを持ってきた。ピストル型の、耳に穴を開けるのと同じようなやつ。
「舌出して。どの辺に開ける?」
鏡の前で舌を出して、先端から二センチほどの中心に指をさすと、シバさんは慣れた手つきで私の舌をコットンで拭き、指差した部分に黒い印を付けた。
「テーブルに顎を載せて」
私は舌を出したまま言われるままに体を低くした。舌の下にタオルが敷かれ、シバさんがピアッサーにピアスをセットした。私は思わずシバさんの腕をバシバシこづき、首を振った。
「ん? 何?」
「14にして。お願い」
私は必死になって、反対するアマとシバさんを説得した。耳のファーストピアスだって、いつも14か16だった。シバさんは14のピアスをセットし、もう一度「ここね?」と確認した。私は軽く頷き、拳に力を込めた。すでに手は汗ばんでいて、ぬるぬるした感触が気持ち悪かった。シバさんはピアッサーを縦にして先端をタオルに押しつけた。そろりと舌を挟み、舌の裏に冷たい金属が当たった。
「オッケー?」
シバさんは優しい声で聞き、上目遣いで軽く頷くと、いくよ、小さい声で言って指を引き金に賭けた。その声でシバさんがセックスしてる所が頭に浮かんだ。セックスしてる時もあんな小さい声でGOサインを出すのだろか。ガチャ、という音と共に、全身に戦慄が走った。イク時なんかよりもずっと強烈な戦慄に、私は鳥肌を立ててヒクッと短い痙攣した。
胃に力が入り、それと共に何故か膣にも力が入った。エクスタシーと同じように、陰部全体が痺れた。バシッという音と共にピアスはピアッサーから離れ、自由になった私は顔を歪めて舌を口の中に戻した。
「みして」
シバさんは私の顔を自分の方に向かせて自分の舌を出して見せた。私は少し涙目になりながら感覚のない舌を突き出した。
「うーん、オッケーだね。真っ直ぐに入ってるし、位置もばっちり」
「ほんとだ。ルイ、良かったじゃん」
アマが割り込んできて、私の舌をジロジロ見た。私は舌がじんじんしていて喋るのも億劫だった。
「ルイちゃん、だっけ? 痛いの強いんだね。女の方が耐えられるんだってね、こういうの。舌とか性器とか、粘膜に開けると失神する人とかいるんだよ」
私は頷いて、表情だけでそうなんだ、と答えた。鈍い痛みと鋭い痛みが短い間隔で交互に襲ってくる。でも、ここに来て良かったと思った。最初は自分で開けようと思っていたけど、アキの言うことを聞いて良かった。自分だったらきっと途中で断念していただろう。
その後氷を貰い、舌を冷やした。興奮が少しずつ治まっていくのが分かった。落ち着くと店内に戻ってアマと二人でピアスを物色した。アマはピアスに飽きるとSMグッズのコーナーをうろつき、私は奥の部屋から出てきたシバさんを見つけ、カウンターに寄りかかった。
「シバさんはスプリットタン、どう思います?」
シバさんは、ん? と言って首をひねった。
「ピアスは刺青と違って、形を変えるもんだからね。おもしろい発想だと思うけど、俺はやりたいとは思わないね。俺は、人の形を変えるのは、神だけに与えられた特権だと思ってるから」
シバさんの言葉は、何故かすごく説得力があって、私は大きく頷いた、私は自分が知っている限りの身体改造を頭に浮かべた。纏足(てんそく)、ウェストンのコルセットでの矯正、あと首長族なんてのもあった。歯の矯正なんてのも、改造だろうか。
「じゃあ、シバさんが神だったらどんな人間を作ります?」
「形は変えないよ。ただ、バカな人間を作る。ニワトリみたいなに、バカなのを。神の存在なんて考えつく事のないように」
私は少しだけ目を上げてシバさんを見た。シバさんはサラッと言ったけど、目はいやらしく笑っていた。おもしろい男だと、私は思った。
「今度、刺青のデザイン見せてもらっていいですか?」
シバさんはニッコリしていいよ、と優しい目で言った。シパさんの目は不自然なほど茶色く、白い肌といい、白人並に色素の薄い人なんだなと思った。
「良かったら電話して。ピアスの事も、訊きたいことがあったらいつでもいいよ」
シバさんはそう言ってお店の名刺の裏に携帯電話の番号を書いて私に手渡した。私はそれを受け取るとありがとう、と微笑み、まだムチを手にとって物色しているアマにチラリと目をやって、財布に押し込んだ。
「あ、お金」
「財布で思い出して「いくら?」と聞くとシバさんは「いいよ」と興味なさそうに言った。私はカウンターに肘をつき、手に顎を載せてシバさんを観察した。カウンターの中の椅子に座っているシバさんは私の視線をうざったそうにかわし、ずっと目を合わせなかった。
「なあ、俺はお前の顔を見てるとSの血が騒ぐんだ」
おもむろに、シバさんが目を合わせないまま言った。
「私Mだから。オーラ出てんのかな」
シバさんは腰を上げ、やっと私の目を見た。カウンターの向こうから私を覗き込むシバさんは、子犬でも見るような愛おしい目をしていた。私の目の高さに合わせて腰をかがめると細い指で私の顎をぐいと持ち上げ、微笑んだ。
「この首、ニードルで刺してぇ」
彼は今にも声を上げて笑いだしそうな顔でそう言った。
「それってSavageのSじゃないの?」
「ああ、確かに」
何それ、と返されるだろうとおもっていたら、少し驚いてシバさんを見つめ返した。
「知らないと思った」
「俺、残酷な言葉は詳しいの」
そう言うとシバさんは唇の片端だけ上げて恥ずかしそうに笑った。狂ってる‥‥という思いの中、この男になぶられたいという欲求だけは否めなかった。腕をカウンターに置き顎を上に向けた私の首を、シバさんは撫でまわした。
「ちょっとお、シバさん。人の女に手ぇ出さないでくださいよ」
私たちの視姦を遮ったのはアマの間抜けな声。
「ん? 肌見てたんだよ。彫る時の参考に」
シバさんの言葉にアマはそっか、と顔の筋肉を緩めた。私とアマはいくつかピアスを買い、シバさんに見送られて店を出た。
アマと一緒に外を歩くのも、段々慣れてきた。アマは左眉に三本4Gの針型のピアスを刺し、下唇にも同じように三本同じピアスを刺している。それだけでも目立つというのにタンクトップからは龍が飛び出し、真っ赤な髪はサイドが短く刈り込まれていて、太いモヒカンみたいな形。あの暗いテクノしかかけないクラブでアマを見て、はっきり言って私は引いていた。
私はそれまでヒップホップとトランスをかけているクラブにしか行ったことが無かった。ほとんどが友達付き合いのイベントだったけど、クラブなんてどこも同じようなもんだと思っていた。あの日、私は友だちと遊んだ帰りになまった英語を話す黒人に声を掛けられ、あのクラブに連れていかれた。
クラブはクラブ違い。知らない曲ばかり流れるブースに嫌気がさしてカウンターで飲んでいると、そこから妙な踊り方をするアマが目に入った。異質な客の中でも際立っていた彼は、私と目が合うとつかつかと歩み寄って来た。こういう人種もナンパするんだ、と少し驚いた。
他愛もない話の後、私は彼の舌に見せられた。そう、私は彼の二手に分かれる細い舌に魅せられた。どうして強く惹きつけられたのか、未だに分からない。私はこの意味のない身体改造とやらに、一体何を見出そうとしてるんだろう。
舌のピアスを指でつついてみた。たまに、口の中でピアスが歯に当たりカチ、と音をたてる。痛みはあるけど、痺れは大分治まってきた。
「ルイ、スプリットタンに一歩近づいてきた感想は?」
不意にアマが振り返ってそう言った。
「よく分からない。でも嬉しい気がする」
「そうか、良かった。俺は、お前と気持ちを共有したいんだよ」
アマはそう言って、だらしなく笑った。どこがだらしないのか分からないけど、アマは笑うとだらしない顔になる。口を開けると下唇のピアスの刺さった部分がダラッと下がるかもしれない。私の中でアマみたいな、パンクな人のイメージはいつもマリファナ吸って乱交してるって感じだったけど、意外とそうでもない人もいるらしい。
アマはいつも優しくて、ガラにもなくくさいセリフを吐いたりする。全く、似合わないにも程がある。アマは部屋に帰ると呆れるくらい長いディーブキッスをして、あの蛇舌で私の舌のピアスを舐め回した。じんじんと体の芯を震えさせる痛みが、もうすでに心地よかった。
アマとセックスしながら、目を閉じてシバさんの事を思い出した。
神の特権‥‥上等だ。私が神になってやる。喘ぎ声が冷たい空間に響く。夏で、エアコンも効いていなくて、私の体は汗ばんでいるというのに、何故かアマの部屋は冷たい。
「イッていい?」
アマの苦しそうな声がだらしなく宙を舞う。私はうっすら目を開けて、小さく頷いた。アマは引き抜くと、私の陰部に放出した。まただ‥‥。
「ちょっと、お腹に出してって言ってるじゃない」
「ごめん、ちょっとタイミングが‥‥」
アマは申し訳なさそうに言ってティッシュを引き寄せた。アマはいつも私の性器に射精する。何が嫌って、毛がバリバリになる事。そのまま余韻に浸って寝てしまいたいのに、アマのせいでいつもシャワーを浴びる事になる。
『広告 挿入避妊具なら小さいチンコ、ユルユル膣であっても相手に満足させ心地よくイカせられる』
「お腹に出せないんだったゴム使ってよ」
アマは俯いてもう一度ごめん、と言った。私はティッシュで軽く拭き取ると立ち上がった。
「シャワー、浴びるの?」
アマの声があまりにも寂しそうで思わず足が止まった。
「浴びる」
「俺も一緒に入っていい?」
思わずいい、と言いかけたけど、全裸のまま情けない顔をしているアマを見てバカらしくなった。
「狭い風呂に二人で入るなんて嫌よ」
私はバスタオルを取ると風呂場に入り、鍵を閉めた。洗面台の鏡に向かって舌を出してみた。舌の先には銀の玉が付いている。これが、スプリットタンへの第一歩だ。一カ月位は拡張しないように。とシバさんは言っていた。道は、まだまだ遠い。
風呂を出るとアマは黙ったままコーヒーを差し出した。
「ありがう」
そう言うとアマは顔をほころばせ、コーヒーを飲む私をじっと見ていた。
「ルイ、布団に入ろう」
言われるままに並んで布団に入ると、アマは私の胸に顔を埋めて乳首を口に含んだ。アマはこれが大好きで、セックスの前も後もこれを欠かさない。スプリットタンだからだろうか、アマの愛撫は気持ちいい。安心しきったアマの顔は本当に赤ちゃんみたいで、こんな私でもほんの少し母性本能が働く。身体を撫でてやるとアマは上目遣いで私を見て、幸せそうな笑みを浮かべた。それを見たら、私も少しだけ幸せな気分になった。パンクなくせに、癒し系。アマはよく分からない男だ。
「えっ? うそっ? ちょーいたそー」
友達のマキの反応はこんなもん。まじまじと私の舌を見て、いーたっそー、と連呼して顔を歪めている。
「どういう心境の変化なの? 舌ピなんてさ。ルイ、パンクとか原宿系とか嫌いじゃん」
マキは二年前にクラブで知り合った。コテコテのギャル。ずっと仲良しで、いつも一緒に遊んでるから、私の趣味をよく分かっている。
「うん、ちょっとパンクな人と知り合ってさ。影響受けたというか。なんつーか」
「でもギャルが舌ピっつーのも珍しいよね。耳のピアスの穴でかくしたと思ったら次は舌かあ、ルイ、このままパンクに走っちゃうんじゃないのぉ?」
ギャルじゃないって、という私の言葉にも耳を貸さずマキはあーだこーだとパンク批判を口走り続けた。確かに、キャミソールワンピースに、金の巻き毛で、舌ピは変だろう。でも私がやりたいのは舌ピじゃない、スプリットタンだ。
「マキ、スミってどう思う?」
「スミって刺青? 刺青はいーんじゃない? 薔薇とか、蝶とか可愛いんじゃん」
ニコニコしてそう答えるマキ。
「そうじゃなくて、龍とかトラ、バクとか浮世絵とか、可愛くないやつ」
マキは顔を曇らせて、はぁ? と大きな声を出して、どーしちゃったのよ? と私に詰め寄った。
「その知り合ったパンクな人にやれって言われたの? その人と付き合ってんの? ルイ、もしかしてその人に洗脳されちゃったんじゃないの?」
洗脳、そうかもしれない。初めてアマのスプリットタンを見た時、明らかに自分の中の価値観が音を立てて崩れるのが分かった。何がどう変わったのかは分からないけど、私は一瞬にしてあの舌に魅了された。でも魅了はされたけど、それで私もやりたいと思ったわけじゃない。どうしてこんなに血が騒ぐのか、その理由を知りたくて今スプリットタンに向かってひた走っているような気がする。
「そうだ、マキ会ってみる?」
二時間後、私たちは待ち合わせ場所で落ち合った。
「あ、アマ」
「手を振る私の視線の先を見て目を丸くしているマキ。
「うそ、まじで?」
「うん、あの赤毛ザル」
「うそ、まじで? あたし怖いよ」
明らかに引いているマキに気づいて。アマは申し訳なさそうにおずおずと私たちに近づいた。
「何か、怖くしてごめんね」
アマはマキに訳の分からない謝罪をし、マキはその言葉に大ウケし、私はマキの反応に安堵した。私たちは夜の繁華街を徘徊して、結局安いだけが取り柄の居酒屋に入った。
「何か、アマさんと歩いているとみんな道をあけるよね」
「ほんとだよ。アマと歩くとね、キャッチされないしティッシュももらえないんだから」
「じゃー俺って便利じゃん」
アマとマキはすぐに打ち解け。アマがスプリットタンを自慢すると。かっこいーじゃん、とマキは手のひら返してはしゃいだ。
「じゃあ。ルイもこれやるんだ」
「当たり、おそろにするの。ルイさあ、眉ピと口ピもしなよ。全部おそろにしようよ」
「やだよ、私がやりたいのは舌と刺青だけ」
「でも悪いけどルイをパンクな道に連れ込まないでくださいね。私とルイは二人で一生ギャル同盟組んでるんです」
「組んでいないし、ギャルじゃないし」
二人は「ギャルだし」と言って、何故か私に一気コールをかけた。
三人でペロベロに酔っぱらって店を出ると、ギャーギャー騒ぎながら駅に向かって歩いた。もう店は閉まって、静まり返っているスカウト通りでたむろしている、見るからにチンピラかギャングみたいな男が二人、目に入った。例のごとく、アマをジロジロ見ている。アマはしょっちゅうガラの悪い奴らに絡まれてている。ガンくれただけの、ぶつかったただの、いちゃもんつけられて。でもアマはいつもヘラヘラ笑って「ごめんね」と言うだけだ。パンクはパンクでも、中身はただのヘタレだ。
「おねーえちゃん、そいつ彼氏?」
片方のベルサーチの服を着た男が私に歩み寄って来て、ちゃかすように言った。マキは私たちの後ろに隠れて目を合わせないようにしているし、アマは男を睨みつけるだけだし、どいつもこいつも役に立たない。シカトして通り過ぎようとすると、男は「違うよね?」と言って私の前に立ちはだかった。
「私とこいつがヤッてるとこ、想像できないの?」
無表情のまま小首をかしげると、男は私の肩を抱き、できないよー、と言って無造作に私のワンピースの胸元に手を掛けた。今日、何色のブラジャーしてたっけ? と考えた瞬間。ゴッという音と共に私の視界からワンピースの中を覗き込んでいた男が消えた。一瞬訳が分からず、ぐるりと一周見渡した。男が道端に倒れていて、アマの目が血走っていた。なるほど、アマが男を殴ったわけね。
「てめー何するんだこら」
そう怒鳴ったもう一人のツレがアマに殴りかかる。アマはそいつにも鉄拳をくらわし、まだ倒れたままの男に馬乗りになって仰向けにさせるとこめかみの辺りを何度も殴りつけた。どろっとした血が流れるのが見えた。男は気を失っていて動きもしない。
「ひぃっ」
マキが血を見て悲鳴をあげる。
「あ‥‥」
そうだ。私はふと思い出す。アマのお気に入りのシルバーリング、今日も右手の人差し指と中指に嵌めていた。鈍い音の正体が分かって、全身に冷や汗がにじんだ。ゴッ‥‥ゴッ‥‥TEL・骨と銀がぶつかる音。
「アマ、もういいでしょ」
アマは無言のまま、私の声が聞こえているのかいないのか。また拳を男のこめかみに叩きつける。アマが一発加えたもう一人の男が起き上がってじりじりと逃げていく。まずい、警察呼ばれる。私は思わず声を荒げる。
「いい加減にしろよ」
私がそう言ってアマの肩をつかむと同時に、アマの拳が男の顔面に振り下ろされた。思わず、目を伏せた。マキが嗚咽している。
「アマ!」
怒鳴ると、アマはようやく体の力を抜いた。正気に戻ったかとホッと息をついた私の目に映ったのは、男の口の中をまさぐるアマの指。
「何してんだよこの野郎!」
私はアマの頭を引っぱたいてタンクトップを引っ張った。その時、微かにサイレンの音が聞こえた。
「マキ、あんた逃げな。早く」
マキは真っ青な顔で頷くと「今度また三人で遊ぼうーね」と言って手を振った。マキは、意外とタフだ。酔っている割にはなかなかの走りでその場を去った。フラフラしているアマは虚ろな目で私を見つめたまま。
「ほら、ねえ分かってよ。アマ、警察呼ばれたんだよ。逃げるんだよ」
肩を叩くとアマはいつものようにだらしなく笑って、やっと走り出した。アマは思いのほか逃げ足が速く。私はぜいぜい言いながら手を引かれて走った。細い路地裏で、私たちはやっと足を止めた。アマの後ろで、私はへたり込んだ。
「何やってんだよ馬鹿野郎―」
絞り出すように言った私の言葉は、自分でも驚くくらい情けなかった。アマは私の隣にしゃがみ込むと血まみれの右手を出し、拳を開いた、そこには一センチ程の赤い物体が二つ。すぐに、あの男の歯だと分かった。背中に一滴冷水を垂らされたような感覚が、私の全身の毛という毛を逆立てた。
「ルイの仇、取ってやった」
そう言って勝ち誇ったような笑みを浮かべるアマ。何により恐ろしかったのは、その笑みが少年のように無邪気だった事。大体仇って言われても…‥、私は殺された訳じゃない。
「んなもんいらねーよー」
そうシカトする私の腕を取り。アマは二本の歯を私の手の平にコロッと落とした。
「これも一応、俺の愛の証」
私は呆れて、口を開けたまま肩をすくめた。
「日本じゃそんな愛の証は通用しないわよ」
私は寄り添って来るアマの頭をぐしゃぐしゃと撫でてやった。
それから私たちはトロトロと公園まで歩き、アマは水道でタンクトップと手を洗って、何事もなかったように終電でアマの家まで帰った。部屋に入ってすぐアマを風呂場に押し込むと、捨てる事も出来ず化粧ポーチに放り込んだ二本の歯を手に載せて観察した。キッチンの水で歯に付いた血を洗い流すと、また化粧ポーチに押し込んだ。もしかしたら私は相当厄介な男に関わってしまったのかもしれない。アマは完全に私と付き合っていると思っているようだし、もし別れを切り出して逆上されたら殺されるかもしれない。アマは風呂から出てくると私の隣に座り、窺うような目でこちらを見て、私が黙ったままでいるとボソッとごめんね、と呟いた。
「コントロール出来ないんだよ。俺って結構温厚な方だと思うんだけど、一回殺してやる、って思っちゃうと本当に殺すまでやらなきゃ、って気になっちゃうんだ」
こいつは人を殺した事あるんじゃないかと思った。
「アマ、あんたもう成人してるんだから、人殺ししたら実刑なんだよ。分かってるの?」
「いや、俺まだ未成年だけど?」
アマは真面目な顔でそう言って、まじまじと私を見た。私はそんなアマに呆れて、心配しているのがバカらしくなった。
「バカじゃないの?」
「本当だよ」
「だって会った時二十四って言ったじゃない」
「いや、ルイがその位かと思って合わせてみた。ガキだと思われたくなかったし。ああ、何か軽いトーンでカミングアウトしちゃったね。もっと真剣に言うべきだった? そういや、ルイって幾つなの?」
「あんたね、失礼にも程があるわよ。私だって未成年よ」
「うそっ?」
短くそう叫んで目を丸くするアマ。
「まじで? 俺何かすごく嬉しいや」
そう言って満面の笑みで私を抱きしめるアマ。
「まあ、お互い老けているって事だな」
私はそう言ってアマを突き放した。そう言えば、私たちはお互いの事をほとんど知らない。お互い、生い立ちや歳の事も、避けていた訳ではなくてただ話題に上がらなかった。結局私たちは未成年だということだけ知ったけども、やっぱりそこから、じゃあ幾つなの? という話にならなかった。
「ねえアマ、あんた名前何ていうの? 天野? スアマ?」
「何だよスアマって。俺のアマはね、アマデウスのアマなの。アマが名字でデウスが名前ね。ゼウスみたいでかっこいいでしょ?」
「ふうん、まあ言いたくないならいいけど」
「本当だってば。ルイは?」
「あんたはどうせルイ十四世のルイだと思ってんでしょ。私はルイ・ヴィトンのルイよ」
「あっそう。随分お高い女だな」
私たちはその後もくだらない事ばかり話して、ビールを片手に明け方まで語っていた。
次の日の昼過ぎ、私はDesireでシバさんと刺青のデザイン画を見ていた。その筋の人が入れるような浮世絵から、ドクロや初期のミッキーマウス等の洋画まで、様々なデザイン画が気が遠くなるほどファイルされていて、私はシバさんのマルチな画力に啞然とした。
「お前、龍がいいの?」
何十枚もある龍のページにじっくり目を通しているとシバさんが身を乗り出してファイルを覗き込んだ。
「うん、やっぱり龍かなあ。これアマのやつじゃない?」
「ああ、そう。少し形は違うけどそのデザインだよ」
シバさんはカウンターに寄りかかって、椅子に座ったままファイルに目を通している私を見下ろした。
「なあ、アマ知らないんだろう? お前がここに来るって事」
目を上げるとシバさんはうっすら笑みを浮かべていやらしい目で私を見た。知らないよ」
そう言うとシバさん少し真面目な顔で、俺が携帯の番号教えたの、あいつに言うなよ、と言った。その言葉でシバさんがアマのあの気質を知っているんだと分かった。
「ねえ、アマってさ‥‥」
私はそこまで言って口を噤んだ。
「知りたい? あいつのこと」
シバさんは一瞬おどけたように宙を見上げてから私を見つめ、首を傾げて言った。
「ん、やっぱいいや。知りたくないかも」
そ、シバさんは興味なさそうに言うとカウンターを出て、店を出た。十秒もしない内にドアが開いてシバさんは戻った。
「何? どうしたの?」
「大事なお客様が来たから閉店しといた」
そ、私は興味なさそうに言ってまたファイルに目を落とした。それから、私たちは奥の部屋でデザインの打ち合わせを始めた。シバさんは驚くくらい素早く綺麗な絵を描いていく。そういうアーティステイックな血がまるで通っていない私は羨ましい限りだ。
「でもね、はっきり言って迷ってるんだよね。スミって一生モンでしょ。入れるからには最高の絵を入れたいし」
私は頬杖をついてシバさんが描いた龍を指でなぞった。
「そりゃ、そうだよな。今はレーザーで取ることは出来るけど、基本的に取り返しつかないからね。ま、俺の場合、これは髪伸ばせば見えなくなるけど」
シバさんそう言ってツルツルの頭に舞う龍を撫でた。
「そこだけじゃないんでしょ?」
そう聞くとシバさんは見たい? と言ってニヤッと笑った。私が軽く頷くと、シバさんは長袖のTシャツに手を掛けた。シバさんの体はキャンパスのようにカラフルな画が所狭しと描かれていた。背中には龍、猪、鹿、蝶、牡丹や桜や松。
「猪鹿蝶だ」
「そう。俺、花札とか好きなの」
「でも萩と紅葉入ってないんじゃん」
「ああ、場所がなかったから諦めたんだよ」
ふうん、なかなか適当なもんだな。そして、シバさんが私の方に向き直った瞬間、一匹の動物が目に入った。
「これ、麒麟?」
シバさんの右の二の腕に彫ってある一角獣に、私の目は釘付けになった。
「ああ、知っている? こいつはね、俺の一番のお気に入りなんだ。聖なる生き物なんだよ。生草は踏まず、生物を食わず。言ってみりゃ動物界の神だな」
「麒麟って一角獣だっけ?」
「ああ、これはねえ、中国人の想像の産物だから、中国では、麒麟には肉に包まれた一本の角があるって言われているんだ」
「私これがいい」
腕を眺めながら呟いていた。シバさんは一瞬言葉を失って俯いた。
「これ彫ったの、日本でトップクラスの彫り師なんだ。俺、麒麟彫ったことないし」
「その彫り師に彫ってもらえない?」
「その人、死んだんだ」
シバさんはそう言うと顔を上げた私の目を真っ直ぐみつめた。軽く息を吐くとアメリカ人のように肩をすくめて口を開いた。
「麒麟のデザイン画抱いて焼身自殺したんだ。芥川龍之介の世界でしょ。多分、麒麟が怒ったんだよ、神聖な麒麟を勝手に彫ったから。麒麟彫ったら呪われるかも知んねーぞ」
シバさんはちゃかすように言って、自分の腕の麒麟を撫でた。私はどうしても諦めきれず、シバさんの麒麟をじっと見ている事しか出来なかった。
「しかもお前、麒麟って鹿と牛とかオオカミとか、色んな動物の集合体なんだぞ。描くのだってめんどうくせーんだからな」
「これがいいの。シバさん、お願い」
「…‥」
「お願い。デザインだけでも描いてみて」
シバさんはチッと舌打ちして苛立ったような顔で私を見た。そして小さい声で仕方ないねーな、と呟いた。
「やった。ありがとうシバさん」
「とりあえず、デザインだけ描いてみる、何か、背景とかリクエストある?」
私はしばらく考えて、またさっき見ていたファイルをめくった。
「これ、アマの龍と組み合わせて欲しいの」
シバさんはしばらく龍のデザインを見つめ「なるほどね」、と独り言のように呟いた。
「麒麟彫るの初めてだし、何かとコラボレーションした方が気が楽ではあるね。いいね、今流行のコラボレーション」
私は一笑して「そうだね」と言った。
「アマのと同じくらいの大きさで、背中に収めて欲しいの。幾らくらいかかる?」
シバさんはうーん、宙を見上げ、エッチ一回、と言って私を横目で見た。
「そんなんでいいんだ」
横目で見返すシバさんはS丸出しのやらしい目つきで私を睨んだ。
「服脱げよ」
というシバさんの言葉に、私は立ち上がる。ノースリーブのワンピースは汗ばんでいる体に張り付いて、ジッパーを下げると少し冷たい空気が入った。ワンピースを床に落とすと、シバさんは興味なさそうな目で私の体を一瞥した。
「お前、細いなあ。彫った後に太ると皮が張ってかっこ悪いぞ」
ブラジャーとパンツも、脱ぐと汗で湿っていた。ミュールを脱ぎ、寝台に腰を下ろした。
「大丈夫。もう何年も体重は変わっていないし」
シバさんはタバコを灰皿に押し付けるとベルトを外しながら寝台に歩み寄った。寝台の脇で立ち止まると、シバさんは片手で乱暴に押し倒し、私の首に手の平を押しつけた。指は頸動脈をなぞり、次第に力がこもっていった。シバさんの細い指が私の肉に食い込んでいく。立ったまま、私を見下ろしているシバさんの右腕に血管が浮き出ているのが見えた。私の体は酸素を欲しがり、所々短く痙攣した。喉が音をたて、私の顔は歪みだす。
「いいね。お前の苦しそうな顔。すげえ勃つよ」
シバさんは無造作に手を放し、パンツとトランクスを脱いだ。寝台に上がり、まだ意識が朦朧(もうろう)としている私の肩の上に膝をつき、チンコを差し出す。シバさんの両脚には龍が一匹ずつ泳いでいた。私は無意識のうちにチンコを手に咥えていた。酸っぱい匂いが口の中に広がった。
春夏秋冬の中で夏のセックスが一番好きなのは、この汗とアンモニアの混ざった匂いが好きだから、というのもある。シバさんは私を無表情のまま見下ろし、私の髪を鷲掴みにして引っ張った。顎をガクガクと前後運動させていると、濡れてくるのが分かった。どこを触られた訳でないのに濡れるなんて、便利なもんだ。
「なあ、アマってどんなセックスすんの?」
シバさんはそう言って腰を上げた。
「ん? ノーマルだけど?」
ふうん、と頷きながらシバさんは自分のベルトをパンツから引き抜いて、私の手首を後ろで縛った。
「欲求不満になんない?」
「別に。私はノーマルでもイケるくちだから」
「何? 俺はノーマルでイケないくちだと思う?」
「イケるの?」
「イケない」
「マッドなサディストだもんね」
「でも俺、男でもイケるよ。結構広範囲でイケる方だと思うけど」
シバさんが笑って言った。その言葉で、アマとシバさんがヤッているところを想像してみた。案外、美しいかもしれない。シバさんは細い腕で私をひょいと持ち上げ、寝台から下ろし、寝台に腰を下ろすと右足を私の前に出した。私は親指から小指まで丹念に吸い、口の中がカラカラになるまで足を嘗め続けた。手が付けず這いつくばっていたから、首が痛くなった。シバさんはまた私の髪をつかんで、上を向かせた。多分私は虚ろな目をしてたんだと思う。シバさんのチンコには血管が浮き立っていた。
「濡れてんの?」
小さく首を縦に振ると、シバさんはまた私を抱き上げ寝台に座らせた。私は無意識に脚を開いていた。軽い緊張が私を包む。Sの人を相手にする時、いつもこの瞬間私は身を硬くする。何をするのか分からないからだ。浣腸だったらいい、おもちゃもいいし、スパンキングも、アナルもいい。でも、出来るだけ血は見たくない。昔、膣にファイブミニの瓶を入れられ、危うくトンカチで割られそうになった事があった。あと、針で刺す人も苦手。
手首から手の平がじっとりしていて、肩から二の腕にかけては鳥肌が立っていた。シバさんは、物を使う気はないらしく、私はホッとした。シバさんは指を二本入れ、何度かピストンさせると引き抜き、汚いものを触ったように私の太股に濡れた指をなすりつけた。シバさんの表情を見て、また濡れていくのが分かった。
「入れて」
そう言うとシバさんは太股で拭った指を私の口に押込み、口の中をまさぐった。
「不味いか?」
シバさんの言葉に頷くと口から指を引き抜き、そのままマンコに入れ。また口の中に戻し、口の中をまさぐった。チンピラの口の中を探るアマの姿がフラッシュバックした。
「苦しいか?」
同じようにまた頷くとシバさんは指を抜き、私の頭に手を当てて荒々しくシーツに押し付けた。顔と肩と膝で体を支えると、下半身がガクガクした。
「お願い、早くいれて」
うっせーな、シバさんはそう吐き捨てて私の髪を掴み、枕に押し付けた。シバさんは私の腰を高く上げるとマンコに唾を吐き、また指で中をグチャッとかき混ぜるとやっとチンコを入れた。初めからガンガン奥まで突かれ、私の喘ぎ声は泣き声のように響いた。気づくと本当に涙が流れていた。
私は気持ちいいとすぐに涙が出る。満たされていくのが分かった。シバさんは突きながら私の手首を縛っていたベルトを外し、私の手が自由になると勢い良くチンコを抜いた。抜かれた瞬間、また一筋涙がこぼれた。シバさんは私を上に乗せ、私の腰を掴んで揺さぶった。マンコ一帯がシバさんの肌と擦れて痺れていた。
「もっと泣けよ」
シバさんの言葉に、また涙が伝わった。私は短く「イク」と呟き腰がガクガクと震わせた。イッた後、満足に動けないでいるとシバさんはめんどくさそうに私を押し倒し、上になった。シバさんは深く、強くピストンして私の髪を掴んだり、首を絞めたりしてひとしきり私の苦しむ顔を楽しむと「いくよ」と言った。あのピアッサーを持って言った時と同じだった。
短く、抑揚のない声。ぐっと深く入れて、引き抜き、私の口の中に射精した。その終わりは地獄からの解放のようでも、天国からの追放のようでもあった。シバさんはすぐに寝台から降りて。ティッシュでチンコを拭くとトランスを穿いた。私は投げられたティッシュの箱をキャッチし、鏡を見ながら精子を拭きとった。涙でメイクもはげかけていた。
私たちは寝台の上に座って壁に背をもたせかけ、宙を見つめてぼんやりタバコを吸った。「灰皿取って」とか「暑いね」とか何でもない言葉を交わし、しばらくそのまま何もせずに座っていた。やっと立ち上がるとシバさんは振り返り、蔑(さげす)むような目で私を見た。
「お前、アマと別れたら俺の女になれよ」
私は思わずその言葉に吹き出した。
「シバさんの女になったら殺されそう」
シバさんは表情を変えずに口を開いた。
「それはアマだって同じだろう」
私は一瞬言葉を失った」
「付き合うんだったら、結婚を前提にな」
シバさんそう言ってブラジャーとパンツを私に投げた。パンツを穿きながらシバさんとの結婚生活を想像してみた。きっとサバイバルな生活なるだろう。ワンピースを着て寝台を降りると、シバさんは小さな冷蔵庫から出したばかりの缶コーヒーを開けて差し出した。
「優しいだね」
「お前の爪が異様になげぇから開けてやったんだよ」
ふてぶてしくそう言うシバさんに私は素早くキスをした。
「ありがとう」
このダークな部屋に不釣り合い極まりない感謝の言葉が、行く当てのなく宙に舞った。私たちは店内に戻って、シバさんは店を開けた。
「でもこの店はほんと客来ないよね」
「ほとんどがピアスか刺青なんだよ。だから大体予約してくんの。こんな店にフラッと立ち寄る奴いないだろ」
「なるほどねー」
カウンターの中の椅子に腰を下ろし、舌をベロッと出した。ピアスを指で確認してみる。もう痛くない。
「ねえ、もう12入れてもいいかな?」
「まだだよ。一カ月くらいつけときな。だからファーストピアス12にしときゃ良かったのに‥‥」
シバさんは素っ気なく言ってアロアーの方からカウンター内を覗き込んだ。
「デザイン、出来たら連絡してくれる?」
「電話は、日中にお願いね。アマがバイトの時間に」
はいはい、と言ってラックの整理に戻るシバさん。帰ろうかとバッグに手を掛けた瞬間、シバさんが振り向く。私は思わずピタッと止まって何? と目で問いかけた。
無表情で、シュールギャグをかますシバさん。
「カミノコ? 何かノコギリみたい」
「人間に命を与えるなんて、神は絶対サディストだ」
「マリア様はMだった?」
もちろん、シバさんは呟いてまたラックに向き直った。私はバッグを持ってカウンターを出た。
「飯とか、食ってかねー?」
「もうアマが帰って来ちゃうもん」
「そ。じゃあまたな」
シバさんはそう言って乱暴に私の頭を撫でた。私はシバさんの右腕を取り、麒麟の場所を撫でた。
「かっこいいの、描いてやるよ」
シバさんの言葉に笑顔で応えると、私は小さく手を振って踵(きびす)を返した。店をでるともう外は陽が傾きかけていた。空気が爽やかで。むせかえりそうだった。電車に乗って、アマの家に向かう。駅から家までの道、家族連れが多い商店街で、うるさい人々の声に吐き気を覚えた。
ゆっくりと歩く私の足に、子供がぶつかった。私の顔を見て、素知らぬ顔をするその子の母親。私を見上げて泣き出しそうな顔をする子供。舌打ちをして先を急いだ。こんな世界にいたくないと、強く思った。とことん、暗い世界で身を燃やしたい、とも思った。
アマの部屋に帰るとすぐに服を洗濯機に入れて回した。Desireはいつも甘ったるいお香の匂いがする。きっと服にも匂いが付いているだろう。それからバスルームに入ると丹念に全身を洗った。部屋に戻るとデニムのパンツにアマのTシャツを着た。さっと薄く化粧をして、髪の毛を乾かした。洗い終わったワンピースを外に干し、やっと一息ついた所でガチャン、という音と共にアマが帰って来た。
「おかえり」
アマは満面の笑みで、私はホッとした。
「今日は一日中眠かったよ」
欠伸をしながらアマが言う。当然だ、朝方まで飲んでいのだから。私だってヘロヘロだ。今朝、アマを送り出した後、私は何故か寝付けずにシバさんに電話をした。いってみれば私の意志通りの、意外性の欠片もない一日だった。ただ一つ、今日という日のおまけに麒麟が私の体に住み着く日が待ち遠しい。
アマがアマデウスで、シバさんが神の子なら、私はただの一般人で構わない。ただ、とにかく日の光が届かない、アンダーグラウンドの住人でいたい。子供の笑い声や愛のセレナーデが届かない場所はないのだろうか。
私たちは居酒屋で夕飯を食べ、部屋に戻るとノーマルのセックスをして、アマは気を失うようにして眠りにおちた。私はアマの寝顔を眺めながらビールを飲んだ。私がシバさんとセックスした事を知ったらアマはあの薄汚い男にしたように、私をたこ殴りにするだろうか。どちらかと言えば、私はアマデウスより神の子に殺されたい。でもきっと、神の子は人を殺さない。
ベッドからだらんと伸びているアマの手には、あのごついシルバーリングが光っていた。気を紛らわそうとテレビを点けたけど、くだらないバラエティやつまらないドキュメントばかりで、一通りチャンネルを回し、電源を切った。アマの部屋にある雑誌は男物のファッション誌ばかりだし、パソコンの使い方は分からない。私は舌打ちをして新聞を手に取った。下世話なスポーツ新聞だけど、一応これが私の社会の情報源。テレビ欄で深夜番組をチェックし、裏から目を通した。
この日本で毎日殺人が行われ、風俗業界も不景気だという事ぐらいしか、理解できないが、ふと小さな記事が目に留まった。『新宿の路上で二十九歳の暴力団員撲殺される』という見出しで昨日の男が思い出された。いや‥‥あの男はもっと歳がいっていたはずだ。あの顔で二十代なんて、私やアマ並みの老け顔だ。まあ、同じような事件が、同じ新宿で起こってんだろう。
フッと息をついて記事を読んだ。『被害者は搬送先の病院で死亡。犯人は逃亡中。目撃者の証言によると、男は二十代半ばで赤い髪。身長は175~180センチ、細身の男』そんな感じ。記事とアマを見比べて、新聞を閉じた。もしこれがアマの起こしたあの事件で、目撃者というのがあの男のツレだったとしたら、犯人の特徴はまず第一に顔面のピアスと刺青を挙げるはずではないのか?
分からないけど、きっとアマは大丈夫。そんな根拠のない自信があった。きっと、アマと同じような男が、二十九歳暴力団員を殺したんだ。アマが殴った男は、きっと生きている。そう強く思った。私はバッグをつかむと部屋を出て、早足でコンビニに向かった。ブリーチ剤とアッシュのヘアカラーを買って戻るとスヤスヤと寝息を立てているアマを叩き起こした。
「ん? ルイ、どーしたのぉ?」
間抜けな声を上げているアマの頭を引っぱたき、鏡前に座らせた。
「何っ? 何事?」
「何事? じゃないわよ。髪の色変えんの、前から気になっていたのよ、その気色悪い赤毛」
アマは訳が分からない顔のまま私に言われるがままに服を脱ぎ、トランクス一枚になった。
「大体さあ、黒い肌に赤って汚いのよ。アマはね、センスなさすぎ」
ブリーチ剤を混ぜながら強烈な匂いに顔をしかめていると、アマは何故か満面の笑みを浮かべていた。
「ルイって優しいんだね。俺、もっとセンス磨くから、ルイも手助けしてね」
アマはポジティブな解釈をしてくれたようだ。きっとアマは幸せ者だ。私は「はいはい」、と流してブリーチ剤をブロッキングした髪に塗り始めた、髪の色を変えたからってどうにもなるもんじゃないけど、変えられるところは変えたほうがいいと思った。私はブリーチ剤を半分に分けて使った。
一度髪を流し、ドライヤーで乾かすともう既に赤色は抜けて金になっていたけど赤からアッシュとか、反対の色を入れる時には念を入れて丹念に色を落とした方がいいと、昔美容師さんから聞いた。残りのブリーチ剤を混ぜ、もう一度さっきと同じ工程を繰り返すとアマの髪はほぼ白に近い金になっていた。
ドライヤーでパリパリに乾かし、アッシュのカラー剤を塗り込んだ。アマの眠気はマックスらしく、ずっとうとうとしていた。さすがに可哀想に思ったけど、これも一応アマの事を思ってやっているんだと思い直した。カラーを塗り終えて頭にラップを巻くとアマは虚ろな目で私に笑いかけた。
「ルイ、ありがとね」
新聞を見せた方がいいとのかどうか考えたけど、私は黙ったまま手を洗いにバスルームに向かった。
「アッシュだったら少しはかっこよく見えるかな?」
「別に、かっこわるいとか言った訳じゃないでしょ」
そう言って洗面所から顔を出すとアマは笑った。
「俺、ルイのためだったら坊主なしてもいいよ。服も、ルイに合わせてギャル男っぽくしてもいいよ。美白しろって言うならするよ」
「勘弁してよ」
アマは別にかっこ悪い訳ではない。目つきは悪いけど、むしろかっこいい部類に入る方だと思う。ただ刺青と顔面のピアスが、かっこいいとか悪いとかの問題じゃなくしている。きっと他人として街で見かけたらもったいない‥‥と思うだろう。でも今はアマの気持ちが分かる。私は今、外見で判断される事を望んでいる。陽が差さない場所がこの世にないのなら自分自身を影にしてしまう方法はないかと、模索している。
カラーを入れて十分もするとアマはそわそわし始め「まだ? まだ?」と何度も聞いた。気持ちは分からないでもないけど、私は少しでも赤みを落とそうと躍起になっていた。結局私は三十分以上も放置させ、ラップを取ると無造作に髪の毛に手ぐしを入れてバサバサとかした。
「何してんの?」
「酸化させてんの。空気に触れさせると色が深く入るの」
ムラがないかチェックすると、もういいよ、と言ってバスタオルを手渡した。アマは「はーい」、と言って意気揚々とバスルームに向かった。アマが出て来るまで私はまたあの新聞の記事に目を通した。アマじゃない、アマのはずがない、自分にそう言い聞かせた。幾ら考えても答えは出なかった。
出てきたアマの髪を乾かしてセットしてやると、アマは鏡に向かって目をパチパチさせて微笑んだ。
「やめろよ、気色悪い‥‥」
私が呟くとアマはふくれ顔で振り返った。アマの髪は見事な灰色になっていた。灰そのものの色だった。あの赤毛の面影は、もう何処にもない。
「アマ、あんたに明日から長袖の着用を義務づける」
「何で? まだ暑いじゃん」
「うっさいな。タンクトップばっか着てっからギャングにしか見えねーんだよ」
そう言うとアマはしょんぼりして「はーい」と答えた。刺青は目立つ。もしかしたら、警察が捜査のために刺青の事を公表していなかったのかもしれない。私は気がおかしくなりそうな程、深読みと逆読みをして、ギャング系の服は着るなだの髪を伸ばせだの外で目立つなだのアマにきつく注意した。アマは私の剣幕にキョトーンとしつつも分かった。約束するもと言って私をきつく抱きしめた。
「ルイのためならお安いよ」
そう言って私をベッドに引きずり込むアマは、とても殺人犯になんか見えなかった。大丈夫、アマはいつも間抜けなバカ男で、私の隣で笑ってる。アマはベッドの中で私のキャミソールをたくし上げ、乳首を吸った。次第にその口が脱力し、そのままアマは寝息をたて始めると私はキャミソールを下ろし、電気を消して目を閉じた。闇の中で、私は懇願した、アマが捕まりませんように。誰に懇願したのか分からない。
でもたとえそれが神にでもあっても構わないとすら思った。深い眠りが、私を飲み込んでいくのが分かった。
次の日、ずっと休んでいたコンパニオンのバイトに出る事になった。昼過ぎ、電話の声で起こされ、欠員の穴埋めに入ってくれないか言われ、渋っていると三万円出すとマネージャーは太っ腹にもそう言った。アマと会ってから、アマの金で生活していたから、もうバイトも辞めてしまおうかと思っていた。
バイト代でおいしい酒でも飲みに行くか、と思い私は重い腰を上げた。コンパニオンのバイトは登録制プラス日払いという手軽さに後押しされて半年前に始めた。ホテルのイベントでお酒をついで回るだけにも関わらず、一パーティー大体二時間で一万円。ウケのいい顔に生まれて、良かった。
少し時間に遅れたけど、ホテルのロビーでマネージャーと女の子たちと落ち合った。マネージャーは私を見付けると顔をほころばせ、良かった、微笑んだ。控え室でそれぞれ着物を渡される。私は先ず自分で着つけが出来ない子の着つけを始めた。このバイトを始めて、見よう見まねで始めた着付けも、今ではそつなくこなせるようになっていた。
私は赤い派手な着物を渡され、自分で着付けをすると、持って来ていた茶色のストレートのウィッグをつけた。金髪で一流企業のパーティーのコンパニオンは出来ない。といって染めるのも嫌だった私はいつもウィッグを持参していた。ウィッグをアップにまとめているとマネージャーが声を掛けた。
「中沢さん」
久々に名字を呼ばれて、私にもそんな名前があったことを思い出す。
「あの、ピアス‥‥」
マネージャーは申し訳なさそうに言った。ああ、と呟いてピアスを触った。忘れる所だった。普通のピアスなら何も言われないけど、さすがに0Gにもなると着物には不釣り合いだし、一流企業には引かれる。五のピアスをすべて外すと、化粧ポーチに入れた。ちらっと二本の歯が見えた。もしもあの記事がアマの起こした事件だったとしたら、警察は男の歯が二本消えてることに気づいているのだろうか。
「中沢さん?」
またマネージャーの声がして、うんざりしながら、はい? と振り返った。マネージャーの顔に驚きの色が広がる。
「中沢さん、それピアス?」
すぐに、舌のピアスの事だと分かった。
「そうですよ」
マネージャーは困惑の表情を浮かべて「外せる?」と聞いた。
「あ、入れたばかりなんでまだ外したくないんですけど」
そう答えるとマネージャーは更に首をひねり「でも…」とか「うーん」とか言葉を濁した。
「大丈夫ですよ。大口開ける事はないですから」
にっこりして近づくと、マネージャーは顔の筋肉を緩めて仕方ないな、小声で言った。マネージャーは私のことを気に入っているらしく、大抵の事はにっこりすれば許してくれる。だから私はほとんどの女の子に嫌われている。
会場に入ると、私たちは笑顔を振りまき、トレーを片手にビールやワインを注いで回った。いつもと全く変わらない。退屈な立食パーティー。しばらくすると私は数少ない中のいいコンパニオン仲間のユリと会場の控え室で空き瓶の整理をしているふりをしながらビールを飲み、舌ピの話で盛り上がっていた。
「いやあ、びっくり。まさか舌に開けるとね」
ユリの反応はマキとほぼ同じ。
「男の影響でしょ?」
ユリはニヤッとして親指を立てた。
「まあね、男よりも舌に惚れた感じだけど」
話は舌から下ネタにもつれ込み、キャッキャとはしゃいでいるとマネージャーが呼びに来て、私たちは最後に一杯ずつビールを飲むと口臭スプレーをして会場に戻った。
私は二時間のパーティーでエリートさんたちから十三枚名刺を貰い、パーティーが終わった後ユリと名刺を物色した。
「これでいいじゃん。取締役」
「でも顔覚えてないし。どうせオヤジじゃないのぉ?」
はっきり言って、スーツを着込んだエリートに興味はないし、彼らだって舌ピをしているような女に興味はないだろう。気だての良い日本女性を装うった私は、どこのパーティーでもたくさん名刺を渡されるけど、結局私のイメージは全てが作り物。スプリットタンを完成させたら、このバイトも出来なくなる。早く穴を開けたいと、舌を鏡に映して思った。
私たちはその後別のホテルでも同じことを繰り返し、夜の八時に解散した。バイト料を貰いユリと一緒に事務所まで行った後、途中まで一緒に帰る事にした。携帯が鳴り、ユリが親指を立てて眉を上げて笑った。着信はアマからだった。そう言えば、置手紙かメールをしようと思っていたけど、完全に忘れていた。
「もしもし? ルイ? どこいんの? 何してんの?」
アマは今にも泣き出しそうな声でたたみかけた。
「あー、ごめん。急にコンパニオンのバイトに呼ばれて、今帰ってるから」
「何それ? ルイ、バイトなんかしてたの? コンパニオンって?」
「うるさいなー。登録制のバイトだよ。変なバイトじゃないから」
アマの怒涛の質問に辟易(へきえき)している私を、ユリが笑いをこらえながら見ていた。駅前で落ち合う約束して電話を切ると、ユリは吹き出した。
「何? 彼氏、束縛厳しいの?」
「あー、何か子供みたいな奴でさ。調子が狂うよ」
可愛いじゃーん、と言ってユリは私を小突いた。可愛いだけならいいんだけど‥‥、そう思ってため息をついた。駅でユリと別れて、帰路についた。二十分電車に揺られて、駅に着くと軽いステップで階段を上った。改札の向こうにアマの姿が見えた。手を振ると、アマは情けない顔をして手を振り返した。
「帰ったらルイいないし、書き置きもないし、出て行っちゃったんじゃないかって死ぬほど心配したんだから」
焼き肉屋に入り、ビールを注文するとアマは一気にそう言った。
「ま、いいじゃん。おかげで贅沢出来る訳だし」
アマはバイトの内容をしつこく聞き出し、やましいことがないと分かるといつものスマイルを見せた。アマはルイの着物姿見たいなあ、なんて言って私の小皿にレモンを搾った。焼き肉は美味しくて、ビールも美味しくて、最高の夕飯だった。働くのは大嫌いだけど、働いたのちのビールはいつもより美味しい。
それだけが労働の救いだ。上機嫌の私はアマの髪の色を褒めてやったし、珍しくつまらないギャグにも笑ってやった。大丈夫、アマの髪の色はアッシュだし、アマは幸せそうに笑ってる。まずいところは何一つない。
暑い。このクソ暑さも、残暑と呼ばれるようになった。Desireで麒麟の刺青を見せてもらった日から三週間余り、やっとシバさんから電話が来た。なかなか上手く描けなくて、苦戦したんだぞ、シバさんそう言ってデザインにかけた苦労をひとしきり語ると、早く見せてやりたいよ、とボソッと言った。私の舌ピも12Gになっていた。
次の日私はピアスを見たい、とアマを誘い、二人でDesireに向かった。Desireに着くと、シバさんは待っていましたとばかりに私たちを奥の部屋に連れて行き、デスクから一枚の紙を取り出した。すげえ、と声を上げたアマ。私もその絵に釘付けになった。そんな私たちをシバさんは満足そうに見て「いいだろ」と子供がおもちゃを自慢するように呟いた。
「これ、彫って」
私は一目で決めていた。こんな麒麟が私の背中に住むなんて、考えただけでゾクゾクする。今にも紙から舞い上がりそうな龍と、その龍を飛び越えようとするかのごとく前脚を高く持ち上げている麒麟、彼等は、私の一生の伴侶に相応しい。
「いいよ」
シバさんはニヤッとして答え、アマはやったじゃん、と叫んで私の手を取った。
こんなに素晴らしい刺青もデザインも、見たことがない。早速私たちは彫る場所と大きさを確認した。左肩の裏から背中にかけて、アマのよりも少し小さめで、15×30センチくらい。三日後に施術と決めた。
「前日はアルコールをとらない事。それと、出来るだけ早く寝て。体力使うからね」
シバさんの言葉に、アマもうんうんと頷いた。
「大丈夫ですよ。俺がルイの面倒見ますから」
アマはそう言ってシバさんの肩を抱いた。あきれ顔のシバさんがチラッと私を見て、一瞬あのヤッてる時の冷たい目をした。私が上目遣いで微笑むと、シバさんは含み笑いをした。
その後、飯でも食おう、というアマの提案でシバさんは少し早く店を閉めた。三人で外を歩くと、通り過ぎる人たちが道を空けた。
「いやー、やっぱシバさんと歩くとみんな振り返りますね」
「お前の方が目立つだろ。そんなギャングみてーなカッコして」
「ていうか二人とも怖いから」
私の言葉に二人は口を噤んだ。
「でもさ、ギャングとパンクとギャルって変な組み合わせだよな」
アマがそう言って私とシバさんを見比べた。
「ギャルじゃないってば。ねえ、私ビールを飲みたい。居酒屋いこっ」
私はシバさんの間に入り、三人並んで人通りの多い繁華街を歩いた。安い大衆向けの居酒屋で、座敷席に案内されると、他の客が私たちを一瞥して気まずそうに目を逸らした。私たちはビールで乾杯して、刺青の話でヒートアップした。アマの体験談から始まり、シバさんの彫り師になったばかりの苦労話、麒麟の画にかけた情熱。終いには二人とも上半身裸になってこの彫り方がどうだの、ここのぼかしがどうだのと熱く語り、そんな二人を見たらひどく微笑ましい気持ちになった。
その時、私はシバさんが楽しそうにしているのを初めて見たことに気づいた。二人でいた時には決して見せなかった顔だった。S男も時には満面の笑みを浮かべるんだ。「服着ろよ」とか「うるせーよ」とか言いながら、私はゴキゲンそでビールを飲んだ。素晴らしいデザイン画、楽しい宴、美味しいビール。これだけあれば、ほとんどの事が上手くいくような気がした。アマがトイレに立った隙に、シバさんは身を乗り出して私の頭を撫でた。
「あれで文句ないだろう?」
もちろん、と答えると、私たちはニッコリして見つめ合った。
「綺麗に彫ってやるからな」
というシバさんの言葉は力強く、私はこの人に出会えてよかった、と思った。
「シバさんの手にかかればお安いもんでしょ」
「ゴッドハンド?」
シバさんは苦笑交じりにそう言ってテーブルの上に置いた手をパーにした。
「彫っている時、お前の事殺したくなったらどうしよう」
シバさんはまた冷たい目に戻って自分の手を見つめた。
「いーんじゃない? それはそれで」
私はそう言ってビールをあおった。アマが戻って来るのが見えた。
「他人にこんなに強い殺意を持ったのは初めてだ」
シバさんがそう言い終わった瞬間、アマがだらしない笑みを浮かべてテーブルに戻った。
「トイレゲロまみれ。俺も吐きそうになったよ」
アマの言葉で、場の空気はあっさり元に戻った。私のために男を殴り続けた男と、私に強い殺意を持った男。どちらが、いつか私を殺すことはあるのだろうか。
二日後、アマは冷蔵庫の中のアルコール類を全て台所の棚の中に入れ、鎖を巻き付け鍵をかけた。「アル中じゃないんだから」と言うと、アマは「アル中みたいなもんだろ」と言って鍵をポケットに入れた。
「俺がいない間にコンビニにビールを買いに行ったりすんなよ」
そう言い残してアマはバイトに向かった。人の事をバカにして…‥。一日アルコールを抜くくらい何て事ない。そう思って棚を軽く小突いた。でも、その日の夜アマが帰って来る頃には、私の頭の中はビールの事で一杯になっていた。このところ、毎日昼夜欠かさず飲んでいた事を思い出した。
日常になっていて、気づかなかったけど、アルコールっていうのは本当に依存性が高いんだ、と再確認した。アマが帰ってくると、たまっていた物を吐き出すようにアマに当たり散らし、そんな私をアマはやっぱりね、という顔で宥めた。
「だから言ったじゃない。ルイは自覚が甘すぎるんだよ。いつも酒浸りなんだから」
「うっさいわね、別に酒飲みたい訳じゃないわよ。あんたの顔を見てると腹立ってくんのよ」
「はいはい。ま、酒の事は忘れてご飯食べて早く寝ようよ。明日は大勝負なんだから」
アマに宥められるなんて、何て失態だ。そう思いながら私は外に出る支度をした。夕飯はノンアルコールの牛丼だった。私は甘ったるい牛丼に腹を立て、七味をまんべんなくふりかけて食べた。アマはそんな私を子を慈しむ母のような目で見た。そんなアマの視線がウザったくて、何度もアマの頭を引っぱたいた。
家に帰るとアマは次々に指示を出し、まだ八時だというのに私は風呂上がりでアマのジャージを着せられ、アマの作った砂糖たっぷりのホットミルクを無理矢理飲まされ、ベッドに引きずり込まれた。
「眠れる訳ないでしょーが。昨日何時に寝たと思ってんのよ」
「がんばれ、寝るんだルイ。羊数えてやろうか?」
アマは頼んでもいないのに羊を数え始め、私は仕方なく目を閉じた。羊が百匹を超えようという時、突然アマは黙り込み、私を抱きしめた。
「明日、俺も一緒に行っていい?」
「何言ってんの? アマ、バイトでしょ明日」
私の言葉にアマは俯いた。
「シバさんの事信用していないわけじゃないけど、心配なんだよ。二人きりな訳だろ?」
私はため息をついた。
「大丈夫だって。シバさんはプロでしょ。そんな事する人じゃないよ」
強い口調で説得すると、アマは分かったよ。としょぼくれた顔で呟いた。
「でも、気を付けてね、本当に。たまに、あの人の考えている事が全く分からない時があるんだ」
「あんた程分かりやすい人の方が珍しいわよ」
そう言うとアマは弱々しく笑った。アマは私の服を脱がせるとうつぶせにさせて、背中を何度も撫でまわし、キスをした。
「明日には、ここに龍が舞うんだね」
「麒麟もね」
「ルイの肌、白いからもったいない気がするけど、彫ったらきっともっとセクシーだね」
アマは繰り返し背中を愛撫して、バックから入れた。アマはいつものように陰部に射精し、私はいつものようにブツブツ言いながらバスルームに向かうハメになった。
出ると、アマはまた謝り、私の体を隅から隅までマッサージした。体がほぐれると次第に意識がボヤけ始め、眠りが目前まで迫っているのが分かった。明日、行く前に舌のピアスを10Gにしようと思った。
Desireに着くと、すでにドアにはCLOSEDの札が出ていた。外は暑くて、ピラピラのワンピースもじっとり湿っていた。ドアは開いていて、押し開けるとカウンターの中でコーヒーを飲んでいるシバさんと目が合った。
「いらっしゃい」
シバさんは威勢良くそう言って、手招きした。奥の部屋に入ると、テーブルの上にはあのデザイン画が置いてあった。シバさんは黒い革の鞄をテーブルに置いて、そろりと開いた。私にはよく分からないけど、色んな道具が入っていた。先に何本も針がついている棒とか、インクとか。
「昨日はちゃんと寝た?」
「アマに急かされ八時に布団に入ったわよ」
シバさんはクスッと笑って寝台にシーツをしいた。
「服脱いで。戸棚の方頭にして寝て」
シバさんはインクや針を取り出しながら私の方を見もせずに言った。私はワンピースを脱いでブラジャーを外し、寝台に横になった。
「今日はライン彫りな。今日で形が全部決まるから。今なら形の変更とかあれば聞けるよ、何かある?」
私は上半身を起こしてシバさんの方を振り返った。
「一つだけ。お願いがあるの。龍と麒麟に目を入れないでほしいの」
シバさん一瞬あっけにとられた顔をして、おずおずと口を開いた。
「それは、瞳を入れないって事?」
「そう。目の玉を入れないでほしいの」
「どうして?」
「画竜点睛(がりょうてんせい)の話、知ってる? 瞳を描いたら、飛んで行っちゃったってやつ」
シバさんゆっくり頷き、上目遣いで宙を見つめた。そして私の方を見た。
「なるほどね。分かった。龍と麒麟には瞳を入れない。その代わり、顔のバランスが悪くなるから、インパクトをつけるために目の縁のラインにぼかしを入れるよ。それでいい?」
「それでオッケー。ありがとう、シバさん」
このワガママ女、シバさんそう言って寝台の脇の椅子に座って私の顔を撫でた。
シバさんは左肩から腰にかけてカミソリで産毛を剃り、ガーゼで消毒して、ラインをトレーシングペーパーで背中に写した。左肩から背中一帯にかけて画が写され、シバさんはそれを鏡に写すとこれでいい? と聞いた。オッケー、そう言うとシバさんは鞄の中の道具をあさり、ハンドルがついている太いボールペンみたいな物を取り出した。恐らくこれが彫る機械なんだろう。
「ねえ、見て。10Gにしたの」
シバさんの方に顔を向けて舌を出すと、シバさんはその日一番の笑顔を見せた。
「そっちも着々と進行してるな。あんまり急いで無理すんなよ。耳と違って粘膜は炎症起こすと厄介だからな」
口をすぼめてはーい、と言うとシバさんは痛かったろ? と私の唇を指でなぞって聞いた。うん、そう答えるとシバさんはまた私の顔を撫でた。
「じゃ、いくよ」
シバさんは私の背中に手を置いた。シバさんはゴム手袋をはめていて、冷たい感触がした。こくっと頷くと、背中にピリッとした痛みが走った。思ったほどの痛みではなかったけど、針が入る度に体中に軽く力が入った。
「針を入れる時に息を吐いて、抜く時に吸ってみな」
シバさんの言ったとおりにすると少しだけ楽になった。
シバさんはまるで絵を描くようにザクザクと彫っていき、二時間もすると龍と麒麟のラインが入った。シバさんは彫っている最中ずっと無言で、たまにチラチラ目を向けて観察してたけど、額に汗を浮かべて一心に彫り続けていた。最後の一針を抜いて、私の背中をタオルで拭くと、シバさんは伸びをしてコキコキと首をならした。
「お前ってほんと痛いの平気なんだな。初めての奴って大体いてぇいてぇってうるせえもんだけどな」
「ふうん。私って不感症なのかな」
「んな訳ないだろう。あんなによがっといて」
シバさんはタバコに火をつけて一口大きく吸うと私に咥えさせた。そしてまたもう一本取り出し火を点けて吸い始めた。
「優しいじゃん」
からかうように言うとシバさんは笑って、一口目がうまいんだよ、と言った。
「噓だあ。美味しいのは二口目でしょ」
シバさんは何も答えずにクスッと笑った。
「ねえ、殺したくなった?」
「ああ、だから彫る事だけに集中してた」
私は寝そべったまま灰皿に手を伸ばして灰を落とした。灰は手応えなく灰皿の中にポロッと落ち、細かい灰がヒラヒラと灰皿の外に落ちた。
「なあ。もしもお前がいつか死にたくなったら、俺に殺させてくれ」
シバさんは私のうなじに手を当てた。軽く微笑んで頷くと、シバさんはニッコリして「死姦してもいい?」と聞いた。
「死んだ後の事なんてどうでもいいわ」
私は肩をすくめてみせた。死人に口なしって言葉があるように、何事にも感想を述べられないなんて、そんな無意味な事ってない。だから私は墓石なんかに高い金を払う人間の気持ちは分からない。自分の意識が宿っていない身体になんて、興味はない。私は自分の死体が犬に食われよと知ったこっちゃない。
「でもお前が苦しそうな顔見れなかったら、勃たないかな」
シバさんは私の髪をつかみ、上に持ち上げた。首筋の筋肉がきつい角度に驚き、ビクビクした。顔を歪めるとシバさんは私の顎をつかみ、上を向かせた。
「舐めるか?」
私は無意識の内に首を縦に振っていた、シバさんには有無を言わせない、絶対的な威圧感がある。上半身を起こし、シバさんのベルトに手を掛けた。シバさんは私の首に手を掛けた。首を絞める力が強くて、殺されるんじゃないかと思った。でも、シバさんは私の背中をかばってくれたのか、ずっとバックだった。そして終わった後もずっと私の背中を見ていた。
ブラジャーをすると痛そうだったから、ノーブラでワンピースを着た。シバさんは上半身裸のまま、ずっと私を見ていた。精子を拭いたティッシュを捨てようとゴミ箱を探していると、僅かな物音が聞こえた。シバさんにも聞こえたのか、怪訝そうな顔をして店の方を見た。
「お客さん? 鍵かけてなかったの?」
「忘れてた。でも、クローズにしておいたけど」
シバさんがそう言った瞬間、ドアが開いた。
「ルイ? 来ちゃった」
「おー、今終わったとこ。お前、バイトは?」
白々しく涼しい顔で答えるシバさん。あと十分早くアマが来ていたら、どうなっていた事か。
「便秘っつて早退しちゃった」
「あんたのバイトは便秘で早退出来る訳?」
私は肩をすくめて言った。
「店長に怒られたけど、何とか」
嫌味で言ったつもりだったのに、アマはニッコリしてそう答えた。私はさりげなくティッシュをシーツの下に隠した。アマは私の刺青を見ると「おー」とか「すげー」とか騒いで、シバさんにお礼を言った。
「でもシバさん、ルイに変な事しなかったでしょうね?」
「大丈夫だよ。俺痩せている女に欲情しないの」
シバさんの言葉にホッとした表情を見せたアマ。あれ‥‥? とアマは間抜けな声を上げ、後ろめたさが残っていた私は驚いてアマを見た。シバさんも同じだったのか、ん? とでも言いたげに眉をひそめている。
「龍も麒麟も、目入ってないんじゃん」
私は胸をなで下ろして、ホッと息をついた。
「私が頼んだの」
シバさんにしたのと同じ説明をすると、アマは大きく頷いてなるほどね、と言った。
「でも俺の龍は目入ってるけど飛んでいかないよ?」
そう言う間抜け面のアマの頭をはたくと私はワンピースの紐を肩にかけた。
「しばらく、風呂入らないでね。シャワーも直接当てないで、後に、タオルとかで拭く時も擦っちゃダメだからね。それと、消毒した後は何かクリームとか塗っておいて。消毒は一日二回くらい。あと、あんまり日光に当てないでね。一週間くらいするとかさぶたが出来ると思うけど、引っ掻いちゃったりしちゃダメだよ。完璧にかさぶたと腫れがなくなったら次の施術な。とりあえず、かさぶたが完全に剥がれたら連絡して」
シバさんはそう言って私の肩を軽く叩いた。はーい、と何故かアマも私も声を合わせて返事をした。飯いきません? というアマの誘いをシバさんはこんな中途半端な時間にくわねえよ、とあっさり返し、私たちは二人でDesireを出た。帰り道で、思いっきり首をひねって背中を見ると、ワンピースから龍と麒麟が少し飛び出していた。そんな私にアマは複雑そうな顔で見ていた。
なに? と目で聞くとアマは私から目を逸らして口をへの字にした。無言のアマに嫌気がさし、半歩先を歩いていると、アマは不貞腐れた顔のまま私の手をつかんで横に並んだ。
「ルイ、何でワンピースなんて着てくんだよ。パンツ一枚で彫ってもらったんだろ?」
バカバカしい言葉に思わずしかめっ面をすると、アマはムッとした顔をして俯いた。
「Tシャツなんかよりヒラヒラな方が彫ってもらったあと楽だと思ったのよ」
そう言うとアマは俯いたまま黙り込み、つないだ手にグッと力を込めた。信号待ちで立ち止まると、やっと顔を上げて私を見た。
「情けない? 俺」
情けない顔でそう聞くアマを見てると、同情に近い気持ちが生まれた。誰かに一生懸命になっている人を見ると、いつもいたたまれない気持ちになる。
「ちょっとね」
アマは情けない顔のまま困ったような笑みを浮かべて、私が弱弱しく微笑み返すと勢い良く私を抱きしめた。仮にも、繫華街。通行人が私たちに目を止めていく。
「情けない男、嫌い?」
「ちょっとね」
アマは更に腕に力を込め、私は少し苦しくなった。
「ごめん。分かっていると思うけど、ルイのこと愛しているんだ」
やっと私から離れたアマの目は少し充血していて、ジャンキーみたいだった。頭を撫でてやると間抜け笑い、私たちはまた歩き出した。その日、私は倒れるまで酒を飲み続けた。アマは意外と嬉しそうに私を介抱した。もう、あの事件から一ヶ月近く経った。アマは、変わらず私の傍にいる。大丈夫、大丈夫だってば‥‥。私は自分に言い聞かせた。
舌ピをした。刺青が完成して、スプリットタンを完成したら、私はその時何を思うだろう。普通に生活していれば、恐らく一生変わらない筈の物を、自ら進んで変えるという事。それは神に背いているとも、自我を信じているともとれる。私はずっと何も持たず、何も気にせず何も咎めずに生きてきた。きっと、私の未来にも、刺青にも、スプリットタンにも、意味なんてない。
刺青は、四回の施術を経て、完成した。デザイン構想から四ヶ月経っていた。シバさんは彫るたびに私を抱いた。最後の施術を終えた後、シバさんは珍しく私のお腹の上の精子を拭いた。シバさんはおもむろに口を開いて「俺、彫り師やめようかな」とボンヤリ宙を見上げ、そう言った。私はシバさんを止める理由もなく、ただ黙ってタバコに火を点けた。
「アマみたいに、一人の女と付き合ってみようかと思って」
「彫り師やめるのと関係あるの?」
「人生の再出発ってやつ? 最高の麒麟彫ったし、思い残す事もーないって思って」
シバさんは自分の頭を撫でて、ため息をついた。
「無理だよな。俺って基本的にいつも転職考えているから、気にしないで」
上半身裸のシバさんの腕の麒麟は、まるでそこに君臨するかのように鋭い目をして、私を睨んでいた。
龍と麒麟は最後のかさぶたを作り、それも完全にはがれ、完璧に私の物となった。
所有、というのはいい言葉だ。欲の多い私はすぐに物を所有したがる。でも所有というのは悲しい。手に入れるという事は、自分の物であるということが当たり前になるという事。手に入れる前の興奮や欲求はもうそこにはない。
欲しくて欲しくて仕方なかった服やバッグも、買ってしまえば自分の物で、すぐにコレックションの一つに成り下がり、二、三度使って終わり、なんて事も珍しくない。結婚なんてんのも、一人の人間を所有するという事になるのだろうか。事実、結婚をしなくても長い事付き合っていると男は横暴になる。釣った魚に餌はやらない、って事だろうか。でも餌がなくなったら魚は死ぬか逃げるかの二択しかない。
所有ってのは、案外厄介なものだ。でもやっぱり人は人間も物も所有したがる。全ての人間は皆MとSの要素を兼ね備えているんだろう。私の背中に舞う龍と麒麟は、もう私から離れる事はない。お互い決して裏切られる事はないし、裏切る事も出来ないという関係。鏡に映して彼等の目のない顔を見ていると、安心する。こいつらは、目がないから飛んでいく事すら出来ない。
施術前10Gだった私の舌ピは6Gになっていた。拡張するたび、これ以上は拡張出来ないんじゃないかと思うくらい痛い。拡張した日は飯が不味い。拡張した日はイライラしてアマにあたる。拡張した日は自分が自己中心的でひどくワガママだという事を再確認する。拡張した日は皆死んじゃえばいいとすら思う。思考とか価値観は、ほぼ猿並だ。
窓からの景色が寒々しい。外に出ると乾いた空気の匂いがする。十二月に入って一週間が過ぎた。滅多に働かないフリーターには曜日感覚がない。刺青を入れ終えてから、一ヶ月以上が経った。あれからというもの、私には活力という物が全くない。寒いからだろうか。毎日毎日、時間が過ぎることを願っている。早く明日になったところで、何が解決するという訳でもないのに。
大体、問題がある訳でもない。なのに私には活力がない、朝起きて、アマを見送り、二度寝する。時にバイトをしてみたり、シバさんとセックスをしたり、友達と遊びに行ったりするけど、自分の行動一つ一つにため息が付きまとう。夜、アマが帰ってくると二人で飯を食いに行き、酒を飲んだりつまみを食べたりして、帰って来てまた酒を飲む。ただのアル中だろうか。
アマは元気のない私を飽きることなく心配し続け、無理にテンションを上げたり、機関銃のように喋り続けたりして、それでも私が暗い表情のままいると急に泣き出したり、憤りと切なさを切々と語ったり「何でだよ」と悔しそうに言ったりもした。そんなアマを見ていると、気持ちに応えてやりたいという小さな希望が生まれるけど、それはいつも自己嫌悪に押しつぶされた。
まあとにかく光がないって事。私の頭ん中も生活も未来も真っ暗って事。そんな事とっくに分かっていたけど。今はよりクリアーに自分が野垂れ死ぬところが想像できるって事。問題はそれを笑い飛ばす力が今の私にないって事。少なくとも、アマに出会うまでは生きる為だったらソープで体売るくらいの事はしてやるよ、と思っていた。
それが今の私には寝て食べるくらいの事しか出来ない。今は、臭いオヤジとやるくらいだったら死んでもいいかなと思う。一体どっちの方が健康的なんだろう。ソープで働いてでも生きてやるってのと、ソープで働くくらいだったら死んだほうがまし、ってのと。考え方としては後者の方が健康的だけど、本当に死んだら健康もクソもない。やっぱり前者が健康的なんだろう。そう言えば、セックスで満たされている女の肌の艶がいいとか言う。別に不健康でもいいけどね。
そして舌ピを4Gに拡張した。血がにじんでその日は飯を食えなくて、ビールだけで腹を満たした。アマは拡張するテンポが早いんだよ、と言ったけど、私は急がなきゃと思った。末期癌と告知された訳でもないのに、時間がないと感じた。きっと時には行き急ぐことも必要だ。
「ルイは、死にたいとか思う事ある?」
いつも通り夕飯を食べて、家に帰ってビールで乾杯した後、アマは不意にそんな事を聞いた。しょっちゅうよ、そう呟くとアマはビールの入ったグラスをぼんやり見つめてため息をついた。
「たとえお前だろうが、お前のその体を殺すことは許さない。自殺するんだったら、その時は俺に殺さしてくれ。俺以外の人間がお前の生を左右するなんて、耐えられないんだ」
シバさんの事を思い出した。私は死にとり憑かれたとき、どちらに殺しを依頼するのだろう。どっちの方が鮮やかに殺してくれるだろうか。明日、Desireに行こう、そう思った。そしたら、ほんの少し生きる気力が湧いた気がした。
昼過ぎからのバイトに向かうアマを見送った後、私はシバさんに会いに行くために化粧をしていた。化粧が終わったらシバさんに電話をしよう、そう思った瞬間だった。けたたましく携帯が鳴った。私の気持ちを読んだのだろうか。シバさんからだった。
「はい?」
「あ、俺、今大丈夫?」
「うん。今日ね、シバさんとこに行こうかと思ってたの。どうかした?」
「ああ、あのさ、アマの事なんだけど」
「‥‥何?」
「あいつ、七月頃に何か問題起こした事とかなかった?」
シバさんの質問に、胸が苦しくなるのが分かった。男を殴り続けるアマの姿が頭に浮かんだ。
「知らないけど。…‥どうして?」
「さっき、警察が来て、刺青を入れた客のリストを見せろって言われた。龍の刺青を彫った客を教えろって。アマの事かは分からないけど、俺リストなんて一見の客しかつけていないし、アマも書いていなかったからもしあいつの事もパレてないと思うけど」
「‥‥アマの事じゃないよ。アマはいつも私と一緒に居たもん」
「そうだよな。ごめん、赤い髪って言っていたから。ほら、あいつ髪赤かっただろう? だから、ちょっと気になってさ」
そう…私は呟いて大きく息を吸った。心臓の鼓動が全身を震わせた。携帯を持っている手が細かく震えていた。どうしよう、シバさんに言ってしまおうか。言ってしまえば、きっと楽になる。シバさんの意見を聞く事も出来る。でも、言っていいのだろうか。シバさんは私の話を聞いたらアマに言うのだろうか。アマは、私が新聞で読んだ事を知ったらどうするのだろうか。自首でもするだろうか。それとも、どこかに逃げたりするだろうか。
こんなにアマの傍にいるのに、あんなに分かりやすいアマの事なのに、私はアマの行動を一つも予想する事が出来ない。だって、人殺しの容疑がかかっているなんて状況。未だかつて経験したことが無い。人を殺したかもしれないとき、人は何を思うんだろう。自分の将来、大切な人の事、今までの生活、きっと様々な思いが頭に浮かぶのだろう。でも、そんなの分からない。だって私には未来なんて見えてないし、そんなのあるかどうかだって分からないし、大切な人なんていないし、生活なんて酒浸りで良く分からない。ただ一つ分かるのは、私はこの生活の中でずっとアマと一緒にいて、次第にアマを大事に思うようになってきたって事。
「ルイ、気にしないでくれ。ただちょっと気になって電話してみただけなんだから。今日、来るか?」
しばらく黙り込んでいると、シバさんが心配そうな声で言った。
「あ、うん。ありがと。今日は、やめとく。また今度行くことにする」
「‥‥来てくれないのか? 話がしたいんだ。お前と」
「じゃあ‥‥気が向いたら、行く」
私は電話を切った後、部屋中を歩き回って、とにかく考えた。イライラして、酒を飲んだ。アマと一緒に飲もう、と約束していた日本酒を開けて、ラッパ飲みした。思った以上においしくて、日本酒はどんどん私の中に落ちていった。空っぽの胃に水分が溜まっていくのが分かった。四合瓶を一本空けてしまうと、途中だった化粧を再開して、化粧が終わるとバッグを持って部屋を出た。
「こんにちは」
「‥‥何だよ、白々しいな」
そう言ってドアの方に振り返ったシバさんは、私を見ると眉間に皺を寄せて訝しげな顔をした。
「心労?」
苦笑してそう言うシバさんに、私も苦笑で返した。カウンターの前まで歩くとレジの脇で焚いているお香がツンと匂った。吐き気がした。
「冗談じゃなくて、お前おかしいぞ」
「何が?」
「前に会ったの、いつだった?」
「二週間前、くらいじゃない?」
「お前あれから何キロ瘦せた?」
「分かんない。アマんとこ体重計ないから」
「お前、気は持ち悪いくらい痩せているぞ。顔色悪いし。酒臭いし」
ショーケースに自分の姿を映して見た。ほんとだ。ガラスに映った私はまるで蚊トンボのようだった。きもちわる…自分でもそう思った。生きる気力が湧かないと、こんな症状まで出て来るのか。そう言えば、最近酒しか飲んでいない。食べるのは酒のつまみだけ。最後にちゃんとした食事をとったのはいつだろうか。私は何だかおかしくなって、肩を震わせて笑った。
「アマに食べさせてもらっていないのか?」
「アマは食べろ食べろってうるさいよ。私は酒が飲めればいいから」
「お前、そんなじゃ、自殺とかの前に餓死すんぞ」
「自殺、しないよ」
私はそう言うとシバさんの横を通って奥の部屋に入った。
「何か買ってくるわ。お前、食べたい物ある?」
「じゃあ、ビール買って来て」
「ビールは冷蔵庫に入ってるよ。他に、ないの?」
「シバさん、人殺した事ある?」
シバさんは、一瞬、私の方を見た。シバさんの目は鋭くて、体中が痛くなった気がした。「‥‥そうだな」シバさんはそう呟いて私の頭を撫でた。私は何が悲しいのか分からなかったけど、涙を流していた。
「どんな気持ちだった?」
そう言った私の声は流れ続ける涙のせいで震えていた。
「気持ち良かった」
お風呂どうだった? と聞かれたかのように答えるシバさん。聞く相手を間違えたな‥‥。私は流してしまった涙に後悔しながら「そう」と呟いた。
「服脱げよ」
「買い物行くんじゃなかったの?」
「お前の泣き顔を見たら勃つた」
私は服を脱いで下着姿になるとシバさんに手を伸ばした。シバさんは珍しく白のワイシャツなんて着ていて、下はグレーのパンツだった。ベルトを外すとシバさんは私を抱きかかえて寝台に寝かせた。見下ろすシバさんの冷たい目に反応する私の下半身。パブロフの犬じゃないんだから‥‥。
シバさんは私のあらゆる肉に指やペニスをめり込ませ、私はその都度苦しんだり喘いだりした。セックスするたび、私に触れるシバさんの指の力が強くなる。これが、シバさんの愛の証なんだろうか。このままじゃ、いつか殺される。
「お前、俺と結婚しない?」
シバさんはセックスした後、寝台で寝そべる私の隣に座り、タバコに火を点けて言った。
「話しがしたいって、その事だったの?」
「まあ、ね。アマは、お前の手に負えるような相手じゃないし、お前は、アマの手に負えるような相手じゃない。とにかく、バランスが悪いんだよ、お前らは」
「だから俺と結婚しろって?」
「いや、別に。まあ、それとは関係なしに。何となく結婚、してえと思ってさ」
シバさんは素っ気ない言い方で、変なことを言った。何となくしたい結婚って‥‥。随分曖昧なプロポーズだ。シバさんは私の返事を待たずに寝台から降りて服を着た。デスクの中からジャラッと何かを摂り出した。
「一応、指輪作ってみた」
シバさんはそう言って私にシルバーのいかつい指輪を手渡した。それは指の付け根から爪の途中まである指輪だった。いかにも‥‥というパンク臭さ。作りはしっかりしていて、関節の所は指の動きに合わせてちゃんと曲がるようになっていた。私はそれを右の人差し指にはめた。
「作った、の?」
「ああ、趣味でこういうのもやってんだ。ま、お前の趣味とかけ離れたもんだろうけど」
「ふうん、すごい。それにしてもいかついね」
そう言って笑うとシバさんも苦笑した。ありがと、私はそう言うとシバさんにキスをした。シバさんはうざったそうな顔をして、買い物に行ってくる、と言って部屋を出た。私はシバさんの言葉を思い出していた。バランスが悪い、っていうのはどういう事だろう。大体、バランスがいい人間関係なんてあるんだろうか。
無気力の中、私は結婚という可能性を考えてみた。現実味がない。今自分が考えている事も、見ている情景も、人差し指と中指で挟んでいるタバコも、まったく現実味がない。私は他のどこかにいて、どこかから自分の姿を見ているような気がした。何も信じられない。何も感じられない。私が生きている事を実感できるのは、痛みを感じている時だけだ。
シバさんがコンビニの袋を持って帰ってきた。
「ほら、食えよ。少しくらい、食えんだろ」
シバさんそう言ってカツ丼と牛丼を私の前に並べた。
「どっちがいい?」
「いらない。ビール、飲んでいい?」
シバさんが答える前に腰を上げた。冷蔵庫からビールを出して、デスクの脇のパイプ椅子に座ると一気に飲んだ。シバさんは呆れた、と言いたげに私を見ていた。
「ま、そんな調子のお前でも、俺はいいと思っているから。気が向いたら結婚してくれよ」
はーい。私は元気よくそう言うとビールを飲み干した。
暗くなる前に帰路についた。外は冷たい風が吹いていた。私は一体、いつまで生きていられるのだろう。そう長くないような気がした。部屋に帰ると、舌のピアスを2Gにした。ググ、と押し込むと血が出た。痛さのあまり涙が出た。私は一体何のためにこんな事をしてるんだろう。アマが帰って来たら、即喧嘩だろう。私は痛みに苛つきながらビールを一気飲みした。
その日、アマは帰ってこなかった。何かが起こったのは、確かだ。一緒に住み始めてからアマが帰ってこない事は一度もなかった。私が待つ部屋に、必ずアマは帰ってきた。異常な程に律儀な奴だった。バイトが延びて遅くなる時は必ず電話してきたし、そう、一度もこんな事はなかった。
携帯に電話したけど、呼び出し音すら鳴らず、留守電に切り替わった。私は眠れないまま朝を迎え、クマを作った。どうしよう。一体どうしたらいい? アマは、私を一人にして一体どこで何をしてるんだろう。アマは、今何を考えてるんだろう。何かが静かに終わるような、そんな予感がした。
「アマ」
アマのいない部屋に、情けない私の声が、響いた。ピアス、2Gにしたんだよ。早く笑って喜んで。スプリットタンに近づいたね、って笑ってちょうだい。勝手に日本酒を飲んでしまった事を、あきれ顔で怒ってよ。
私は考えるのをやめて自分を奮い立たせた。私は意気込んで部屋を出た。
「捜索願って、親族以外でも出せるんですか?」
「あー、出せるよ」
警察のやる気のない態度に私は苛立った。
「あ、出すときは写真持って来てね」
私はそれに答えず交番を出た。私はズンズンと歩いていたけど、何処に向かっているのか分からなかった。私はふと、足を止めた。あ‥‥。私の中にまた一つの不安が生まれた。
「私、アマの名前知らないじゃん」
小さく呟くと、事の重大さが分かってきた。名前を知らないって事は、捜索願も出せないって事だ。私は顔を上げて歩き出した。
シバさんは必死の形相の私に驚いたような顔でもの言いたげに見つめた。
「アマの名前なんて言うの?」
「は? 何、急に」
「アマが、帰ってこないのよ。捜索願出すの」
「何だ? 名前って、名前知らねーの?」
「知らないのよ」
「一緒に暮らしてるんだろ?」
「暮らしているわよ」
言いながら、私は涙を浮かべていた。
「泣くなよ。だって表札とか手紙とか見るだろ普通」
シバさんは、よほど私の涙に引いたのか、目の前で大事故が起きたような顔で私を見つめながら言った。
「アマ表札なんか出していないし、郵便受けはいつもチラシが満タンになってから開いたこともなかったよ」
「ていうか、昨日は普通に仕事行ってたんだろう? 昨日の夜帰ってこなかって事か?」
「そうよ。昨日バイトに行ったきり帰ってこないのよ」
「一日くらいで何でそんなにいきり立ってるんだよ。大丈夫だよ。大体一日家を空けたくらいでそんな慌てるんだよ。アマは子供じゃねーんだぞ」
要領を得ないシバさんの言葉に、私は苛立った。
「アマは私と暮らし始めてから一度も無断で外泊なんてしたことないのよ。バイト三十分延びるってだけで電話してくるような男なのよ」
シバさんは黙り込んで、カウンターに視線を落とした。だからって‥‥、シバさんは呟いて私を見上げた。何故こんなに不安なのか、自分でもわからなかった。そう、シバさんの言っている事は正しい。一日くらい家を空けたって、心配する事はないんだ。
「アマ、人を殺したかもしれないの」
「あの。警察が言っていた暴力団員の‥‥・?」
「私がいけなかったの。私があそこであの男をシカトしてれば、アマはあの男を殴らなかった。まさか、死ぬなんて思ってもいなかったし、新聞見た時もまさかあのアマが殴った男なんて思ってもなかった。きっと別人だって思った。アマの事だなんて‥‥」
シバさんは私の手を取って強く握った。
「捜索願出したら、アマは捕まるかもしんねーぞ。もしもアマが事件のことを知って逃げているとしたら、このまま俺たちが知らないふりをしていれば、アマは逃げきれるかもしれない」
「‥‥アマが心配なの。どこで何して何を考えているか、分からないのが辛いの。アマは、アマは一人で逃げようと考えない。逃げるんだったら、絶対私に何か言っていくはずよ。きっと、私を連れていくはず」
「‥‥分かった。行こう」
シバさんは店を閉めて、私たちは警察署に向かった。シバさんは手際よく捜索願を出すとアマが上半身裸で写っている写真を手渡した。
「写真なんか、持っていたんだ」
「ん? ああ、彫ってやった時に龍撮って、悪ノリして二人で撮ったんだよ」
「雨田和則(あまだかずのり)さん、ですね」
警察が用紙に目を通しながら言った。私は初めてアマの名前を知った。アマダウスじゃ、ないじゃん。再びアマに会うことが出来たら、まず最初にそれを突っ込もう。そんな事を考えていたら、涙が出てきた。私は涙を止めることが出来なくなって、あたふたした。冷静なのに、涙腺が故障したように涙がダクダク流れた。
「‥‥大丈夫か?」
シバさんが私の頭を撫でたけど、涙を止める事が出来なくて、下を向いたまま署の入り口まで歩いて、待合い用の椅子に座って泣いた。どうして。どうして突然いなくなったりするのよ。私は身体を折り曲げて俯いたまま泣きじゃくった。しばらくすると手続きを終えたシバさんが戻って来た。私の視界は曇ったまま。拭いても拭いても涙が溢れる。コートの袖でゴシゴシ涙を拭いていると、子供の戻ったような気がした。私たちはタクシーでアマの家に戻った。
「アマ?」
玄関で呼んだけど、返事はない。シバさんは後ろから私の頭を撫でるとまた溢れだした私の涙を拭った。部屋に上がるとフローリングにべったりと座り込んで、泣いた。グズグズ泣き続ける私を、シバさんはベッドに座って観察するように見ていた。
「どーしてよつ」
そう叫んでフローリングを殴ると、人差し指にはめていたシバさんからもらったリングがぶつかって鈍い音がした。その音に反応して、私はまた激しく泣きじゃくった。一体、どうして、どうして私の事を置いてったのよ。涙が止まると怒りが込み上げてきた。
歯を食いしばっていると、頭が痛くなった。ガリ、と口の中で嫌な音がした。舌で口の中をまさぐると、虫歯だった奥歯が欠けていた。私は欠けた歯をかみ砕いて飲み込んだ。私の血肉になれ。何もかも私になればいい。何もかも私に溶ければいい。アマだって、私に溶ければ良かったのに。私の中に入って私の事を愛せば良かったのに。私の前からいなくなるくらいなら、私になればよかったのに。そうしたら、私はこんな孤独を味わう事はなかったのに。私の事を大事だって言ったのに。何でアマは私を一人にするの。どうして。どーして。
部屋中に、耳障りな泣き声が舞う。私はアマと二人で使っていたジュエリーボックスを開け、ピアスを摂り出した。昨日は2Gにしたばかりで、到底普通に入る訳ないから、短い角型のピアスを選んだ、大台の0G。私を見ていたシバさんの顔色が変わった。
「お前、それ0だろ。昨日4だったじゃねーかよ」
シバさんの言葉に振り返らず、鏡向かって2Gのピアスを外した。ピアスを差し込むと、真中まで入れたところでビリビリした痛みが走った。一気に、奥まで押し込んだ。シバさんが手を伸ばしたけど、ピアスは私の舌にギュウッとはまっていた。
「お前、何してんだよ」
シバさんは私の口を開け、眉をひそめて覗き込んだ。
「舌出せ」
言われた通りにすると、血が舌を伝わって床に落ちた。涙も、落ちた。
「ピアス、外せ」
私が左右に首を振ると、シバさんはひどく落ち込んだような顔をした。
「無理な拡張はすなって、言っただろう」
シバさんは私を抱きしめた。シバさんに抱きしめられたのは、初めてだった。私は、どうしていいかも分からずに、溢れる血をゴクッと飲み込んだ。
「私、00にしたら切る」
ろれつの回らない私の言葉は、アマの笑顔のようにだらしなかった。
「分かったよ。分かったから」
気づくと、涙は止まっていた。アマは、私の0Gを見たら何て言うだろうか。すごいじゃん、そう言って笑ってくれるはずだ。もうちょっとだね。そう言うはずだ。きっと喜んでくれる。
私はビールを飲み、ひたすら泣いた、アマを待った、シバさんはずっと私を見ていたけど、何も言わなかった。また、夜が来た。部屋の中はひんやりしていて、私は身震いした、シバさんは黙ったまま暖房を入れ、座り込んだまま私に毛布をかけた。
舌の血は止まった。涙は、断続的に流れた。悲しくなったり、怒りが込み上げてきたり、感情は揺れ動いた、七時になった。いつものシフトだったらアマが帰って来る時間だ。私は十秒ごとに時計を見上げ、何度も携帯を開いた。何度かアマの携帯に電話をしたけど、やっぱり留守電話に切り替わった。
「ねえ、アマがバイトしてる店って知っている?」
「‥‥え? お前、知らないの?」
シバさんが不思議そうな顔で私を見た。そう、私たちは何も知らない。
「知らないの」
「古着屋だよ。お前らって、ほんとに何も知らないんだな。って事は、まだ連絡してないの?」
「うん」
シバさんは携帯を開いてカチカチ検索すると耳に当てた。ああ、俺だけど。アマの事でさ。‥‥ああ、無断欠勤ね。昨日は? ‥‥ああ。家にも帰って来ていないんだよ。‥‥まだ分からない。‥‥ああ、何か分かったら連絡するからさ。
シバさんの言葉だけで、何も手がかりがないと分かった。シバさんは電話を切るとため息をついた。
「昨日は普通にバイト上がって帰って行ったてさ。今日は無断欠勤だって。電話してもつながらないって怒ってた。アマのバイト先、俺の知り合いの店なんだよ。無理言ってあいつを雇ってもらったんだ」
私はアマの事を何も知らない。昨日までは、自分が見ているアマの事だけ知っていればいいと思っていた。でも今はアマの事も何も知らないという事がひどく私のハンデになっている。どうして、名前や家族構成くらい聞いて置かなかったのだろう。
「知らない。でも、多分親は片方はいるんじゃないかな。父親の話、してた気がするけど」
そう、私は呟くとまた泣いた。
「なあ、何か食いに行かねぇ? 俺腹減ってんだけど」
シバさんの言葉に反応して、また私は泣き出す、いつもそうだった。私がビールだけで腹を満たしてしまうから、アマはいつも腹減った腹減った、と言って無理矢理私を外に引っ張り出していた。
「私、ここにいる。シバさん行って来なよ」
シバさん答えず、台所に行くと冷蔵庫をあさった。酒ばかりじゃねーかよ。シバさんがそう吐き捨ててイカの塩辛を取り出した瞬間、シバさんの携帯が鳴った。
「ねえ、鳴ってる」
私の声は、自分でもビックリするくらい大きく響いた。具合が悪くなるような動悸に、胸を押さえながら携帯を取って、シバさんに投げた。ナイスキャッチ。
はい? はい。ええ、はい。はい‥‥はい。分かりました。すぐ行きます。
シバさんは電話を切ると私の肩をしっかりつかみ、私を睨みつけた。
「横須賀で死体で発見されたらしい。アマかどうかはわからないけど、龍の刺青が入ってるって。確認に遺体安置所来てくれ、ってさ」
「‥‥そう」
そう、アマは死んだ。遺体安置で見たアマはねもう人間でなく、一体二体…と呼ばれる死体になっていた。人間であるアマは、もういない。現場で撮られた写真を見て、私は失神しそうになった。アマは、胸にナイフかなんかで網のような模様を刻み込まれていて、タバコを押し付けられた痕も無数にあった。爪は手も足も全て剝げていたという。アマは裸で、ペニスには何かお線香のようなものが刺してあった。
短い髪は所々むしり取られていて、血が滲んでいた。もう何ていうか、いじるだけいじり倒された後に、殺されたって事。自分の所有物のように思っていた人間がこれだけ他人に弄ばれた後に、殺された。こんな絶望、私はこれまでの人生の中で初めてだった。そして、アマの死体は解剖に回され、更に切り刻まれる事になった。
怒りすらも、痺れた頭は受け付けない。多分、私のアマへの最後の言葉は、今日はシバさんところに遊びに行こう、と考えながら背を向けたまま言った「行ってらっしゃい」だったと思う。シバさんはフラフラする私に何度も何度も手を貸し、遺体安置所で膝から崩れ落ちた私を支えた。そう、やっぱり私の未来に光なんて見えない。
「お前、しっかりしろよ」
「無理」
「お前、飯くらい食えよ」
「無理」「お前、少しくらい寝ろよ」
「無理」
アマが発見されてから、シバさんのところにお世話になる事にした私は、何度となくシバさんとこんなやり取りをした。会話にならねぇ…シバさんはいつもそう言って舌打ちをした。司法解剖の結果、死因は首を絞められた事によると窒息死。何とか反応がどうで、身体につけられた傷は全て生きているうちに付けられた事が分かった。
へえ、ていうか、早く犯人を見つけろよ。アマがどうやって殺されたなんて事よりも犯人が誰かが知りたいんだよ。手がかりなんて、たくさんあるだろ。私がどうしても納得出来なかった。アマの死体が発見された時、あの暴力団の仲間がやったのかと思ったけど、どうも違うんじゃないかと死体を見て思った。
暴力団が、タバコでヤキを入れたり、ペニスに線香を刺したり、そんな足のつくような証拠を残していくだろうか。どうせなら死体を東京湾に沈めてしまって欲しかった。あんな死体、私は見たくなかった。見つからなかったら、いつまでもアマは生きている、という自信をもっていられたのに。そう、アマはあの暴力団を殺していた。今更犯人が死体で見つかっても、しょうがない。アマが起こしたあの事件は、今まで何の意味もない。被害者も、加害者も、死んでしまったのだから。
アマの葬式に行った。アマのお父さんは、人の良さそうな顔をしていて、喪服に似合わない金髪の私を、嫌な顔一つせずに迎えてくれた。火葬場で棺の顔の部分を開けた時、私はその中を覗き込めなかった。お別れなんか言いたくなかった。遺体安置所で見たアマはまだ生きていて、棺の中にいるのは別人だと思いたかった。現実逃避をする以外なかった。こんなに思い悩むって事は、もしかしたら、私はアマの事を愛していたのかもしれない。
「いつになったら犯人は捕まるの?」「あの、こちらも、全力で捜査してますので」
「‥‥何? 私の言い方押しつけがましい?」
葬式が終わった後、私は警察に詰め寄った。
「ルイ、やめろよ」
シバさんが私を押し止めた。犯人も捕まえられないで、何葬式なんて来るんだよ。
私は憤りを抑えることが出来なかった。
「何? 人の事押しつけがましいって言うの? そんな権限ねーだろうお前らによ。じゃあ何? 犯人捕まえろっていう私はおこがましいの? アマが人殺しだから手ぇ抜いてんだろ。おめーらみんな死んでしまえ。みんな死にゃーいーんだよ。それで何もかも解決だろ」
「いい加減にしろよ、ルイ。言っている事が、支離滅裂だぞ」
私はその場で崩れて泣きわめいた。ふざけんなよ、死ねよ、ばかやろー。私のボキャブラリーの少なさがこんな所で暴露された。情けない。自分でも分かっていた。何て情けないんだ。私は。
アマが死んで、五日が経った。犯人はまだ捕まっていない。私はDesireにいた。シバさんに連れられて一度病院に行ったきり、外に出なくなった私を見かねて、シバさんが一緒に店番をしようと言ってくれたのだった。シバさんは、気まぐれに何度か私を抱こうとしたけど、首を絞めても苦しい顔をしなくなった私のことは抱けなかった。首を絞められると、苦しいという思いより先に早く殺して、と思ってしまう。
多分、それを口に出していたら、シバさんは私を殺してくれるだろう。でも、私は殺してと言わなかった。言葉を口にするのが億劫だったのか、この世に未練があるのか、まだアマは生きていると思いたいのか、私には分からない。ただ、私は生きている。アマがいない退屈な日々を生きている。シバさんに抱かれる事も出来ない退屈な日々を生きている。そして、私はつまみさえも食べるのを止めた。半年前に計った時は四十二キロあった体重が、三十四キロになっていた。物を食べて排泄する何て面倒臭い事、出来ればしたくない。
でも、酒しか飲まない私でも、排便する。これを宿便というらしい。腸の中には常にウンコが溜まってるんですよ、と連れられていった病院の先生が言っていた。先生は、このまま痩せてったら死にますよ、と穏やかな口調で私に言った。入院を勧められたけど、それはシバさんが断った。抱けない女なんて囲ったって、シバさんは一体どうするつもりなんだろう。
「ルイ、そこのラック整理して」
シバさんの言葉に私は素直に従い、今値段を貼ったばかりのピアスの袋をまとめてラックに向かった。シバさんはさっきから店のあらゆるところを掃除している。心機一転、って事なんだろうか。そう言えば、もう今年も残り少ない。寒さも厳しくなる一方だし、クリスマスなんていうイベントもすぐそこまで近づいている。年末の大掃除のつもりだろうか。
「ねえ、シバさん」
「お前さあ、そろそろさん付けで呼ぶのはやめない?」
「俺の名前は、柴田キヅキって言うんだ」
シバさんのマンションの表札に名前が書いてあったから、知っていた。
「女の名前みてえだろ、キヅキって。何でか知らないけど、みんなシバって呼ぶんだよな」
「なんて呼べばいいの?」
「キヅキでいいよ」
こういう普通のカップルならあるはずの会話が、アマと私にはなかった。だから、思い残す事がたくさんあるのかもしれない。もっと、普通の会話をすればよかった。家族の話とか、過去の話とか、名前とか、歳とか。そう、葬式の時初めて知った。アマは十八歳だって事。私は、生まれて初めて年下の男と付き合っていた事を、彼が死んでから知った。私は十九歳で、アマの一個年上だった。そんな事、出会ったその日に話すべきだったのだ。
「ギヅキ」 言いにくい。そう思ったけど、そう呼ぶことにした。
「何?」
「ここのラック、もう一杯で入らないんだけど」
「あー、適当でいいよ。隣のラックに掛けてもいいし。無理やり押し込んでもいいし」
私はラックにぎゅうぎゅうピアスを押し込んだ。かなり無理矢理だったけど、袋はラックに整列した。ピアスを見ていたら、アマの事が頭に浮かんだ。あれからというもの、舌の痛みも治まってきたというのに、私は舌ピを拡張する気にはなれない。褒めてくれる人もいない今、私の舌ピは意味を持たないのだろうか。もしかしたら、私がアマに言ったように、アマと同じ気持ちを共有したくてスプリットタンを目指していたのかもしれない。
後一つ拡張すれば、アマがメスを入れた00Gになる。00Gにしたら切ろうと思っていた。アマも熱意もなくなってしまった今、この舌ピに一体何の意味があるんだろう。私はまたカウンターに戻ってパイプ椅子に座るとボンヤリ宙を見つめた。何もする気がない。何かする事にも、それで何かが動くという事にも、今の私には関心がない。
「ルイ、お前の名前、聞いてもいいか?」
「聞きたいの?」
「聞きたいから訊いているだろう」
「私のルイはルイ・ヴィトンの…」
「本名を聞いているの」
「…‥中沢ルイ」
「本名だったんだ、ルイって。ルイ、家族は? 親はいるの?」
「私はいつも孤児に見られるけど、両親いるのよ。今埼玉に住んでるんじゃないかな」
「へえ、意外。今度挨拶しに行かなきゃな」
どうして、私は孤児に見られるのだろう。両親健在で、家族関係には今のところ何も支障はないというのに。シバさんはご機嫌な様子でラックにハタキをかけていた。
私はそんなシバさんみて、一日を過ごした。
次の日、私はDesireに行かなかった。警察に行った。朝方、電話があった。新しくいくつかの情報が入ったという。シバさんは店に出なければならなかったから、私が行くことにした。私はしっかり化粧して、アマの好きなワンピースを着た。寒かったら、カーディガンとコートを羽織った。
「押し付けられたタバコは、全てマルボロのメンソールでした。唾液の鑑定も進めています。それから、陰部に挿入されていたのは、アメリカから輸入されているEcstasyというお香で、種類がムスクでした」
そんな事分かって、どうすればいいんだよ、という憤りがまた怒りを増長させる。アマも、私も、シバさんも、マキも、みんなマルボロのメンソールだ。タバコの銘柄なんて分かっても嬉しくない。
「お香なんて、何処でも売ってるんでしょ」
「ええ、まあ。でも関東区域に限られます。それと、今日は中沢さんに聞きたいことがあるんです」
刑事の顔が一瞬緊張したのが分かった。
「雨田さん、バイセクシャルの気がありましたか?」
私の怒りはマックスになった。悪気があって聞いたわけじゃないのは重々承知だけど、この刑事の顔をシバさんに貰った人差し指の指輪で叩き潰してやりたかった。
「アマがレイプされてたとでも言うの?」
「…‥検死の時に解かったんですが」
私はフゥ、と息をつくと記憶を巡らせた。アマのセックスはいつも単調でアブノーマルなところなんて一つもなかったし、ほぼ毎日のように私とセックスしていた。こっちが嫌になる程単調だったんだ。そんなはずはない。アマが誰か他の男にレイプされていたなんて、考えただけでも反吐が出る。
「そんな気はありませんでした。断言出来ます。絶対にそんな趣味はないはずです」
警察とすれ違うたびに奴らを軽蔑の目で見つめつつ、私も署を出た。そして、収穫が無かった事を伝えるためにDesireに向かった。アマがレイプされたなんて、思いたくもなかった。大体、アマはどっかと言えばネコよりもタチの方だ。アマにそんな趣味があるはずない。
私はDesireのドアを開け、カウンターの中でタバコを吸っていたシバさんに弱々しく微笑んだ。シバさんに、アマが犯されていた事を話すつもりはなかった。アマの印象が汚れるのは、私の頭の中だけで充分だ。
「収穫無し」
シバさんは私の真似をするように弱々しく微笑んで「そうか」と呟いた。シバさんはアマが死んでからというもの、私に優しくなった。変わらず乱暴な言葉遣いをするけれど、どこか表情や行動の端にシバさんの心遣いや優しさを感じることが多くなった。シバさんは私が奥の部屋に連れていき、私が寝台に横になったままいたけど、シラフでは眠れそうにないと思い、起き上がって冷蔵庫を開けて。安い赤ワインを開け、ラッパ飲みした。
久々に食欲を感じた私は、冷蔵庫に入っていたパンを砕いて一口だけ食べた。イースト菌の匂いに、吐き気がした。パンを戻して冷蔵庫のドアを勢いよく閉めると、ワイン片手にデスクの椅子に腰掛け、バッグから化粧ポーチを出してあのアマがくれた、アマいわく愛の証の歯を眺めた。
手のひらに載せ、コロコロと転がしてみた。アマがいなくなった今、この二つの愛の証は何を意味するんだろう。こんな事をして、私は一体何を求めているんだろう。アマは私が手の届かないところに行ってから。私はこの歯をよく眺めるようになった。いつも、この歯をポーチにしまうたび、一つ諦めに近い気持ちが生まれる。
いつも、この歯を眺める習慣がなくなったら、私はアマを忘れた事になるんだろうか。私は歯を化粧ポーチにしまった。その時、私は目にある物が映った。デスクの半開きの引き出しから覗く、細い紙のパックだった。一瞬にして、最悪の結末を予想した。私が手に取った物、それはEcstasyの、ムスク。私は立ち上がった。
「買い物に行ってくるね」
驚いた顔で、どこに? と言うシバさんに振り返らず店を飛び出した、アジアン雑貨の店に向かった。駆け足だった。
息を切らしてDesireに帰ると、シバさんが心配そうな顔で私の頭を撫でた。
「ルイ、どこに行ったんだよ? 心配したぞ」
「お香、買ってきた。私、ムスク嫌いなの」
私はデスクからムスクのお香を持って来ると全部ひとまとめにしてパックごと半分に折ってゴミ箱に捨てた。
「ココナッツ買ってきた」
私はココナッツのお香に火を点け、お香の台に差した。
「どうかした? ルイ」
「ううん。何も。そうだキヅキ、髪の毛伸ばしてよ。私ね、長髪が好きなの」
私の言葉に、シバさんは笑った。前だったら、きっと「うるせぇ」とか言って冷たい目で睨んでいただろう。
「そうだな、たまには伸ばしてみるか」
その日、私はシバさんと一緒に家に帰って、少しだけご飯を食べた。気持ちが悪かったけど、シバさんがすごく喜んでくれたから、吐かなかった。ベッドに入って、シバさんが眠るまで添い寝をした。静かな空気の中、私はずっと頭の中で反吐が出そうな妄想を繰り返していた。シバさんが、アマを犯しながら、首を絞めている場面がリピートしていた。その時、もしかしたらアマは笑っていたんじゃないか、とか、シバさんは泣いてたんじゃないか、とか、色々想像をした。
もしもシバさんが犯人だとしたら、アマはその時シバさんが私にするよりも強く首を絞められていたという事は確かだ。シバさんが寝息をたてると、私はリビングでビールを飲んで、あのアマがくれた愛の証を、また眺めた。私は物置になっている玄関脇の棚をあさってトンカチを手に取った。二本の歯をビニールとタオルにくるみ、トンカチで砕いた。ボス、ボスという鈍い音が胸を震わせた。粉々になると、私はそれを口に含んで、ビールを飲み干した。それはビールの味がした、アマの愛の証は、私の身体の中に溶け込み、私になった。
次の日、私たちはDesireに出勤して、二人で店を開けた。私はほんの少しだけど、シバさんの買ってきたパンを食べた。シバさんはそんな私を満足げに眺めた。
「ねえ、キヅキ、お願いがあるの」
「何?」
私はワンピースを脱いで寝台に横になった。
「本当に、いいんだな」
私は黙ったままコクッと頷いた。シバさんあの機械を手に持った。そう、ボールペンみたいな機械で、私の背中の龍と麒麟に、瞳が入る。私の龍と麒麟は、目を持つ。命を持つ。いくよ‥‥シバさんの言葉と共に、私の背中に懐かしい痛みが走った。刺青を入れたあの時私は一体何のために入れたのだろう。今、私はこの刺青には意味があると自負できる。私自身が、命を持つために、私の龍と麒麟に目を入れるんだ。そう、龍と麒麟と一緒に、私は命を持つ。
「飛んでいかねえかな」
シバさんは私の背中に針を刺しながら言った。
「飛んでっちゃうかもね」
私はクスクスと笑ってシバさんの顔を盗み見た。シバさんは、もう私を犯せないかもしれないけど、きっと私のことを大事にしてくれる。大丈夫。アマを殺したのがシバさんであっても、アマを犯したのがシバさんであっても、大丈夫。龍と麒麟は目を見開いて、鏡越しに私を見つめていた。
閉店前に一人で部屋に帰った私は、舌ピを外し、舌先の残った肉をデンタルフロスデきつく縛ってみた。ぎゅっと結ぶと鈍痛が走った。もう残りは五ミリ程度だった、このま切ってしまおうかと思ったけど、私は眉バサミを手に取り、デンタルフロスをパチンと切った。デンタルフロスは弾けるようにほどけ、痛みはすぐに和らいだ。私はこれを求めていたのだろうか。この、無様にぽっかり空いた穴を、求めていのだろうか。舌の穴を鏡に映してみると、肉の断面が唾液に濡れて、テラテラと光っていた。
翌朝、明るい陽の光の中で目を開けた。ひどく喉が渇いていて、仕方なく起き上がると台所に向かった。冷蔵庫の中の冷え切った水をペットボトルのまま飲むと、舌の穴に水が抜けていく。まるで自分の中に川が出来たように、涼やかな水が私という体の下流へと流れ落ちていった。
シバさんはもそもそと起き出して、鏡向かっている私を不思議そうに見て、目を擦った。
「何しての?」
「私の中に川が出来たの」
「へえ。ねえ、俺さ、変な夢見たんだ」
「どんな?」
「昔仲が良かった友達がさあ、ヒップポップやってて、俺その友達と遊びに行く事になったんだ。でも俺待ち合わせにすげえ遅れちゃってさ、そしたら友達とその仲間が怒りを歌で表現していくんだよ。俺は五、六人に囲まれて歌われたんだ。ラップで怒りの歌」
私は、なかなか布団から出ないシバさんを見ながら、00Gに拡張したら、川の流れはもっと激しくなるんだろうか、なんて考えていた。陽の光が眩しすぎて、私は少しもっと激しくなるんだろうか、か、なんて考えていた。陽の光が眩しすぎて、私は少し目を細めた。
第二回すばる文学賞作 すばる2003年11月号掲載
金原ひとみ
蛇にピアス 2004年1月10日第一冊発行